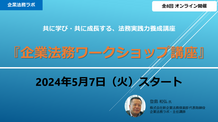QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎第27回 業務委託契約(契約条項)3
2022/07/01 契約法務

今回から業務委託契約の具体的条項について解説します。今回(最終回)は、以下のQ7~Q11です。
Q1:契約前文・目的
Q2:本業務の実施条件と受託者の協力
Q3:業務終了報告書の提出
Q4:成果物の納入・受入検査
Q5:委託料およびその支払条件
Q6:再委託等
Q7:任意解除
Q8:契約不適合責任
Q9:成果物の著作権
Q10:個人情報の取扱い
Q11:その他条項・契約書全体
なお、本稿で解説する業務委託契約で委託される業務は、成果物の納入を要しない業務または成果物の納入がある場合でもその成果物は提案書、調査・分析報告書等の文書である業務に限り、物品の製造やコンピュータプログラムの開発等は含まないものとします(これらの業務の委託に関する契約は製作物供給契約、ソフトウェア開発請負契約等は別の契約として解説)。また、本稿で解説する業務委託契約書(ひな型)全文のPDFはこちらにあります。
Q7:任意解除
A7: 以下に規定例を示します。
第7条 (任意解除) 1.別紙にその旨の記載がある場合には、甲は、別紙に記載された予告期間以上の期間を置いて乙に書面で通知することにより、理由の如何を問わず、任意に本契約を解除することができるものとする。但し、この場合、甲は、当該解除時点までに乙が本業務の実施のために費やした費用を乙に支払うものとする。 2.甲は、前項但書に定める支払の他、前項による本契約の解除に関し、乙に対し損害賠償その他の義務または責任を負わないものとする。 3.第1項に定める場合を除き、甲および乙は、本契約を任意に解除することはできないものとする。 |
6.任意解除 [甲の任意解除を定める場合に必要事項記入] ・予告期間: ...... [例:10日、1か月] |
【解 説】
例えば、コンサルティング契約、顧問契約等において、契約締結後、受託者の業務遂行レベルが委託者の期待に合わない等の場合があるので、契約を途中で任意に解除したい場合があります(契約違反等を理由とする解除は別途規定)。
民法上は、(準)委任の場合、委託者・受託者とも、いつでも契約を任意解除できます(但し一定の場合相手方の損害賠償要:651)。請負の場合、注文者は、請負人が仕事を完成しない間はいつでも任意解除できます(但し相手方の損害賠償要:641)。これに対し、本契約例では、(準)委任・請負を問わず、別紙にその旨の記載がある場合に限って、委託者(甲)のみが、事前予告をすること、および、当該解除時点までに受託者(乙)が本業務の実施のために費やした費用を補償することを条件として、任意解除できるものとしています。他方、それ以外の任意解除は双方ともできないものとしています(契約違反等による解除、合意解除は別)。おそらく、その方が実際の取引に適合すると考えたからです。
受託者(乙)にも任意解除権を与えたい場合は、上記の規定・別紙を修正する必要があります。
Q8:契約不適合責任
A8: 以下に規定例を示します。
|
第8条 (不適合に関する責任) 1.乙は、本業務についてその検収後に不適合が発見された場合には、本条に従い甲から通知があった場合に限り、本条に従い責任を負うものとする。 2.甲は、成果物の納入を要しない本業務について、第3条に定める対象業務の検収後に不適合を発見した場合には、その検収後1年以内にその旨並びにその具体的内容および理由を書面で乙に通知するものとし、乙は、当該通知を受けた場合には直ちにその内容を確認するものとする。 3.乙は、前項に従い通知された不適合が存在する場合、速やかにこれを是正するために必要な対象業務の修正または再実施を行うものとする。但し、乙は、甲乙書面で合意した場合には、これに代えて、委託料の一部または全額を返還するものとする。 4.甲は、成果物の納入を要する本業務について、第4条に定める検収後に不適合を発見した場合には、その検収後1年以内にその旨並びにその具体的内容および理由を書面で乙に通知するものとし、乙は、当該通知を受けた場合には直ちにその内容を確認するものとする。 5.乙は、前項に従い通知された不適合が存在する場合、速やかにこれを是正するために必要な成果物の修正を行うものとする。但し、乙は、甲乙書面で合意した場合には、これに代えて、委託料の一部または全額を返還するものとする。 |
【解 説】
(1)民法上の請負人の契約不適合責任
民法上、請負については、「請負人が種類又は内容に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は内容に関して契約の内容に適合しないとき)」は、注文者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知したことを条件として、「履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすること」ができるとされています(559:売買の規定の準用、636、637)。
なお、ここで、「仕事の目的物を注文者に引き渡したとき」とは、業務委託で言えば、例えば、提案書、調査・分析報告書等の成果物を委託者に納入した場合が、「その(仕事の目的物の)引渡しを要しない場合」とは、例えば、警備、清掃、運送等の場合が該当するでしょう。
なお、上記の1年の期間制限の他、請負人の責任追及にも、民法166条第1項の債権の消滅時効の適用がありますから、その追及が可能な期間は成果物納入・仕事の完成の時[1]から最大10年(166(2)二号)と考えられます。
(2)民法上の(準)委任の受託者の受託事務に関する責任 [2]
民法上、(準)委任については、請負のような契約不適合責任は規定されていません。従って、(準)委任の受託者の責任は軽いという見方があるかもしれません。しかしながら、(準)委任の受託者は、(準)委任の本旨に従い、善管注意義務(その業務分野の専門業者としての注意義務)を尽くして委託業務を処理する義務を負っています。従って、受託者が委託業務を、(i)委任の本旨(本契約例では「別紙に定める内容および実施条件」)に従って実施していなかったこと、または、(ii)委託業務の遂行方法や結果について善管注意義務を尽くしていなかったことが認定されれば、民法第412条以下の債務不履行責任を問われ、委託者は、履行の強制(414)、損害賠償(415)等を請求することができます。
この場合、上記(i)については、契約に委託業務の内容や実施条件が明確・客観的に定められていれば、委託者は比較的容易にその違反を主張・立証にできる場合が多いでしょう。一方、(ii)については、善管注意義務の内容・水準は個々の業務内容と個別事情により様々でありしかも幅があること、受託者の行為がその水準から逸脱したと言えるのかも個別事情によること等、委託者が主張・立証することが困難な点が多く、その違反が重大で誰から誰が見ても明らかである等の場合を除き、受託者の責任追及は一般に容易でないと言えるでしょう。その意味で、(準)委任の受託者の責任は軽くはないものの追及が困難な場合が多いと言えます。
(準)委任の受託者の責任追及には、請負のように1年の期間制限はなく、民法166条第1項の債権の消滅時効の適用しかありませんから、委託業務終了から最大10年(166(2)二号)と考えられます。
(3)本契約例
民法の規定内容は、例えば、以下のような点において、取引の迅速処理・解決が要請される企業間取引の実務に合いません。
(a)請負の場合、注文主は、民法上、その不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知すれば成果物納入・仕事の完成の時から10年以内なら請負人の責任を追及できる(現実の取引では、通常、成果物納入・仕事の完成の時から1年程度)。
(b)(準)委任の場合は、民法上、請負の1年の期間制限さえないので、受託者は委託業務終了から最大10年も責任追及される可能性がある。
また、実務上は同じように扱われる業務委託なのに、それが請負に該当する場合と準委任に該当する場合で、受託者の責任がその内容・期間とも違うことも分かりにくく、また、必ずしもそうでなければならないようにも思われません。
そこで、本契約例では、民法の規定内容に関係なく、(準)委任業務でも請負業務でも、その業務または成果物が、本契約に従い善管注意義務を尽くして実施・作成された(2条1項)ものでない場合、すなわち不適合(3条2項、4条2項)の場合に、検収後1年以内に委託者から通知があったことを条件としてその不適合を是正することを、受託者の責任としています(8条)。
(第8条第2項・第3項)「成果物の納入を要しない本業務」には請負に該当する業務(例:警備、清掃、運送)と、(準)委任に該当する業務(例:データ入力・計算その他情報処理代行)があります。これらの業務、特に(準)委任に該当する業務についての受託者の責任に関してはこれについて具体的に規定した契約例はあまり見かけません。しかし、契約に規定がなければ、上記のように取引実務に合わない民法の定めによることになってしまいます。従って、本契約例では、どちらの業務についても、委託者は、検収後1年内の通知を条件として、不適合の修正・再実施または委託料の一部返金を請求可能としています。
(第8条第4項・第5項)成果物を納入する場合については、委託者は、検収後1年内の通知を条件として、不適合の修正または委託料の一部返金を請求可能としています。
Q9:成果物の著作権
A9: 以下に規定例を示します。
| (例1:受託者に著作権が留保される規定例) 第9条 (成果物の著作権の取扱い) 1.成果物が著作物に該当する場合、乙は、成果物に関する自己の著作権を留保する。 2.甲は、前項の成果物を利用(複製および翻案を含む。以下同じ)すること、および、別紙にその旨の定めがある場合には、第三者に当該成果物を利用させることができるものとする。乙は、これらの利用について著作者人格権を行使しないものとする。 (例2:委託者に著作権が譲渡される規定例) 第9条 (成果物の著作権の取扱い) 1.成果物が著作物に該当する場合、成果物についてその作成上新たに生じた著作権(著作権法第27 条および第28 条の権利を含む)は、委託料完済時に乙から甲に譲渡されたものとする。なお、当該著作権譲渡の対価は委託料に含まれるものとする。 2.甲は、前項の成果物を利用(複製および翻案を含む。以下同じ)すること、および、別紙にその旨の定めがある場合には、第三者に当該成果物を利用させることができるものとする。乙は、これらの利用について著作者人格権を行使しないものとする。 |
7.著作物である成果物の第三者による利用:[成果物が著作物に該当する場合であって、甲が、当該成果物を第三者に利用させる場合には以下の事項を範囲を記載] (1)対象成果物: ...... (2)第三者の範囲: ...... |
【解 説】
成果物が例えば調査・分析報告書等で著作物に該当する場合、その著作権の帰属が問題となります。これら調査・分析報告書等の中には例えば以下のような様々な部分が含まれている可能性があり、それぞれ以下の者に著作権が帰属しています。
(i)乙(厳密にはその従業員。以下同様)が全く新たに記述した部分:乙に帰属
(ii)乙が過去に執筆したものから引用した部分:乙に帰属
(iii)甲の著作物(例:甲社内文書)から引用した部分:甲に帰属
(iv)第三者の著作物(例:第三者刊行物)から引用した部分:第三者に帰属
上記の内、甲乙間でその譲渡または留保を自由に決めることができるのは(i)と(ii)だけです。
(例1)第1項で、上記(i),(ii)の乙の著作権は乙に留保され甲には譲渡されないものとしています。しかし、第2項では、甲は、成果物の全部を自ら利用(複製および翻案を含む)すること、および、別紙にその旨の定めがある場合には、第三者(例:関連会社)に成果物を自ら利用させることができるものとしています。
(例2)第1項で、上記(i)の成果物についてその作成上新たに生じた著作権のみ甲に譲渡することとしています。第2項は例1の第2項と同じ内容です。
(著作権を委託者に譲渡するか否か)多くの委託者は受託者の著作権の譲渡を要求します。しかし、例えば、ある分野専門の調査・分析会社(受託者)が毎回どの顧客(委託者)にも調査・分析報告書の著作権を譲渡していたのでは、他の顧客から同様の事項の調査・分析報告書の作成を委託された場合でも、過去の記述を利用できず常にゼロから作成せざるを得ません。一方、顧客(委託者)としては、著作権の帰属に関係なく、例1・例2の第2項のように、成果物を自己利用および自己の望む第三者に利用させることができれば通常は十分な筈です。従って、例1の第1項では受託者(乙)に著作権が留保されるものとしています。
しかし、それでも、なお著作権の譲渡を要求する委託者もいるので、例2の第1項では「成果物についてその作成上新たに生じた著作権」(上記(i)が該当)に限り委託者に譲渡するものとしています。「新たに」としたのは、乙とすれば上記(ii)の従来から保有している著作権まで譲渡されてしまうのは不合理であり、甲としてもその譲渡を受けなくても第2項があれば通常十分だからです。
(秘密保持義務との関係)なお、調査・分析報告書中に甲の秘密情報に該当する記述が含まれている場合には、仮にその部分について乙に著作権が留保されたとしても、乙は別途設けられる秘密保持条項により制限され、その部分を自由に利用・開示できるわけではありません。
(例2 - 第9条第1項)「(著作権法第27 条および第28 条の権利を含む)」:この括弧書き部分がある理由は、著作権法61条第2項で「2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する」と規定されているからです。なお、27条は翻訳権、翻案権等、28条は二次的著作物の利用に関する原著作者の権利関する規定です。
「なお、当該著作権譲渡の対価は委託料に含まれるものとする」:この部分は後述の指針を意識したものです。
(特許権等の取扱い)物品の製造委託契約やソフトウェア開発請負契約では、成果物(物品、ソフトウェア)の特許権等の取扱いも問題になりますが、それらの契約は、それぞれ、検討を要する特有の事項・契約条項があるので、業務委託契約書としてよりは別個独立した契約書の類型として検討した方が適切でしょう。本契約例では、成果物としては文書等のみ想定しています。
(独占禁止法との関係)第24回Q4で触れた公取委の「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独禁法上の指針」(最終改正:平成29年6月16日)では、「7 情報成果物に係る権利等の一方的取扱い」で、要旨以下のような記述があります。
(要旨)受託者が作成した情報成果物について、取引上優越した地位にある委託者が、一方的に当該成果物に係る著作権、特許権等の権利を委託者に譲渡させる場合、その譲渡の対価を別途支払ったり、当該対価を含む形で対価に係る交渉を行っていると認められる場合を除き、優越的地位の濫用として問題を生じやすい。
なお、ここで、著作権については、受託者が業務委託により情報成果物を作成すればそれについて著作権が発生することが通常なので、委託料の中に著作権譲渡の対価が含まれているとの主張は、特許権に比べればし易いかもしれません。一方、特許権については、特許を受けることができる程の技術的進歩性を有する発明は、委託業務を行えば必ず生まれるものではなく、受託者の特別の能力と努力の結果初めて生まれるとも考えられます。従って、事前には、生まれるか否か、また、その内容も分からない発明に関する特許権の譲渡対価を予め織り込んで委託料を決めることは不可能とも思え、委託料の中に特許権譲渡の対価が含まれているという主張は難しいかもしれません。
Q10:個人情報の取扱い
A10: 以下に規定例を示します。
|
第10条 (個人情報の取扱い) 1.甲および乙は、本契約に関連し相手方から「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という)に定める個人情報を取得した場合には、個人情報保護法に従いこれを取扱うものとする。 2.甲および乙は、本業務に、個人情報保護法上の個人データの取扱いの委託に係る業務が含まれる場合、別途、当該個人データに関し、その安全管理措置、乙における取扱状況を甲が把握するための措置等に関する定めを含む契約を締結するものとし、乙は、当該契約に従い、当該業務を行うものとする。 |
【解 説】
(第10条第1項)本業務の内容如何にかかわらず適用される規定です。
(第10条第2項)個人情報保護法上、「個人情報取扱事業者[委託者]は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者[受託者]に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない」(25)とされています。また、「個人データの保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」によれば、委託者は、「委託契約には、当該個人データの取扱いに関する、必要かつ適切な安全管理措置として、委託元、委託先双方が同意した内容とともに、委託先における委託された個人データの取扱状況を委託元が合理的に把握することを盛り込むことが望ましい」とされています。そこで、本項でその契約に関し規定しています。
Q11:その他条項・契約書全体
A11: 前記した条項以外で、業務委託契約に含まれる条項としては、本シリーズで既に解説した各種契約共通の条項が考えらえます。これらに関しては、それぞれ、以下の各回の解説を参照して下さい。
第10回 解除条項・期限の利益喪失条項
第11回 秘密保持条項(1)
第12回 秘密保持条項(2)
第13回 反社会的勢力排除条項
第14回 譲渡制限条項
第15回 損害賠償条項(法律上の原則など総論)
第16回 損害賠償条項(責任制限条項)
第17回 その他共通条項(契約終了後に存続する規定/紛争解決/完全合意/中途解除/不可抗力/個人情報の取扱い/通知/契約の規定の分離(可能性))
今回はここまでです。
【注】
[1] 【最高裁判例】 最高裁平成13年11月27日判決。民法改正前の売買の瑕疵担保責任に関する事案であるが, 売買目的物(宅地)引渡しから21年余りを経過した後の瑕疵担保による損害賠償請求事案。最高裁は以下のように判断。
・瑕疵担保による損害賠償請求権には, 買主が事実を知った日から1年という制限(除斥期間)の他, 同請求権は債権に当たることは明らかであるから, 債権の消滅時効の規定(旧166条1項:「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」行使しないときは時効消滅する)の適用が排除されることはない。
・瑕疵担保による損害賠償請求権に消滅時効の規定の適用がないとすると,買主が瑕疵に気付かない限り,買主の権利が永久に存続することになるが,これは売主に過大な負担を課するものであって,適当といえない。したがって,同請求権には消滅時効の規定の適用があり,「権利を行使することができる時から10年間」の消滅時効は,買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。
— 上記は, 民法改正後の契約不適合責任にも当てはまると解されている。(参考) 根岸透「契約不適合による担保責任の期間」2021年9月15日, 田宮合同法律事務所「民法改正によって瑕疵担保責任に関する「時効」や「除斥期間」(じょせききかん)はどう変わる?」不動産売買の法律アドバイス2017年11月号, 三井住友トラスト不動産サイト
[2] 【(準)委任の受託者の責任】 (参考) (1) 久礼美紀子「請負契約と準委任契約」内田鮫島法律事務所、(2) 上山浩・若松牧『「準委任契約の誤解を解きほぐす─システム開発契約を題材に─』知財管理 Vol. 70 No. 5 2020
【免責条項】
本コラムは筆者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラムに関連し発生し得る一切の損害等について当社および筆者は責任を負いません。実際の業務においては, 自己責任の下, 必要に応じ適宜弁護士のアドバイスを仰ぐ等してご対応ください。
| 【筆者プロフィール】 浅井 敏雄 (あさい としお) 企業法務関連の研究を行うUniLaw企業法務研究所代表/一般社団法人GBL研究所理事 1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで企業法務に従事。法務・知的財産部門の責任者を日本・米系・仏系の三社で歴任。1998年弁理士試験合格 (現在は非登録)。2003年Temple University Law School (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事, 国際商事研究学会会員, 国際取引法学会会員, IAPP (International Association of Privacy Professionals) 会員, CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe) 【発表論文・書籍一覧】 |
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
 大東 泰雄弁護士
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- ニュース
- 公取委が「ポコチャ」のライバー事務所に注意、独禁法が禁ずる「取引妨害」とは2025.12.10
- ライブ配信アプリ「ポコチャ」で配信する「ライバー」が所属する大手事務所4社が、退社したライバー...

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- セミナー
 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30