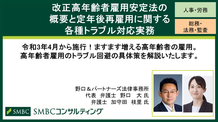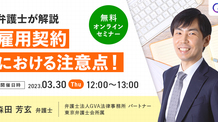社員の有休取得義務化法案は労働環境を改善するか?
2016/04/11 労務法務, 労働法全般, その他

はじめに
厚生労働省は、2016年4月から社員に年間で5日分の有給休暇を取得させる義務を企業に課す方向で、労働基準法改正の調整を進めていました。しかし、2015年9月27日に終わった第189回通常国会では、労働基準法改正案は継続審議となり、成立は見送られることとなりました。もっとも、この法案が今国会で成立するかどうかはともかく、労働者の権利を尊重する世界的な流れを考えますと、有給休暇を取得させる義務を企業に課す労働基準法改正法案は数年のうちにどこかで成立すると予想されます。今回は、先取りという形で、労働基準法改正案の内容と会社に課される義務について見ていきたいと思います。
1. 現行の有給休暇制度の概要
有給休暇は、一定の期間勤続した労働者が心身の疲れをいやし、ゆとりのある生活をするために与えられる休暇のことで労働基準法により定められているものです。この有給休暇を会社から付与されるためには条件が二つあります。
①. 雇い入れの日から6カ月が経過していること
②. 算定期間の8割以上を出勤していること
この条件を満たすと、有給休暇が付与されます。最初に付与されるのは、雇い入れの日から6カ月が経過した時です。その後、1年が経過する度に所定の日数が付与されることになっています。
2. 労働基準法「改正案」の内容
改正案によると、企業は年10日以上の年休を付与している社員に対して、年5日分の有休を取らせなければならないとされています。ただし、社員がすでに5日以上の有休を取得している場合には、企業の義務は発生しないことになります。例えば、社員がその年に3日の有休を取得している場合、年5日に満たない残り2日分を必ず企業側で取得させなければならないということになります。また、企業は、有給休暇の取得状況を正しく把握しておくために、有給休暇の管理簿の作成も義務付けられ、これに違反した企業に対しては、罰則が科されることになります。
3. 義務化を提案する背景
社員の有休取得を企業に義務付けようとする背景には、日本の有休取得率が欧米諸国と比べて、極めて低いという事実が挙げられます。Harris interactive社の調査によりますと、日本の有給休暇消化率は50パーセントとのことで、これは先進諸国の中でも群を抜いて低い数値です。つまり、現行の有給休暇制度では、6年半以上働けば年20日の有休が付与される仕組みですが、実際には半分の10日程度しか有休を取れていないということになります。また、小売、娯楽業、サービス業、医療福祉、宿泊、飲食業などは、これよりもさらに取得率が低いと言われています。
コメント
有休休暇の取得が義務化された場合、小売、娯楽業、サービス業、医療福祉、宿泊、飲食業など特に取得率の低かった業種での労働環境の改善が期待されます。さらに、職場の空気により有休を「取りにくかった」人たちも、有休が義務に変わることで、周りの目を気にせず休めるようになると考えられます。その一方で、長時間労働が常態化している企業においては、有給休暇取得の義務化だけでは足らず、社内の業務分担の根本的な改善が必要だと言えます。有給休暇取得後、休暇中に溜まった業務のしわ寄せが過度に普段の業務に上乗せされた場合、結局は残業時間の増大が常態化してしまう懸念があるからです。
そのため、例えば、有休休暇を取得した労働者に対して、休暇明けに過度の負担が行かないよう、従業員間で業務をカバーし合うなどの仕組み作りが必要となって来ますが、社内の業務量と人員数が変わらないにも関わらず、有給休暇の取得により労働日数だけ減少されるとなると、各従業員の日常の業務負担がこれまでよりも増大することは明白です。結局のところ、本当の意味での労働環境の改善のためには、企業側が従業員の人数を増やし、それと並行して業務の適切な分配を行うことで、自社の従業員の日常的な業務負担自体を軽減して行くより他ないのではないでしょうか。もちろん、従業員の増加による給与コストの増大は企業側にとって小さくない負担となりますが、労働環境の改善は、従業員の自社に対するロイヤルティーを高め、離職率の低下・業務効率の向上へと繋がりますので、人員増による一時的な給与負担増は、長期的には、企業にしっかりと利益となって還元されると考えられます。
昨今、長時間労働の常態化による離職率の増大、離職率の増大による既存社員の負担の増大、追加人員を補充しない(出来ない)ことによるさらなる離職率の増大と、負のスパイラルに陥っている企業が増えて来ていますが、そういった企業は、今回の改正案の検討を契機に、長期的視野を持って、思い切って自社の従業員の業務負担の軽減に取り組まれてみてはいかがでしょうか。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
 大東 泰雄弁護士
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- ニュース
- 「患者からのクレームの多さ」を理由とした懲戒解雇は無効 ー東京地裁2026.1.28
- 山梨県の市立病院で理学療法士として働いていた男性(44)が「患者からのクレームが多いことを理由...

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- セミナー
 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 採用困難職種“企業法務” — 管理部門採用で求職者に“選ばれる”採用の工夫
- NEW
- 2026/03/10
- 13:00~14:00
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階