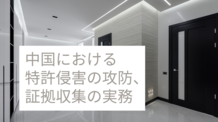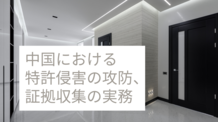海外企業との売買契約における法律の適用関係まとめ
2017/10/22 海外法務, 外国法

はじめに
日本の企業が海外の企業と売買契約を結ぶ場合、企業法務担当者は日本の企業と取引をする場合と異なり、当該契約に適用される法律が何なのか確認するところから始めなければなりません。特に売買契約である場合には、多くの取引で国際物品売買契約に関する国際連合条約(以下、「ウィーン売買条約」)の適用を想定しなければなりません。そこで、今回は日本の企業が海外の企業と売買契約を締結する場合の法律の適用関係についてまとめてみました。
ウィーン売買条約とは
まず、海外企業との売買契約においては、ウィーン売買条約の適用を一番に考える必要があります。ウィーン売買条約は、1988年1月の条約発効以来、2011年9月現在で米国、カナダ、中国、韓国、ドイツ、イタリア、フランス、オーストラリア、ロシア等77カ国が締約しており、日本では2009年8月1日から発効しています。内容は、異なる国の間で物品売買をする場合に用されるものです。したがって、サービスの提供についての契約や業務委託契約・コンサルティング契約などの物品売買ではない契約書には適用がありません。また、一般消費者との取引には適用されません。
当事者の所在する国がウィーン売買条約に締結していた場合には、ウィーン売買条約の適用可能性がありますので、確認が必要となります。
ウィーン売買条約概要:日本
ウィーン売買条約についての解説図(PDF):財務省
ウィーン売買条約:実践貿易アドバイザー/海外営業研修所
適用関係
では、海外の企業と売買契約を締結する場合にウィーン売買条約と競合しうる他の法律等との適用関係についてみていきます。適用関係を注意すべきものとしては、国際私法、当事者間の合意、準拠法、慣例および国内法の協定との関係が問題となります。
Ⅰ まず、売買契約当事者双方の営業所所在地国がウィーン売買条約を締約している場合はウィーン売買条約が適用されます(第1条第1項)。条約は法律よりも優先されるため、注意が必要です。日本はすでに本条約を締約しているので、企業法務担当者は相手方の営業所所在地国がどこであるかを調べて、その国が条約締約国であれば本条約が適用されます。
Ⅱ 次に、相手方の営業所所在地国が本条約の締約国ではない場合は、国際私法の準則によれば締約国の法の適用が導かれる場合に適用されます(第1条第2項)。「国際私法の準則」とは、国際紛争等が生じた際にどの国の法が適用されるのかを決めるための法律です。日本でいえば「法の適用に関する通則法」がこれに該当します。この「国際私法の準則」によって、日本等の締約国の法の適用が導かれる場合には、本条約が適用されます。イギリス、インド、ブラジル等の国は本条約を締約していないので、企業法務担当者はこれらの国と取引をするときは注意が必要です。
Ⅲ ウィーン売買条約においては適用を排除または変更することができます(第6条)。仮にウィーン売買条約の適用を排除したければ、企業法務担当者は、売買契約において明示的に同条約を排除する文言を規定しなければなりません。単に、別途準拠法を定めただけでは、原則的には、ウィーン売買条約が優先されることになります。例えば、英文売買契約書において日本法を準拠法とするとし、民法や商法と矛盾する内容がウィーン売買条約に書かれていた場合、日本の民法や商法よりも上位にあるのがウィーン売買条約ですので、ウィーン売買条約の内容が適用されることになります(ただし、明示的な排除規定がなくとも、準拠法を定めることで同時にウィーン売買条約を排除することが、意図されていたと証明できる場合はこの限りではありません)。もっとも、ウィーン売買条約は、全面適用、全面排除のほかに、一部はそのまま残し一部は改正するといった調整が可能です。ウィーン売買条約の内容は日本の民法とは異なる箇所も多いため、契約によって排除する条項を選択するということもできます。
ウィーン売買条約を上手く使う:弁護士法人クレア法律事務所
Ⅳ ウィーン売買条約には、当事者が合意した慣習および当事者間で確立した慣行に拘束されるという規定があります(第9条第1項)。このことから、ウィーン売買条約が適用された場合でも、合意した慣習や当事者間で確立した慣行はウィーン売買条約に優先することになります。ここでは合意した場合にとどまらず、合意がなされていなくても業界の間などですでに確立した慣行であれば、ウィーン売買条約の規定に優先するという点が重要です。ここでいう「慣習」には、インコタームズのような国際慣習も含まれます。売買契約書にインコタームズによることの明示的に規定があれば、ウィーン売買条約の規定に優先してインコタームズの規定が適用されることになります。
Ⅴ 国内法の強行規定(契約が公序良俗に則ったものかどうかなど)の適用関係については、ウィーン売買条約ではもともとこのような強行規定を示していません。そのため、どちらを優先するということなく当然従うこととなります。
おわりに
海外の企業と売買契約を締結しようとする場合、どの法律が適用されるかが契約締結の出発点です。仮に、あらかじめウィーン売買条約の適用を意図していたのであれば問題ありませんが、準拠法を日本法とすると書いた意図が、常に日本法で解釈・解決したいというものであった場合、ウィーン売買条約の存在を知らなかったということであると問題を生じることになりますので注意が必要です。そして、ウィーン条約の内容は日本法と異なるものと、日本法より日本の企業に有利に働くものもありますので、条約を適用するかどうか、適用とするとしても排除する条項は無いか項目ごとに検討が必要です。高度な法的判断が必要となりますので、海外の企業との取引の際に会社内部にウィーン条約の専門家がいない場合には、外部のウィーン条約に詳しい弁護士と相談する事をお勧めします。
新着情報

- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...

- 解説動画
 岡 伸夫弁護士
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- ニュース
- スリムビューティハウスに3ヶ月間の業務停止命令(特定商取引法違反疑い)2026.2.9
- エステ大手「スリムビューティハウス」に対し、消費者庁が3ヶ月間の業務停止命令を出していたことが...

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
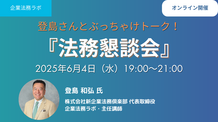
- セミナー
 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階

- 解説動画
 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士) 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年) 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号