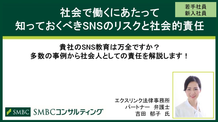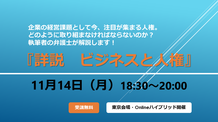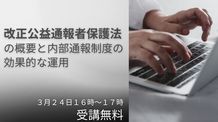今、内部通報制度が東芝を揺さぶる
2015/09/01 コンプライアンス, 民法・商法, その他

内部通報が東芝を動かした
東芝は8月31日、予定していた2015年3月期決算及び有価証券報告書の提出を延期すると発表した。東芝の発表によれば、「複数の国内・海外子会社において会計処理の適切性について調査が必要となる事象が新たに発生し」たという理由が挙げられているが、その背景には、不適切会計を告発する従業員の内部通報や監査法人の監査が多数あったという。
第三者委員会が7月20日に提出した報告書においては、東芝内で内部通報制度が十分活用されていないことが指摘されていたが、その後現在に至り内部通報がさかんに行われていることはどういう意味を持つのだろうか。
内部通報制度のポイント
内部通報制度とは、従業員が企業の不正・問題点を通報する制度のことである。コンプライアンス強化を目的として、いわゆるCSR事業の一つとして制度を設けている企業も多い。
東芝においては、2000年1月に内部通報制度を設け、メールや電話などによって従業員からの通報を受け付けていた。 2006年4月には、物品の調達、工事発注などの取引に関連した従業員のコンプライアンス違反を防止するために、取引先から通報を受け付ける制度も取り入れていた。その一方、内部通報の件数については年に61件(2013年度)と、従業員数の多い大企業としては少ないようにも感じる。この点が第三者委員会から指摘されているのだろう。
内部通報制度が機能すれば、自浄作用がはたらき不正を早期に、あるいは事前に抑止することができるはずである。東芝の内部通報制度自体は他の企業と比べても見劣りしない、十分なものであった。しかしこの制度が十分に活用されていなかった。
制度の実情
この点を考えるにおいては、内部通報制度が実情どのように扱われていたのか、という点が重要となるだろう。
興味深い事例に、オリンパスにおける内部通報事件(東京高裁平成23年8月31日判決)がある。これは、内部通報を行ったことに対する報復人事がなされたとして従業員から配転無効及び損害賠償を請求する訴訟が提起されたものであった。内部通報の守秘義務が守られず通報者が不利益を被ったというケースである。
このケースでも内部通報制度自体は存在していた。しかし、現実には十分な管理体制が敷かれていたとはいえず、通報すれば何らかの不利益を被るというデメリットが存在していたのである。
つまり、制度が設けられていること自体では、直ちに内部通報制度が自浄作用をもたらすとはいえない。実際には形式だけの制度となっていないか、その時々の企業風土に密接に結びつくものとして考えなければならないのである。
内部通報増加の背景とは
そうすれば、今回の東芝の内部通報の増加は、企業内の風土の変化という点に原因を求めることができるかも知れない。
風土の変化の原因は様々考えられる。この度の不正会計処理の発覚を契機として、第三者委員会が立ち上がり内部通報制度の利用を促したということ、不正を糾弾する世論が増え社内の倫理より社会の倫理を優先しようと考える者が現れたこと、あるいは企業政治の変革を察知し、言わば不正を働いた「沈みかかった舟」の追い出しをはかる派閥が現れようとしているのかも知れない。それらが渾然一体となって、内部通報が許容される「雰囲気」が生じ、これまで抑圧されていた報告が一挙にあがったのではないだろうか。
同じ内部通報制度を設けていたとしても、企業の風土の変化によってその有効性は変化する。今後の内部通報制度は、このことを認識した上で、企業の風土に影響されない独立した強固な制度を設計する必要があるのではないだろうか。
関連コンテンツ
新着情報

- セミナー
 片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長) 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー) 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- まとめ
- 経済安全保障法務:中国の改正国家秘密保護法の概要2024.3.15
- 2024年2月27日, 中国では国家秘密保護法(原文:中华人民共和国保守国家秘密法)の改正が成...
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- ニュース
- グーグルマップの低評価口コミによる名誉権・営業権の侵害は認められず ―仙台地裁2025.12.3
- グーグル地図サービス「グーグルマップ」のクチコミ欄で最低評価の「星一つ」を付けられたとして宮城...

- 解説動画
 大東 泰雄弁護士
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階