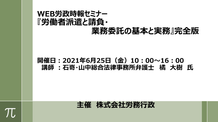選挙に行けない...成年被後見人の投票を拒む法律の壁
2011/07/05 法務相談一般, 民法・商法, その他
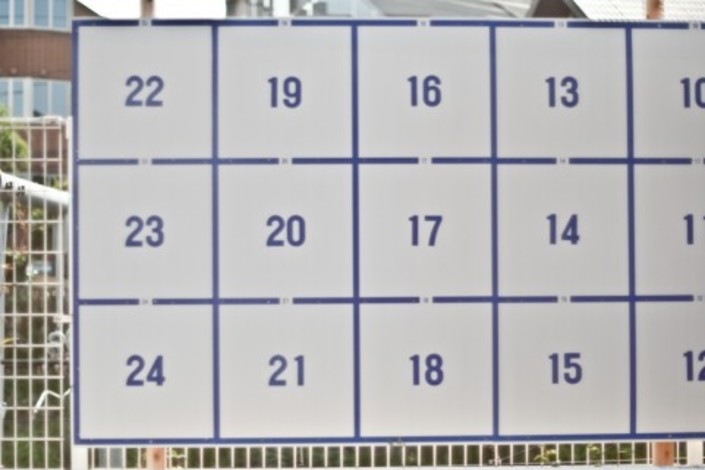
後を絶たない、公職選挙法違憲訴訟
成年後見制度を利用すると選挙権が喪失する公職選挙法の規定は憲法違反であるとして、知的障害をもつ男性が国を相手取り、選挙権の確認と慰謝料を求める訴訟を京都地裁に提起した。成年後見制度利用者が提起する選挙権確認訴訟は、今年の2月に東京地裁、4月にさいたま地裁に提起されており、今回は3例目となる。現行の成年後見制度は、従来の禁治産制度が2000年に廃止されるとともに移行したものだが、公職選挙法は依然として成年被後見人の選挙権を否定している。
公職選挙法
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない
一 成年被後見人
なぜ、選挙権を認めないのか
公職選挙法はなぜ成年被後見人の選挙権を否定するのか。その理由としては、①成年被後見人は事理弁識能力を欠くため投票に必要な判断ができない、②(①と関連して)現実的に投票行動を行うことが困難である、あるいは成年被後見人以外の者による不正な投票行為の虞があるという点が考えられる(日本弁護士連合会「成年後見制度に関する改善提言」参照)。しかし、成年被後見人の事理弁識能力は回復可能性があることを法(民法7条、973条2項参照)も予定しており、一律に選挙権を奪うべきではない。また、本当に事理弁識能力がない場合にはそもそも投票を行うことができず、判断能力のないまま投票を行う危険性を危惧する必要はないのではないか。さらに、成年被後見人以外の者の悪用については、抽象的な危険性に過ぎず、またそれを防ぐ法律の整備こそがなされるべきである。
総評
成年後見制度は財産管理能力がない者の行為能力を制限することで、成年被後見人の財産を保護し、かつ、取引の安全を図ることを目的とする。そこで問題とされるのは財産管理の能力であり、選挙で投票する能力とは別次元の能力のはずである。また、成年後見制度は、知的障害をもつ者の自己決定権の尊重とノーマライゼーションを理念に掲げ成立した制度であるが、民主主義の前提をなす選挙権の付与はその理念達成のために不可欠ではないだろうか。憲法は成年者による普通選挙を保障しており(15条3項)、不合理な差別を禁止している(44条但書)。本人に責任のないやむを得ない事情で成年被後見人になった者を犯罪を犯したものと同列に扱い、選挙権を否定する現公職選挙法は選挙権を不当に侵害するものとして違憲性の疑いが高いと思われる。
関連リンク
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 解説動画
 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌)) 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- ニュース
- 「患者からのクレームの多さ」を理由とした懲戒解雇は無効 ー東京地裁2026.1.28
- NEW
- 山梨県の市立病院で理学療法士として働いていた男性(44)が「患者からのクレームが多いことを理由...

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
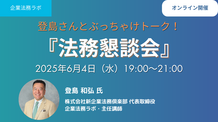
- セミナー
 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード