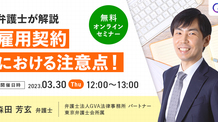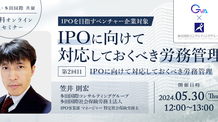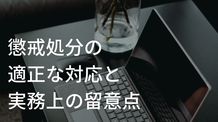NHKラジオセンター職員、交通費不正申告で懲戒処分
2023/01/18 労務法務, 労働法全般

はじめに
NHKは1月13日、同社のラジオ番組を制作するNHKラジオセンターの50代職員に対し、交通費の不正請求を理由に、停職1ヶ月の懲戒処分(20日付)を下すと発表しました。同職員は、2021年9月から昨年6月にかけて、出勤や取材などで発生した交通費について実際とは違った経路を申告したり、乗っていない区間を申告するなどして、50回にわたり、合計10万円近くを不正請求していたということです。職員は事実関係を認め、全額を弁済しています。また、同職員の直属の上司ら4人を厳重注意としています。
不正受給の例
交通費の不正受給はどういった場合に発生するのでしょうか。大きく以下の4つのパターンが挙げられます。
(1)公共交通機関の利用を申告したが実際には徒歩、自家用車
電車賃を浮かす目的で、申告している駅より数駅手前の駅で降りていたり、自家用車で通勤している例が挙げられます。
(2)会社に申告している場所とは違う家に住んでいる
住民票は申告地でも、会社の近くに部屋を借りたり、結婚などでより近場に引っ越した場合には、その場所からの通勤手当が交通費受給の対象となります。
(3)高い路線を申告する
経由地、利用する路線やルートにより料金が高くなります。
実際にはより安いルートを利用していると、その差額分を不正受給していることになります。
(4)住民票を移すなどし、虚偽申告をしている
引越しの際に住民票を移し忘れていたケースもありますが、中にはあえて移さなかった例や、引っ越していないのに少し離れた実家や親戚宅に住民票を移す、偽造するケースもあります。
会社としての対処は?
では不正が発覚した場合、会社としてどのような対応が求められるのでしょうか。
・事実確認を行う
実際にどのルートを利用し、どのぐらいの期間で不正を行ったのか。また、不正を行った理由、背景についてしっかり話を聞くことが重要です。不正受給の事実がわかるものや、万が一不正受給の手口などが悪質な場合、その悪質さを証明できる証拠を集めることも重要です。後日、従業員側が処分の有効性をめぐって法的に訴える場合があるためです。
・返還を求める
悪質性の低さ、高さに関わらず、不正受給分は返還を求めることができます。ただし、この請求権には時効があるため注意が必要です。不当利得返還請求権の消滅時効は、原則5年、最長10年となっています。不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間とされています。
・懲戒処分を下す
聞き取り調査などで故意によるもので、悪質性が高いと認められた場合には懲戒処分を検討する企業が多くあります。今回のように停職にするのかなどは就業規則にのっとり、検討することができます。ただ減給については、労働基準法で「1回の額が平均賃金の1日分の半額以内、総額が一賃金支払い機における賃金総額の10分の1以内」と限度が定められています。
懲戒解雇は慎重に
不正行為が悪質だったり不正受給の金額が大きい場合、「懲戒解雇」も選択肢に入ってきます。しかし、従業員にとって最も重い処分となるだけに、後日、解雇の有効性が争われる可能性があります。懲戒解雇に相当するか、根拠の有無を含め、慎重に検討することが重要です。
では懲戒解雇の裁判例にはどのような事例があるのでしょうか。
○実際に暮らしていない場所の住民票を会社に申告したケース
虚偽の住所を申告し、約3年間で100万円の通勤手当を不正受給していた事例です。こちらの訴訟では、企業側が勝訴しました。
刑法に該当する犯罪行為であり、即時解雇されてもやむを得ないと認められるほど重大、悪質な背信行為であると判示された事案があります。
○申告より安い通勤経路を利用し、差額分の通勤手当を不正受給していたケース
こちらのケースでは、企業側が不正受給を理由に従業員を解雇し、その有効性が争われました。判決では、
・ほぼ通勤経路が同じであることなどから、詐欺的場合ほど悪質ではないこと
・現実的損害も約34万円と大きすぎない上、差額分の返還の意思があること
・不正受給をした従業員が過去に懲戒を受けていないこと
などから解雇無効としています。
判例を見る限り、不正行為の期間や得た金額、悪質性が大きな鍵となりそうです。
コメント
交通費の不正受給は、一回一回の金額がそれほど大きくないこと、不正が比較的行いやすいことなどから、表に出ていない不正は相当件数あると言われています。不正の有無に目を行き届かせるには相応のコストがかかりますが、ときに業務上横領罪や詐欺罪にも問われない刑事犯罪を放置することは、社内におけるモラルおよびコンプライアンス意識の低下を招きかねません。
・不正受給発覚時の返還や罰則規定を含む、交通費支給ルールの整備
・明確かつ具体的な申請フローの設定
・交通費の精算の定期調査の実施(調査の負担の軽減のため、ランダムなサンプリングも有効)
などを通じて、交通費の不正受給を予防することが重要になります。この機会に、自社の交通費支給ルールや交通費精算の調査状況を改めて確認してみてはどうでしょうか。
関連コンテンツ
新着情報

- セミナー
 片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長) 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー) 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- ニュース
- 医学生への貸与金制度、県内勤務9年を条件とする高額違約金条項は不当 ー甲府地裁2026.1.22
- 山梨県が実施する大学医学部生向けの修学資金貸与制度をめぐり、違約金条項の差止めを求めた訴訟で、...

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- 解説動画
 大東 泰雄弁護士
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード