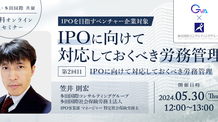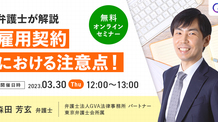ミドルシニア・法務パーソン、働き方の実態
2023/03/10 労務法務

1.はじめに
リーガル領域の専門性を武器に企業内で活躍する法務パーソン。そんな法務パーソンも、ミドルシニア期を迎えると、家族の介護の開始、役職定年による給与の減少、望まぬ部署異動・転勤、体力低下など様々な変化にさらされることになります。
その結果、従前と異なる働き方が必要となるケースも少なくありません。
ミドルシニア・法務パーソンは、どのように働いているのか。
今回、38名の法務経験者を調査して見えてきた、リアルな実態をレポートします。
調査概要
|
2.ミドルシニア期に望まれる働き方
まず、ヒアリングを行う中で印象的だったのは、大多数の方が、“法務の専門性を生かして働き続けたい”と強く希望しているということです(92%)。
「周囲に頼られる今の仕事にやりがいを感じている。」
|
また、次に多かったお声が、“若いときにこなしたような長時間労働はもう避けたい”というものでした(82%)。ミドルシニアに差し掛かり、体力の低下を実感している方、持病をお持ちの方、親の介護等の環境変化でプライベートとの両立が難しくなっている方などが少なくないようです。
まとめると、「①専門性を生かしつつ、②自分のペースを保って仕事をする」というのが、一般的なミドルシニア・法務パーソンが希望する働き方といえそうです。
3.ミドルシニア・法務パーソンはどう働いている?
この結果を踏まえ、同じ対象者に対し、今現在、①専門性(法務経験・法律知識・法的素養)を生かした仕事ができているか、②自分のペースを保った働き方ができているか(労働時間、年間休日)という観点で調査を行いました。
①仕事の専門性への満足度
[満足:26%、不満:74%]
仕事の専門性への満足度については、想像していたよりも低い数字となりました。法務実務を一応担当しているものの他業務の割合が高い方、法務実務をほぼ離れマネジメント業務メインとなっている方、転職・転籍・出向等を機に法務実務から完全に離れた方などがおられました。
やはり、ご年齢が上がるにつれ、「法務実務をメインとする仕事」の選択肢は狭まる傾向にあるようです。
■仕事の専門性への不満の声
|
②仕事のペースへの満足度
[満足:32%、不満:68%]
仕事のペースへの満足度についても、やや低めの数字となりました。管理職となって労働時間が増えている方、単純に部門内での業務量が増え残業・休日出勤が増えている方、転職先がハードな職場だった方、労働時間・年間休日自体は一般的な範疇にあるものの介護・育児との兼ね合いで負担を感じている方などがおられました。
■仕事のペースへの不満の声
|
なお、現職において、仕事の“専門性”と“ペース”の両面で満足している方は、わずか18%となりました。ミドルシニア・法務パーソンにとって、希望する働き方を実現するのが簡単ではないことがわかります。
4.理想の働き方へのハードル
では、ミドルシニア・法務パーソンが理想の働き方をなかなか実現できない理由はなんでしょうか。(1)企業側の求める役割と本人が希望する役割とのギャップ、そして、(2)希望する仕事への転職ハードルが高いことが主に挙げられます。
(1)企業側の求める役割と本人が希望する役割とのギャップ
これは、企業側がミドルシニアを迎えた法務経験者に対し、手を動かす実務よりも、マネジメントをはじめ、より多人数に影響を及ぼす役割を担って欲しいと期待を抱くことから生まれるギャップです。また、長年マネジメント業務をメインに担っている方に対しては、企業側から、実務へのブランクに対する懸念が持たれることもあります。
(2)希望する仕事への転職ハードルが高い
現職での業務の専門性やペースに不満がある場合、「転職」が選択肢としてあがって来ます。一方で、採用企業側は、ポジションフィット・カルチャーフィット・年収の高さなどの観点で、ミドルシニア~シニア期にある人材の採用に対し慎重になりがちです。そのため、“法務”という専門職とはいえ、40代後半以降、転職へのハードルが高まる傾向があることは否めません。
5.ミドルシニア期に理想の働き方を実現するために
今が「理想の働き方ではない」と感じているミドルシニア・法務パーソンが専門性とペースの両面で理想の働き方を実現するために、以下の選択肢があります。
(1)現職での立場や就業環境に変化を加える
まず考えられるのが、現職での立場(職位・職種etc.)や就業環境を変えることです。具体的には、マネジメント職から法務実務を担当するプレイヤーへの転向、他職種から法務職種へのカムバック、社内の法務業務効率化や人員増による業務負担の低減などが考えられます。しかし、現職で何かしらの変化を起こすには多数の当事者を巻き込みながら慣例等に抗う必要があり、総じて大きな困難を伴います。
(2)転職する
二つ目の選択肢が転職です。しかし、上述のように、年齢が上がるにつれて、希望に沿った転職先を見つけるのが難しくなる傾向があります。また、現職から環境を変えること自体のリスクもあります。そのため、総合的な視点による慎重な判断が必要になります。
(3)副業で法務の専門性が生きる仕事を行う
仕事の専門性を求めるミドルシニア・法務パーソンにとって、副業も有力な選択肢です。現職での仕事内容への物足りなさを副業先の仕事で埋めるという構図となります。その場合、基本的に、以下のいずれかの契約形態となります。
・副業先企業と雇用契約を結んで働く
・人材派遣会社やプロフェッショナルシェアリングサービス会社から副業先企業に派遣されて働く
もっとも、現職にプラスアルファして働くことになるため、労働時間は長くなりがちで、仕事のペースへの満足度が下がるおそれがあります。また、現職・副業先企業双方が社内規程等で副業を認めている必要があります。
(4)プロフェッショナルとして特定の企業に縛られずに働く
もう一つの選択肢が、現職を辞め、“法務のプロフェッショナル”として特定の企業に縛られずに働く形です。具体的には、人材派遣会社やプロフェッショナルシェアリングサービス会社から案件を受けて一定期間雇用され、法務課題を抱える企業にて業務遂行する働き方となります。一般的な派遣案件よりも時給単価の高い案件も多く、法務としての専門性を発揮しながら相応に高い給与をもらうことができます。
また、週3日のみ働く、週2日ずつ異なる企業で働く、数ヶ月の期間限定で働く等、ご自身の望むペースで柔軟に働ける点も魅力です。
さらに、転職とは異なり、スキルさえフィットすれば、上述したような企業目線の様々な採用ハードルに阻まれることもないため、就業までがスムーズなのも特徴です。そのため、法務としての専門スキルに自信のある方であれば、早期に仕事に就けるケースも少なくありません。
もっとも、こちらも転職同様、現職から環境を変えることのリスクが伴いますし、常に希望通りの案件と巡り合えるとも限らず雇用の安定性という面で正社員雇用に分があるのも確かです。役職定年・定年退職やライフステージの変化など個々人の置かれた状況に照らし合わせながら、冷静な検討が求められます。
【参考リンク】
専門性を生かしプロとして働く「プロシェアサービス」
6.終わりに
時流、経済の好況・不況、会社の経営状況・経営指針、自身および家族の体調など、働き方を左右する変数は非常に多く、先々の見通しを立てることは簡単ではありません。
それだけに、自身が大切にしたい「働き方の軸」を明確に持ち、その実現のためにどのような選択肢があるのかを知ることが重要になります。
ぜひ、本記事をご参考に、ミドルシニア期以降の働き方について考えてみてください。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- ニュース
- 株主総会書面決議9割賛成で可決へ、会社法改正の動き2026.1.19
- 株主総会における「みなし決議」の要件を、全会一致から議決権の90%賛成へと緩和する方向で、会社...
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階

- セミナー
 松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属) 阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30

- 解説動画
 浅田 一樹弁護士
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード