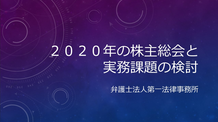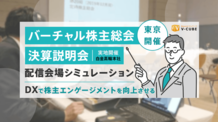ゼロから始める企業法務(第6回)/株主総会における想定問答集の作成と株主質問対応
2021/11/06 商事法務, 総会対応

皆様、こんにちは!堀切です。
これから企業法務を目指す皆様、念願かなって企業法務として新たな一歩を踏み出す皆様が、法務パーソンとして上々のスタートダッシュを切るための「ノウハウ」と「ツール」をお伝えできればと思っています。今回は上場企業の株主総会における株主からの質問対応と想定問答集の作成についてお話いたします。
株主からの質問は最後にして最大の難関
上場企業の株主総会では、報告事項と決議事項の説明の後、決議を取る前に、株主からの質問を受け付けます。この株主からの質問に対する説明が、株主総会業務の中で最後にして最大の難関になります。
理由は簡単で、株主が何を質問してくるかが分からないからです。
もっとも会社法上は、議長の説明義務は一般的な株主が報告の内容を理解でき、議案については賛否の判断ができる程度でよいとするのが原則(会314)であり、会議の目的たる事項と無関係な質問等については、議長の説明義務は免除されている(会314但書)のですが、近年は「開かれた株主総会」が求められており、各社、どの様な質問でも可能な限り説明する傾向です。これが株主総会担当者にとっては相当の負担になります。
株主によっては、およそ株主総会の目的事項とは全く関係ない質問をしてくるからです。
会社によっては、
「なぜ××製品のCMにタレント××を起用したのか」とか
「会社が所有しているスポーツチーム××の成績が低迷しているが、どう立て直すつもりか」
等の質問までされると聞きます。議長(社長)が株主からのどの様な質問にも回答できる様にするためには、想定問答集を充実させ、株主総会の場で迅速・的確に展開することがとても重要になります。
想定問答集の充実(インプット)
まずは質問事項をカテゴライズしていきます。
主なカテゴリは会社によって違うと思いますが、私の経験では「事業報告」「議案」「株式」「株価」「株主還元」「取締役」「監査役」「経営戦略」「資本政策」「知財戦略」「IR・PR」「会計・税務」「人事」「ビジネス」「技術開発」「情報セキュリティ」「リスク管理」「内部統制」「法令遵守」「CSR」辺りでしょうか。
カテゴライズした後は、当事業年度中と直近にリリースされたIR/PR文書を一通り読み込み、その中から株主総会で聞かれそうな質問とその回答をカテゴリ毎に記載していきます(ちなみに、回答は最後「以上、ご回答申しあげました。」で締めます。)。
また、その年々で株主から聞かれやすいトピックスについては、証券代行から情報を提供してもらいます。その他にも、例えば「当社の強みは?」「市場環境は?」「生産性は?」等の経営に関する一般的な質問もなされるので、いわゆる「SWOT分析」や「3C分析」等のフレームワーク分析やROE、ROA、労働分配率等の経営指標についても記載していきます。
質問、回答を記載していく中で、自分では回答案が思いつかない事項や、他に株主から質問がなされそうな事項については、各部門の責任者に対応をお願いします。「ビジネス」であれば営業部長、「会計・税務」であれば経理部長、「技術開発」であれば開発部長、経営指標であれば経営企画部長、といった具合です。また、IR担当者が、投資家説明会用にQ&Aを作成していれば、その内容も拝借します。
作成した想定問答集は、弁護士と証券代行に、抜け漏れが無いかや、回答が適切かをチェックしてもらいます。
また、株主総会リハーサルの際には、株主役の弁護士や証券代行から出された質問が想定問答集に無い場合は、その質問と回答も追記していきます。この様にして、想定問答集の内容を充実させていきます。
想定問答集の展開(アウトプット)
苦労して作成した想定問答集も、株主総会当日に株主からの質問に対して迅速・的確に回答を引き出し、議長に提供できなければ意味がありません。これには各社様々な工夫をされていると思いますが、私の経験では、議長席・役員席に設置したモニターに、質問に対する回答を表示する様にしていました。
具体的には、Excelに①「質問一覧」シートと②「回答画面」シートを別に作成し、①と②がリンクする様にします。①のシートにはカテゴリごとの質問が箇条書きされており、②のシートにはそれに対する回答が画面いっぱいに大きな文字で表示される様にします。
株主からの質問がなされたら、議長からは「只今のご質問は、~の趣旨ですね?」とオウム返しをしてもらいます。その間に、奥の事務局では一人が質問のメモを取り、もう一人がパソコンの①のシートを[Ctrl] Fで検索し、該当すると思われる回答を②のシートで表示します。それをPCとケーブルでつながれた、議長席・役員席に設置のモニターに映し出す方法です。
それまでは印刷した回答を、質問の度に必死にめくって探し、議長に紙を渡していたのが、遥かに効率的になりました。但し、株主総会当日にモニターが映らなくなるトラブルも想定されますので、株主総会前日の会場リハーサルの際に回答がちゃんとモニターに表示されるかを確認すると共に、印刷した回答も一冊、予備で用意して置きます。
株主からの質問が始まると、事務局は回答を検索し、モニターに表示させるという作業を繰り返します。株主からの質問対応が一通りなされた後、弁護士から質問を打ち切って良い旨の合図があります。今までの苦労が報われる瞬間です。後は粛々と決議事項を諮るのみとなります。
(おまけ)社内のキーパーソンとの連携について
想定問答集に限らず、株主総会業務においては社内のキーパーソンとの連携がとても重要になります。例えば、想定問答集に用意されてない質問があった場合でも回答できる様に、経理部長、営業部長、開発部長には事務局に同席してもらう様にします。
また、法務の職責上、株主総会当日は事務局を仕切らなければならないので、会場全体の仕切りについては総務部長にお願いすることになります。株主総会当日のスタッフについても、関係各所の上長にお願いして、通常業務が忙しい中、リソースを割いてもらいます。
意外と大事なのは、役員秘書との連携です。株主総会業務では、招集通知の読み合わせや株主総会リハーサル等、役員の時間が必要となるイベントがあります。上場企業であれば社外役員もいるので、社内のみでなく社外の秘書との連携も必要となります。役員秘書との連携が出来てないと、場合によっては役員がリハーサルに同席できず、不安を残したまま株主総会当日を迎えることになりますので、役員秘書には一番に株主総会スケジュールを伝え、調整をお願いすることになります。
この様に、関係各所の協力なしには、株主総会を成功させることはできません。そのためには、普段から上席、同僚の方々に感謝と敬意を持って接することが大切だと思います。
いかがでしたでしょうか。皆様がこれから取り組む業務に少しでもお役に立てるヒントがあれば幸いです。次回は、取締役会業務について、記事にできればと思います。
==========
本コラムは著者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラム内容を業務判断のために使用し発生する一切の損害等については責任を追いかねます。事業課題をご検討の際は、自己責任の下、業務内容に則して適宜弁護士のアドバイスを仰ぐなどしてご対応ください。
【筆者プロフィール】
私立市川中学校・高等学校、専修大学法学部法律学科卒業。
|
関連コンテンツ
新着情報
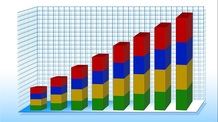
- ニュース
- 2025年の合同会社の倒産数374件で増加率5.6%2026.1.13
- 2025年1~11月の合同会社の倒産件数が374件で、増加率は5.6%であったことがわかりまし...
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- セミナー
 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- 解説動画
 大東 泰雄弁護士
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード