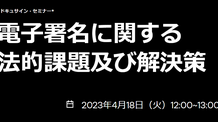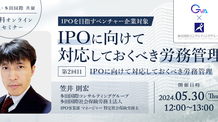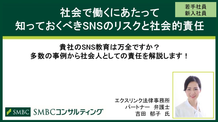施行1年で指導・勧告が445件、フリーランス法について
2025/11/05 契約法務, 労務法務, コンプライアンス

はじめに
フリーランス新法が施行された日から、11月1日で1年が経過しました。公正取引委員会の発表によると、昨年11月から今年9月までの11ヶ月間で、発注業者に出した勧告や指導が445件に上ることがわかりました。今回はフリーランス法の概要について見直していきます。
事案の概要
報道などによりますと、フリーランス法に違反する行為を認め改善措置や原状回復などを求めた“勧告”は、出版大手「小学館」や大手楽器店「島村楽器」などへの4件、指導は441件とされています。
勧告や指導の大部分は取引条件の明示義務違反と報酬の支払遅延によるもので、業界別ではアニメ制作、ゲームソフト開発、フィットネスクラブ、出版、放送などで違反行為が目立っていたとのことです。
特にアニメやゲーム業界では原作者の了承が得られるまで修正を求められるケースが多く、取引条件などをあらかじめ定めておかないと無償でやり直し作業を強いられる場合が多いとされています。
なお、同法に関して公取委に持ち込まれる相談は2024年が5018件、2025年は9月までに2050件とのことです。
フリーランス法の適用対象者
フリーランス法の適用対象となる当事者として委託を受ける側を「特定受託事業者」、委託する側を「特定業務委託事業者」とされています(2条1項、6項)。特定受託事業者は従業員を使用しない者を言うとされており、それが法人である場合の代表者やその者自体を「特定受託業務従事者」と言うとされます(同2項)。
一方、委託する側である特定業務委託従事者とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用する者を指します(同6項)。そして、ここで言う「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託することを言うとされています(同3項)。
つまり、従業員を使用する者が、従業員を使用しない者に物品製造や情報成果物の委託をする場合に本法が適用されるということです。
なお、「従業員」には短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まれません。
フリーランス取引の適正化
フリーランス法が適用される場合、フリーランスとの取引の適正化を図るための規制が置かれています。まず、業務委託をした場合、特定受託事業者であるフリーランスに対し給付の内容、報酬などを書面または電磁的方法で明示することが義務付けられます(3条)。これは従業員を使用していない事業者が委託する場合も同様とされます。
次に報酬は給付を受領した日から60日以内の日を支払日として設定し支払うことが義務付けられます(4条)。再委託の場合は発注元から支払を受ける期日から30日以内とされています。
そして、フリーランスに委託する場合に禁止事項として、(1)受領拒否、(2)報酬減額、(3)返品、(4)通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること、(5)正当な理由なく自己の指定する物の購入や役務の利用を強制すること、(6)金銭役務その他の経済上の利益を提供させること、(7)フリーランス側の責に帰すべき事由なく内容の変更ややり直しをさせることが規定されています。
これらはほぼ下請法の規制と同様なものとなっています。
フリーランスの就業環境の整備
フリーランス法ではフリーランスの就業環境改善のための規制がいくつか用意されています。まず、(1)公告等によって募集情報を提供する場合は虚偽の表示をしてはならず正確かつ最新の内容に保たなければならないとされます(12条)。
次に、(2)6ヶ月以上かかる業務委託に関してはフリーランスが育児介護等と両立できるよう申し出に応じて必要な配慮をすることが求められます(13条)。
(3)6ヶ月以上の業務委託については中途解除する場合等には原則として30日前までに予告しなければならないとされます(16条)。
そして、(4)特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じることも義務付けられています(14条)。
コメント
フリーランス新法は働き方の多様化によって個人事業主やフリーランス等の労働者が増加するに伴い、その立場の弱さから生じるトラブルを防止し、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とされています。
従前、下請法は親事業者と下請事業者の相互の資本金の額で適否が決まっており、資本金を1000万円未満にしている会社には適用がなくフリーランス等の十分な保護ができていないと指摘されていました。ちなみに、2026年1月から施行される改正下請法では資本金基準に加え、従業員数も基準となります。
フリーランス法では上記のように会社が個人(従業員を使用しない者)に委託を出す場合は漏れなく適用となります。違反に対しては現状直罰規定は無いものの公取委や中小企業庁、厚労省からの勧告や命令、検査拒否に対しては50万円以下の罰金と法人両罰規定が用意されています(24条、25条)。
外部委託を利用している場合は下請法だけでなくフリーランス法の適用を受けないか、また口約束だけで注文をしていないかを今一度確認しておくことが重要と言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- ニュース
- 大阪高裁が森永ヒ素ミルク事件での賠償請求を棄却、除斥期間とは2026.2.2
- NEW
- 森永ヒ素ミルク事件で脳性まひになった大阪市の女性(71)が製造元の森永乳業(東京)に5500万...
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階

- 解説動画
 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌)) 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- 解説動画
 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士) 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年) 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
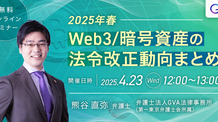
- セミナー
 熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00