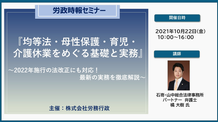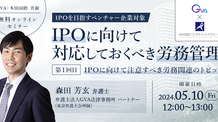東京地裁がコンビニ店主の団交権を否定、労組法の労働者性について
2022/06/07 労務法務, 労働法全般

はじめに
コンビニ大手「セブンイレブン・ジャパン」とフランチャイズ契約を結ぶ店主らに団体交渉権が認められるかが争われた訴訟で東京地裁は6日、団体交渉権を認めない判決を出していたことがわかりました。事業に不可欠な労働力に組み入れられていないとのことです。今回は労働組合法の労働者性について見直していきます。
事案の概要
報道などによりますと、「コンビニ加盟店ユニオン」(岡山市)は2009年にフランチャイズ契約を結ぶ店主らの待遇や店舗の経営改善を求め、セブンイレブンに団体交渉を申し入れたとされます。しかしセブン側は、店主は独立した事業者で会社と労使関係にはないとして応じなかったとのことです。ユニオンは岡山県労働委員会に救済申し立てを行い、同委員会は14年に労働者性を認め、団交拒否は不当労働行為に該当するとしました。一方でセブン側による不服申立てがなされた中央労働委員会は19年に、店主達の事業者性は顕著として労働者性を否定しており、ユニオンは中労委の命令を取り消すよう求め東京地裁に提訴しておりました。
不当労働行為とは
労働者には憲法で団結権や団体交渉権などの権利が保障されており、労働組合法7条各号では次のような行為を不当労働行為として禁止しております。まず(1)労働者が労働組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱、(2)正当な理由のない団体交渉の拒否、(3)労働組合の運営等に対する支配介入および経費援助、(4)労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱が禁止されます。労働者が労働組合に加入しないこと、または脱退するkとおを条件とする雇用や、団体交渉に応じても誠実な交渉をしないこと、労働組合の運営につき、経理上の援助を与えることなどもこれら不当労働行為に含まれることとなります。不当労働行為に対して労働者は労働組合が労働委員会に救済申立を行った場合、担当委員が選任され、調査、審問、公益委員会議を経て、使用者に対し是正を命じる救済命令が出されることとなります。命令に不服がある場合は中央労働委員会への再審査申立、または裁判所に取消を求める訴訟を提起できます。
労働組合法上の労働者
労働契約法2条によりますと、「労働組合」とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」とされます。そして「労働者」とは「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」を言うとされております(3条)。つまりここに言う「労働者」該当しなければ団結権や団体交渉権などが認められないということです。そしてその判断にあたっては、(1)事業組織に組み入れられているか、(2)契約内容の一方的・定型的決定がなされているか、(3)報酬の労務対価性が認められるかを基礎に、補充的要素として(4)業務の依頼に応ずべき関係か、(5)指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束があるかを総合的に勘案するとされております。逆に消極的判断要素として、顕著な事業者性が認められた場合は労働者性が否定される方向に働きます。
労働者性に関する裁判例
労組法上の労働者性が問題となる事例として、エンジニア等の技術者に業務委託を行う場合や、歌手などの芸術家に出演してもらう場合が挙げられます。前者に関する裁判例として、自社が製造した住宅設備機器のメンテナンスをカスタマーエンジニアに業務委託していた事例で最高裁は、会社側が全国の担当地域に配置を割り振って休日なども交代制で業務を担当させていたことから恒常的に会社組織に組み入れていたこと、契約内容も会社が一方的に決定し、報酬も労務の対価となっていたことなどから労働者と認めました(最判平成23年4月12日)。後者の例としては、国立劇場でのオペラ公演に出演していたオペラ歌手につき、公演の実施に不可欠な歌唱労働力として組織に組み入れられていたこと、公演件数、演目、上演回数などを劇場側が一方的に決定していたこと、劇場側の指揮監督下で歌唱していたことなどから労働者性を認めております(新国立劇場事件、最判平成23年4月12日)。
コメント
本件で岡山県労働委員会はセブンイレブンのFC加盟店の店主につき労働者性を肯定したものの、その後の中央労働委員会での再審査では一転労働者性を否定しました。加盟店の店主は会社の事業のための労働力として組織に組み入れられているとは言えず、得られる金員も労務の対価とは言えず、また顕著な事業者性が認められるとのことです。契約内容について会社側に一方的に決定されているものの、交渉力の格差があるというだけで労働者性の根拠とはならないとしております。東京地裁も同様に労働者性を否定しております。以上のように団体交渉などを行える労働者に該当するかについては様々な要素を総合的に考慮されます。本件でも県労働委員会と中央労働委員会で判断が分かれました。今後も新たな労働形態が生じるごとに同様の問題が生じることが予想されます。今一度これらの規定を確認して準備しておくことが重要と言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- セミナー
 森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45

- 解説動画
 浅田 一樹弁護士
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- ニュース
- 東京五輪をめぐる汚職事件でコンサル会社元代表の初公判、受託収賄とは2025.12.8
- 東京五輪・パラリンピックをめぐる汚職事件で大会組織委員会の元理事とともにコンサル会社「コモンズ...
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 解説動画
 大東 泰雄弁護士
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間