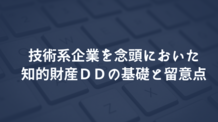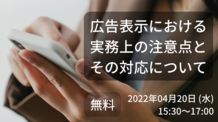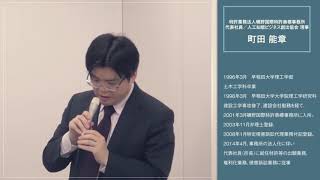オリンピックの撮影は「誰」のものか
2019/06/13 知財・ライセンス, 著作権法
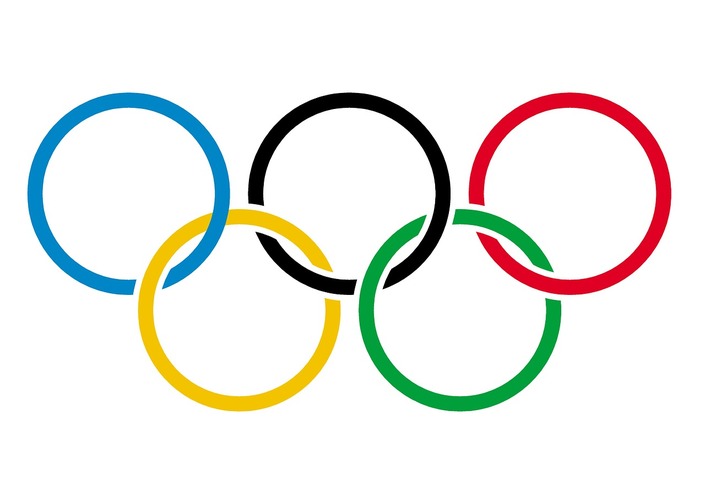
はじめに
いよいよ来年2020年に迫った東京オリンピック。第一陣のチケット抽選が先月5月28日に締め切られ、今月6月20日の抽選結果を心待ちにしておられる方も多いでしょう。
ところがそのチケット規約をめぐり、ネット上ではちょっとした話題になりました。今回は撮影行為と著作権の関係について見ていきます。
事案の概要
問題となったのは東京オリンピックのチケット購入規約である「東京2020チケット購入・利用規約」。その33条3項・4項はこのような規定となっています。
「第33条(撮影)
3.チケット保有者は、会場内において、写真、動画を撮影し、音声を録音することができます。・・・チケット保有者は、これらのコンテンツについて保有する一切の権利(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)をIOCに移転するとともに、その著作者人格権を行使しないことに同意します。
4. IOCは、前項を前提としたうえで、チケット保有者が会場内で撮影・録音したコンテンツを個人的、私的、非営利的かつ非宣伝目的のために利用すること・・・を、チケット保有者に対して許諾します。ただし、チケット保有者は、会場内で撮影または録音された動画および音声については、IOCの事前の許可なく、・・・配布(その他第三者への提供行為を含みます。)することはできません。」
この規約を見ると3項で写真・動画撮影・録音できるとしておきながらも、著作権は全てIOCに移転し、著作者人格権の不行使についてもチケット保有者は同意していることとなります。また4項はそれを前提に私的利用は一応認められるもののSNS等の電子メディアへの投稿が禁止されているように見えます。
この規定が一部報道において「高額の放映権料を支払っているテレビ局の利益を守るため」と報じられたため、話題となりました。
著作権・著作者人格権
著作権は著作物に対する権利であり、届出や審査といった手続きを踏まずに著作物を生み出すのと同時に権利が発生します。著作物は創作の結果として生まれたものなのでその利用には創作者の不利益になるべきでないという狙いがそこにはある訳です。
著作権は「権利の束」といわれ、例えばコピーする複製権や劇場公開する上映権などが含まれるため権利者は多様な利用態様について権利を持つことになります。この著作権は譲渡(著作権法61条)することができ、それを定めたのが規約の3項ということになります。
一方の著作者人格権とは同じく著作物に対する権利なのですが「人格権」という名の通り著作者の人格を尊重した権利である点に特徴があります。具体的には意に反して公表されない公表権、出典を省略されない氏名表示権、意に反する改変を受けない同一性保持権という三つの権利から成り立っています。
この人格を尊重するという権利の性質上、著作者人格権は譲渡になじまない一身専属的な権利と考えられ、著作権のように譲渡することができません。従って規約3項のように不行使について合意をするという方法を取ることになる訳です。
規約の制限は何に及ぶか
チケット保有者は自由に撮影録音することができるため、その写真・動画の著作者です。しかし規約3項により著作権は譲渡されるため著作「権」者はIOCになります。
つまり4項でIOCが利用について許諾する形をとっているのは、チケット保有者が著作者ではあっても著作権を行使できないため改めて著作権者の許可が必要となるからと言えます。
そして4項の規定により動画・音声については配信等の利用に制限がされていますが(明示的に許諾のある私的利用を除く)これは上記のように本来的に権利がないため、注意的な規定とみることができるでしょう。
他方で写真については注意的な規定からわざわざ外されているので事実上配信等の利用に許諾が与えれているものとみることができ、自由に利用してよいとみられます。
コメント
規約自体は法的には問題が見受けられないとはいえ、一般的な感覚との乖離が話題の原因となったようです。
スポーツの祭典として皆で盛り上げていくべきオリンピックの感動は独占されるべきでないという意見はもっともです。特に最近のYoutube等の新たな映像メディアの流行から見れば映像配信ができないという規約は時代の流れに逆行しているようにも思えます。
他方でスポーツ風景の撮影はオリンピックに限らず現在のスポーツ大会等においても撮影の許可を要することが多いのが現状です。その理由として無関係な第三者が営利目的で配信を行い競技者に還元されない、また映像が不当な目的で利用されるといった点が挙げられ、動画配信の規制についても一定の合理性は存在しています。
禁止を含む規約はともすると批判に晒されがちではありますが十分にその理由付けの説明がされれば理解は得られるはずです。このような場合に備え、例えば「よくある質問」のコーナーを設けて禁止に至った経緯を説明するといった工夫が重要となってくるのではないでしょうか。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- ニュース
- クスリのアオキが買収防衛策を導入予定、大株主オアシスは反対2026.2.12
- NEW
- 「クスリのアオキ」が臨時株主総会で買収防衛策の導入を予定していることがわかりました。これに対し...
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- 解説動画
 大東 泰雄弁護士
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- セミナー
 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30