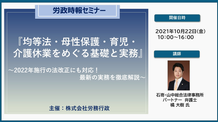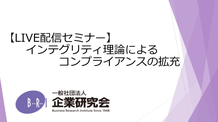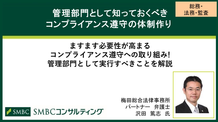神戸製鋼がデータ改ざん、不正競争防止法による規制について
2017/10/13 コンプライアンス, 不正競争防止法
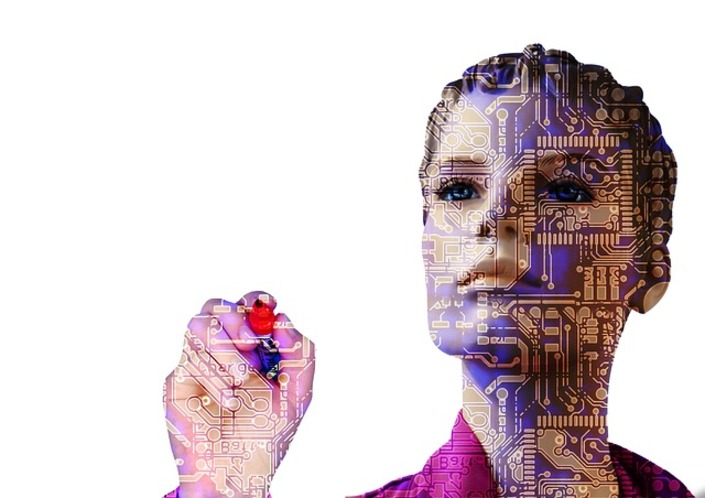
はじめに
神戸製鋼は、13日、アルミ・銅事業でのデータ改ざんに加え、鉄鋼事業でも新たにデータの不正が見つかった旨発表しました。先日まで不正は存在しないと強調していた主力事業であるだけに、業界からの信頼失墜は避けられないものと思われます。今回は不正競争防止法の禁止する虚偽表示について見ていきます。
事案の概要
報道などによりますと、神戸製鋼所は8日、同社が出荷していたアルミ・銅製品において顧客が求めていた品質基準を満たしていなかった旨発表しました。品質のデータを改ざんしていたとのことです。改ざんがあったのは昨年9月から今年8月にかけて大安工場(三重県)、真岡製造所(栃木県)など4事業所で製造されていたアルミ製品約1万9300トン、銅製品2200トン、アルミ鋳造品19400個とされております。出荷先は自動車関連メーカーや航空機関連メーカーなど約200社に及ぶとされております。そして今回新たに見つかったのは神戸製鋼所の主力製品である線材で、自動車のボルトやエンジン周辺、弁ばねなどに使用されております。このうち弁ばね用線材は世界シェア50%に及び米GM社などにも出荷されていたとされております。
不正競争防止法による規制
不正競争防止法2条1項14号では「不正競争」の一つとして「商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示」をすることをあげております。いわゆる品質等誤認惹起行為と呼ばれるものです。違反した場合には、それによって利益の侵害を受ける者から差止請求や賠償請求を受け(3条、4条)、また刑事罰として5年以下の懲役、500万円以下の罰金またはこれらの併科となり、法人に対しては3億円以下の罰金となります(21条2項、22条1項)。
成立要件
(1)表示の対象
同条では誤認惹起の対象として「商品」「役務(サービス)」「その広告」「取引に用いる書類」としています。市場に流通させる商品やサービス、それに関する広告などです。そして取引に用いる書類とは、注文書、見積書、送り状、計算書、領収書などが該当します。それ以外のものも「通信」として規制の対象に含まれるとされます。
(2)表示の内容
これらの対象について、原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量等に関して「誤認させるような表示」が禁止されます。誤認させるような表示に該当するかの判断は、①個別・具体的な事案に応じて、②当該表示の内容や取引業界の実情等、諸般の事情を考慮し、③取引者・需要者に誤認が生じるおそれがあるかどうかで判断するとされております。裁判例では直接原産地を表示していなくてもイタリアの国旗と「イタリアンタイプ」といった表示がイタリア産と誤認させるとし(大阪地判平成8年9月26日)、「みりん風」といった表示が本みりんと誤認させるとしました(京都地判平成2年4月25日)。また実際には特級清酒の品質であっても、公的機関から清酒二級とされた商品に「特級清酒」と表示する行為も誤認惹起に該当するとされました(最判昭和53年3月22日)。また一見誤認惹起表示に該当するように見えても一般的に普通名称や取引慣行となっている場合は適用除外となります(19条1項)。たとえば「薩摩芋」や「佃煮」などは薩摩や佃島産でなくとも表示が可能です。
景表法との異同
同様の規制は景表法にも存在します(5条1号)。景表法の規制の目的はそのような表示により一般消費者の判断を誤らせることを防止ことにありますが、不正競争防止法はそれよりも広く他の事業者、取引業者、ひいては一般消費者もその保護の対象としています。景表法違反の場合も同様に罰則がありますが(36条等)、それに加えて行政からの措置命令(7条)、や課徴金(8条)が課せられることがあります。一方不正競争防止法にはこのような行政処分の規定は存在しておりません。被害を受けた相手方は専ら民事訴訟か刑事告発によることになります。
コメント
本件で神戸製鋼は製品の品質検査に関する証明書のデータを改ざんし、顧客が求める基準に満たないにもかかわらず満たしているように表示していたとされます。これは「取引に用いる書類」に「品質」について「誤認させる表示」を行ったことになると考えられます。以前にも取り上げました東洋ゴムの免震ゴムのデータ改ざん事件でも同様に不正競争防止法違反で起訴されております。神戸製鋼所はこれにより、顧客からの賠償請求や警察当局からの捜査を受ける可能性だけでなく、株主からの責任追及が及ぶ可能性も考えられます。以上のように、製品の品質や産地、性能のデータを実際よりも良く表示した場合には不正競争防止法違反となるだけでなく多方面からの責任追及が及ぶことになります。製品の製造・販売を行っている場合には、これらについて改ざんは行われていないか、不当表示となっていないかを今一度確認することが重要と言えるでしょう。
新着情報

- セミナー
 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 採用困難職種“企業法務” — 管理部門採用で求職者に“選ばれる”採用の工夫
- 2026/03/10
- 13:00~14:00

- ニュース
- ヘリコプター・オーナー商法疑いで3人を逮捕、預託法の規制について2026.2.16
- 「ヘリコプターなどを共同購入すれば賃料収入を毎月得られる」などとうたい販売預託商法をしていたと...

- 解説動画
 岡 伸夫弁護士
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
 浅田 一樹弁護士
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...