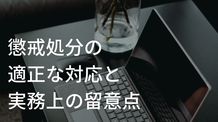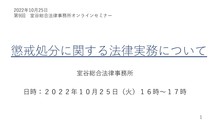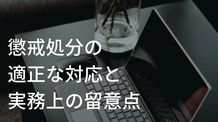企業がとるべきセクハラ対策を考える!(前編)
2014/12/17 労務法務, 労働法全般, その他

スーパー大手「西友」の男性社員が女性パートにセクハラ
16日、スーパー大手の「西友」でパートとして務めていた20代の女性が、同僚の男性社員から繰り返し胸や下半身を触られるなどのセクハラを受けたとして、西友とこの男性社員に慰謝料など計1100万円を求めた訴訟の判決が東京地裁でありました。担当した沢井真一裁判官はセクハラを認定、さらに西友の職場環境の配慮義務違反も認めて、同社とこの男性社員に対し計330万円の支払いを認めました。この他にも、今月9日には、兵庫県教育委員会が、50代の教育振興室長の男性を20代女性職員に対するセクハラを理由に懲戒処分に処すなど、近頃、企業や地方公共団体におけるセクハラに関する報道が後をたちません。
当サイト、「企業法務ナビ」では、企業の法務担当者向けに、その日にあった法務関連のニュースや法務関連コラムなどを「法務ニュース」として毎日アップしていますが、過去1ヶ月の間で最もアクセスが多かった記事は「企業内ハラスメントに注意!(2014年11月26日)」でした。やはり、セクハラを始めハラスメントに関する報道は、企業イメージを大きく傷つけるものでありますし、何より、社員全員が心地よく業務にあたることのできる健全な職場環境の構築のために、企業の法務・人事をはじめ管理部門の皆さんは、職場における「ハラスメント対策」に対し、日ごろより気を配っているようです。
一言に「ハラスメント対策」といえど、種種様々。そこで、今回は、企業におけるハラスメントとして代表的なセクハラについて、厚生労働省の「セクハラ指針」を参考に、企業としてはセクハラ対策として具体的に何をすべきかを、“事前対策”“事後対策”として、全2回に分けて考えたいと思います。
セクハラ事前防止策の重要性
まずはじめに、男女雇用機会均等法は第11条1項にて、「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、または当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」として、事業主に、セクシュアルハラスメントに関して、事前及び事後の対策を講ずることを義務付けています。
セクハラはいったん発生すると、被害者に加え行為者も退職に至る場合があるなど双方にとって取り返しのつかない損失となることが少なくありません。また、今後の職場での立場などを考えて、社内においてセクハラ被害を訴えることを長年躊躇していた被害者がそれに耐えかねて声を挙げる場合、被害者は腹をくくって会社側と裁判を含めて徹底的に争う場合が多く、これこそ、被害者にとっても会社にとってもそのダメージは計り知れません。したがって、企業におけるセクハラ対策では、それを未然に防ぐ、事前の防止策が特に重要といえるでしょう。
具体的なセクハラ事前防止策を考える
職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、厚生労働省はその指針において10項目を定めています。そのうち、事前の対応策として挙げられているのが以下の4つです。
①「職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。」
周知の方法としては、社内報、パンフレット、社内ホームページ等を活用する方法があります。また、就業規則、もしくは、就業規則の本則ではなくとも、就業規則の一部をなすと考えられる従業員心得や行動マニュアルなどにおいて、会社のセクハラに対する方針を明らかにしておくことも必要です。
また、周知・啓発の方法として、研修やセミナーを実施することも有益ですが、この場合、予めセクハラに関する調査やアンケートを行い、職場の実態を有る程度踏まえた上で実施したり、職階別に分けて研修を実施するなどするとより効果的でしょう。
②「行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発」
セクハラを行った者が具体的にどのような処分を受けるのかを予め文書でルール化し、それを労働者に認識させることは、セクハラが行われた後の懲戒内容が明確化されるというだけでなく、懲戒内容を事前に掲げることで、セクハラ行為の抑止・事前防止にもなります。
なお、懲戒規定を就業規則の本則以外で定める場合は、就業規則の本則にその旨の委任規定を定めることが必須になりますので、注意が必要です。
③「相談窓口の設置」
相談窓口の設置については、もちろん「セクハラ相談窓口」といったそのものズバリの機関を置くもよし、そこまで会社の規模が大きくない場合は、相談に対応する担当者を予め定めたり、場合によっては外部の機関に相談への対応を委託することも一つの手でしょう。
そして、企業としては、窓口を“形式的”に設けるだけでは足りず、その窓口の存在を社員に周知た上で、相談は面談だけでなく、電話、メールなど複数の方法で受けられるようにするなどして、社員が“実質的”に相談しやすい、利用しやすい体制を整備することが何よりも重要です。
④「相談に対する適切な対応」
相談窓口においては、職場におけるセクシュアルハラスメントが既に生じている場合でなくとも、発生のおそれのある場合や、セクハラに該当するか否か微妙な場合にも、広く相談に対応し適切な措置を講ずることで、セクハラを事前に防止することができます。したがって、企業としては、社員自身がはっきり「セクハラ」と確信を持てずとも、「とりあえず相談してみよう」と思えるような、相談しやすい環境づくりが大切でしょう。
そして、これは“事前”“事後”ともに重要なことですが、窓口として相談を受けた者は「二次セクシュアルハラスメント(相談者が相談窓口の担当者の言動などによってさらに被害をうけること)」を防止するために、十分留意した上で相談に対応しなければなりません。そのために、対応の仕方やカウンセリングなどについて、相談対応者に対する研修をすることも必要と思われます。
以上、今回は“事前”のセクハラ対応策として4点を御紹介しました。次回は“事後”のセクハラ対応策を検討します。
関連サイト
- 企業内ハラスメントに注意! | 企業法務ナビ
- セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ 厚生労働省
- 西友の女性パートに、指導役男性社員がセクハラ YOMIURI ONLINE(リンク切れ)
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- 解説動画
 加藤 賢弁護士
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- 解説動画
 大東 泰雄弁護士
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- セミナー
 森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45

- ニュース
- 育休明け男性社員の内勤配転は「著しい不利益」を負わせ無効 ー東京地裁2026.2.19
- NEW
- 「育児休業から復帰後、外勤の営業職から内勤に配転されたのは不当だ」として、パナソニックリビング...