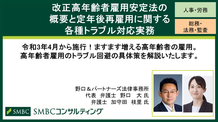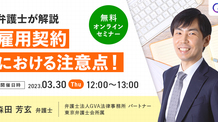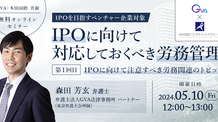セクハラ、パワハラ、遂に「カラハラ!?」
2014/06/11 労務法務, 労働法全般, その他

カラハラとは
職場には様々なハラスメントがある。パワハラやセクハラ等だ。しかし、最近「カラハラ」と呼ばれるハラスメントがあることをご存じだろうか?
「カラハラ」とは、職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、カラオケで歌うことが苦手・嫌いな人に、無理矢理歌わせることである。
カラハラの具体例として以下のものがある。
某飲料メーカー営業部社員として入った女性Aさんは、自分が音痴のため、昔からカラオケが嫌いだった。入社後付き合いで仕方なく飲み会の二次会等でカラオケには参加していたものの、歌うことを拒否してきた。
しかしある日、飲み会の二次会でカラオケに行き、上司が歌い終わった後、「Aちゃん、君も歌いなさい。」と言われ、最初は断っていたものの、上司の機嫌が次第に悪くなることを感じ、仕方なくマイクを取り、なんとか歌い終えた。すると、周りは微妙な雰囲気、上司もニヤけていた。その後、上司から一言。
「Aちゃんは、B社の接待に連れていけないな~」
翌日、上司から予定されていたB社の営業から外れるよう告げられ、代わりに、営業成績は私よりも低いが、カラオケでたくさん歌っていたCさんがB社の営業に抜擢された。Aさんは、これに対し、人事部に相談しても、上司が正しいとされた。
このような「カラハラ」に悩まされる人達は以前から存在しており、実際に取引先との接待中のカラオケで歌った挙句、営業から外され、他の部署に配置転換されたこともあるという。
コメント
「カラハラ」はパワーハラスメントにあたるのではないか?
パワーハラスメントとは、職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えることをいう(厚生労働省参照)。
そうだとすると、確かに、カラオケを用いた接待も仕事と言われることがあることからカラオケが「業務」に該当するという考え方もある。しかし、職業として継続して行われる仕事を「業務」というのであり、カラオケは契約締結という「本来の業務」を達成する一手段に過ぎず、カラオケ自体に継続性があるものではないだろう。とすれば、カラオケそれ自体が「業務」に含まれることは極めて稀であるといえる。
それにもかかわらず、わざわざカラオケが嫌いな社員を連れて行き、歌うことを無理強いすることは甚だ疑問である。
また、カラオケが嫌いで、歌いたくないのに歌わされる権利は、個人の人格権(憲法13条後段、民法710条)として保護されるべきであると考えられる。
そうであるとすると、接待、打ち上げの度にカラオケを強要することは「継続的に人格と尊厳を侵害する言動」に当たり得る。そして、上記の通り、カラオケをしなければ、配置転換のおそれがつきまとうとすると、カラオケが苦手な従業員は雇用に不安を継続的に抱くことになる。
よって、「カラハラ」はパワーハラスメントに認定されることは十分考えられる。
「カラハラ」を不法行為(民法709条)と認定した判例は未だ存在しないが、今後裁判で問題になる可能性が高いだろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- セミナー
 殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー) 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59

- 解説動画
 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌)) 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- 解説動画
 大東 泰雄弁護士
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- ニュース
- ニデックのTOBを巡り三田証券元取締役を逮捕、インサイダー取引について2026.2.4
- NEW
- モーター大手「ニデック」(旧日本電産)の株式公開買付をめぐり、インサイダー取引に関わったとして...