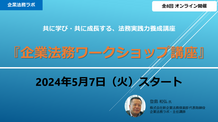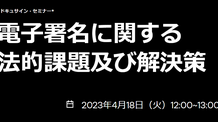Q&Aで学ぶ英文契約の基礎(1)- 国際契約が英文で長文の理由等
2021/01/20 契約法務, 海外法務

今回から英文契約書の基礎というタイトルで執筆させていただく浅井です(プロフィールは末尾をご覧ください)。英文契約に関する書籍は数多くありますが、このシリーズではQ&Aを通じ基礎を解説していくこととします。
Q1:国際契約は何故英文なのですか?
A1:この原因は、かつては英国が、現在は米国が、国際的な取引の主なプレーヤーであることにあります。また、英語が世界で最も広く使われている言語であり、英語が母国語でない当事者同士でも共通の言語として使うことができるからです。
Q2:英文契約は何故長文なのですか?
A2:最近では日本の契約書も英文契約の影響を受け、昔に比べれば大分長文になってきましたが、それでも英文契約の長大さには閉口することも多いと思います。その主な原因は次のようにいうことができると思います。
(1). 口頭証拠排除の原則
口頭証拠排除の原則とは、Parol Evidence Rule(パロール・エヴィデンス・ルール)という英米の契約上の原則です。簡単に言えば、契約書を作成した場合はこれと異なる口頭での合意を裁判所は考慮しないという原則です。英文契約の一般条項の一つとして規定されているいわゆる「完全合意条項(Entire Agreement Clause)」の背景となっている原則です。従って、いきおい、全ての合意を盛り込もうとし契約書が長文化します。
なお、我が国にはこのような原則はなく、事実認定を裁判官の自由な判断に委ねる「自由心証主義」により契約書に記載されていない合意や契約書の記載と異なる合意も認められることがあることはご存知の通りです。
(2). 国際契約としての特性
同じ国の当事者同士で締結される契約と異なり、国際的な取引に用いられる英文契約は、文化的背景や思考方法、法律制度などが異なる国の当事者間で締結されます。従って、例えば、我が国の当事者同士の契約のように、全てを契約書に規定しなくても話し合いや民法の規定により解決できるだろうという期待ができません。一方、独占禁止法などの強行法規に違反しない限り私的自治・契約自由の原則に従って当事者が合意した通りの法的効力が認められるというのが、世界的にも基本となっています。従って、可能な限り様々なケースを想定しそれに対応した規定を置こうとするので、このことも契約の長文化につながっています。
(3). その他
上記の他、特に米国では、国内においても多様な民族が存在すること、州ごとに法律が異なること、州ごとに判例法が形成されていること、弁護士が多く契約書作成も重要な仕事となっていることなどが契約長文化の原因になっていると思います。また、我が国を含め外国からの多くの留学生が米国のロースクールで学びその後も米国の法律事務所で研修するなどして、米国の長文の契約書スタイルを身に着け帰国し国際契約の交渉場面で活躍するので長文の契約が当然ということになります。
Q3:英文契約書に「信義誠実条項」はないのでしょうか?
A3:基本的にはないと考えていいでしょう。
ここでいう信義誠実条項とは、例えば、「本契約に定めのない事項または本契約に関し疑義を生じた事項については、両当事者が誠意をもって協議の上これを解決する」というような条項のことですが、上記のような英米の契約の考え方からすれば、そもそも、「定めがない」ことや「疑義」が生じないよう様々なケースを想定して明確に規定すべきであるし、協議により解決できるのならそれを契約書に規定してもしなくても同じなので規定する意義が理解できないということになるでしょう。
Q4:英文契約書のタイトルとして、「~ Agreement」と「~ Contract」どちらが適切なのですか?
A4:どちらでも問題ありません。
法概念としての違いはありますが、契約書のタイトルとしてはどちらを選んでも法的効果に差は生じません。
これは、国内の契約で、表題が「~覚書」であるか「~契約書」であるかにより法的効果に差が生じないことと同様と考えていいでしょう。
ただ、筆者の印象に過ぎませんが、特に米国の企業との契約では、「~ Agreement」の方が「~ Contract」よりも一般的という感じがします。
「Q&Aで学ぶ英文契約の基礎」第1回は以上です。第2回は「リーガルビジネススクールONLINE(外部サイト)」にてお読みいただけます。
Q&Aで学ぶ英文契約の基礎(2)- 英文契約書の形式・スタイル等①
Q&Aで学ぶ英文契約の基礎(3)- 英文契約書の形式・スタイル等②
==========
本コラムは著者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラム内容を業務判断のために使用し発生する一切の損害等については責任を追いかねます。事業課題をご検討の際は、自己責任の下、業務内容に則して適宜弁護士のアドバイスを仰ぐなどしてご対応ください。
(*) この「Q&Aで学ぶ英文契約の基礎」シリーズでは、読者の皆さんの疑問・質問等も反映しながら解説して行こうと考えています。もし、そのような疑問・質問がありましたら、以下のメールアドレスまでお寄せ下さい。全て反映することを保証することはできませんが、筆者の知識と能力の範囲内で可能な限り反映しようと思います。
review「AT」theunilaw.com(「AT」の部分をアットマークに置き換えてください。)
|
【筆者プロフィール】
1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで複数の日本企業および外資系企業で法務・知的財産部門の責任者またはスタッフとして企業法務に従事。1998年弁理士試験合格。2003年Temple University Law School (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事、国際取引法学会会員、IAPP (International Association of Privacy Professionals) 会員。 【発表論文・書籍一覧】
|
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
 岡 伸夫弁護士
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- セミナー
 森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...

- 解説動画
 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士) 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年) 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- ニュース
- 医学生への貸与金制度、県内勤務9年を条件とする高額違約金条項は不当 ー甲府地裁2026.1.22
- 山梨県が実施する大学医学部生向けの修学資金貸与制度をめぐり、違約金条項の差止めを求めた訴訟で、...
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード