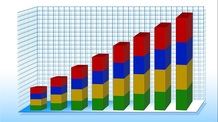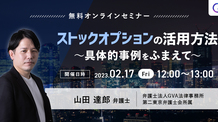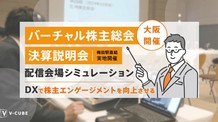積水ハウス地面師詐欺事件に係る株主代表訴訟、二審も株主側が敗訴
2022/12/13 商事法務, コンプライアンス, 会社法

はじめに
積水ハウスが東京都内の土地取引で約55億円をだまし取られた「地面師詐欺事件」を巡って、株主が当時の社長らに対して、損害額と同額を会社側に支払うよう求めた株主代表訴訟の控訴審判決が8日、大阪高裁で下されました。判決は株主側の控訴を棄却し、1審で株主の請求を退けた大阪地裁判決支持した形となりました。
事件の経緯
報道などによりますと、当時の営業担当者は2017年3月、会合で知り合った仲介者から、東京都品川区JR五反田駅近くの旅館跡地の売却情報を入手。分譲マンション用地として購入する目的で、その2週間後に社内で土地購入の方針を決定していました。当時の社長も現地視察を行い、 稟議書は担当役員のチェックを後回しにして決裁されたということです。
担当者は土地の所有者と名乗る女にパスポートを提示させていましたが、実は偽造したものでした。担当者らはそれを見抜けなかった上、権利証も原本ではなく、コピーで確認を済ませていたということです。その後、売買契約が結ばれ、手付金14億円を支払いました。
しかし翌月、実際の所有者から「売買契約はしていない」などといった内容証明郵便が複数回届くも、会社側は「怪文書」と判断。社内外からの不審点の指摘があったにも関わらず、十分に検討されなかったということです。
結局、当時の社長の了承のもと、残金は当初の7月末から前倒しして、6月1日に支払っています。詐欺だと発覚したのはその後、法務局から登記申請が却下された段階でした。
「地面師」グループは約55億円をだまし取ったとして、十数人が詐欺容疑などで逮捕され、10人が起訴されました。事件を主導した男は懲役11年が確定しています。積水ハウスは被害額の一部である10億円の損害賠償を男らに求める訴訟を起こし、一部賠償が命じられました。
稟議書のあり方について
この地面師事件を通じて、リスク管理に対して多くの指摘が寄せられました。
まずは稟議書のあり方について。
稟議書とは担当者に決裁権などがない場合に、関係する部署などの上司や役員などに承認を求め、決裁を得るために使用されるものです。
最近では電子化の動きも多くみられますが、紙1枚で必要な責任者からの判断を仰ぐことができ、会議を召集するなどの時間や物理的な手間を省くことが可能です。
今回の事件でも、取引前に稟議書が起案されていますが、十分に時間をかけず吟味されなかったとされています。
積水ハウスの報告書では4月14日に不動産部長らによる会議で購入決定がされた後、「4月19日に不動産部が稟議書を受け付けて、19日中に経営企画部長、執行役員経理財務部長、常務執行役員法務部長までが関係先として稟議書の内容を確認した」「4月20日に(中略)社長のところに本件稟議書を持ち込んで、社長の決裁を得た」と記載があります。
さらに売買相手の名義が4月19日に、詐欺グループ側の要望で別の人間に変更されましたが、これは鉛筆書きで修正されています。
この稟議書が通った後、売買契約書締結を実施し、手付金などが支払われたほか、所有権移転の仮登記も行われました。
稟議書は業務の円滑化・透明化を図ることができる一方、実態の確認が不十分なままに手続きが進行しがちです。稟議規定を改めて確認することも重要です。
リスク管理について
もう一つは、リスク管理について。積水ハウスには複数のリスク情報が寄せられていましたが適切な対応を取っていなかったということです。
仮登記手続きの完了後、合計4通の内容証明郵便が届き、所有者から、真の所有者は自分であり、この取引は偽物によるものであるとの警告を受けていました。また、数人のブロー力一的人物が会社を訪れるなどし、当時取引中の詐欺グループたちについて忠告を受けていました。
マンション事業本部と法務部は、内容証明については「本人は面会謝絶としながら、代理人名の書状ではないこと」といった幾つかの矛盾点があるとして、怪文書の類として評価。
また、ブローカー的人物に関しては、マシショシ事業本部内で、取引を妨害したい者の嫌がらせと判断されていました。
このほかにも今回の事件では権利書や本人確認書類の確認のあまさや、長年売却を拒んでいたと知られている所有者が、急に売却することになった動機調査の不十分さが指摘されています。
コメント
上述のように、積水ハウスの調査報告書では、法務部に対し、①重要なリスク情報(所有者からの内容証明郵便の受け取り)の取扱いの不備、②稟議手続きへの対応の不備(初期情報で気づくべき懸念事項がほぼ記載されていない)などが指摘されています。
法務部門は、ときに、現場の実態がよく見えない中で仕事に取り組まねばならず、なおかつ、問題発生後に遡って不備を指摘されてしまう、苦しい役どころです。その一方で、現場から少し距離のある法務だからこそ、客観的な視点・証拠から契約の妥当性、取引の正当性を判断できる側面もあります。
ビジネスのスピード感が求められる中で簡単な話ではありませんが、重要な取引時には、ある種「性悪説」に則って、慎重に取引を精査する必要がありそうです。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 解説動画
 大東 泰雄弁護士
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- ニュース
- あおぞら銀行、内部通報した行員の長期隔離配置は違法 ー東京高裁2026.1.26
- NEW
- 「あおぞら銀行」の行員が内部通報後に受けた懲戒処分を巡り損害賠償などを求めた訴訟で22日、東京...
- 弁護士

- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- セミナー
 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号