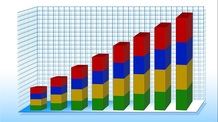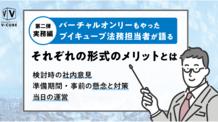トヨタが受取り期間を延長へ、株主優待のメリット・デメリット
2025/08/27 商事法務, 総会対応, 会社法, 自動車

はじめに
トヨタ自動車が株主優待で受け取ることができる電子マネーの付与期間を延長していたことがわかりました。手続きが終わっていない株主が多かったとのことです。
今回は株主優待制度のメリット・デメリットについて見直していきます。
事案の概要
報道などによりますと、トヨタ自動車は今年3月から同社では初となる株主優待制度を導入しました。初回の基準日は3月31日で、その内容は保有株式数と継続保有期間に応じて電子マネーを受け取れるというものとされます。
保有株式数は最低100株以上となっており、1年未満で500円分、1年~3年未満で1000円分、3年以上で3000円分、1000株以上を5年以上保有で30000円分となっており、専用サイトで発行された特典コードをスマホ用決済アプリ「トヨタウォレット」に入力することで受け取ることができます。
当初の受取期限は7月15日だったものの、株主から手続きが難しいとの声があり、受取未了が多く期限を2026年2月1日まで延長したとのことです。
株主優待制度とは
株主優待制度とは、株式会社が自社の株式を保有する株主に対して商品やサービスなどの優待品を贈呈する制度を言います。
配当金以外のリターンを得られることから個人投資家に人気があり、株主還元や個人投資家を誘引する目的で導入する会社が多いと言えます。
一般的には年に1、2回提供されることが多く、その内容も会社によって様々です。自社の製品やサービス以外にも金券やカタログギフト、QUOカードなどが提供されます。
また、株式の保有期間に応じて内容を増やしたり、豪華にするなど安定した長期保有を促す効果も期待できます。
このように株主優待制度は個人投資家や会社にとっても様々なメリットがある反面、デメリットや法的な問題点も内包しています。以下具体的に見ていきます。
株主優待制度のメリット・デメリット
株主優待制度のメリットとしては、上でも触れたように個人投資家の投資を誘引することができることや、安定した長期保有株主を増やすことができる点が挙げられます。
これらの株主は株主優待を目的としていることから、ある程度会社の業績が下がったり、多少株価が下落しても保有し続ける傾向があると言われています。
また、優待の内容を自社製品や自社製品を割安で購入できるクーポンなどとしておけば、自社製品の宣伝にもなり、また自社製品の売り上げにもつながると言えます。
一方で、株主優待のデメリットとしては、まず、なによりコストがかかることが挙げられます。株主が数万人単位で存在する上場企業にとっては、1人あたりのコストが数100円であっても総額では数億円に上ることとなります。
また、一度株主優待を導入した場合、これを廃止すると株価が大幅に下落するリスクがあると言えます。手厚い株主優待を行っている会社ほどそのリスクは顕著となります。
株主優待制度の法的な問題点
株主優待制度には会社法上いくつか問題となりうる点が存在すると言われています。まず、(1)株主平等原則に反しないか、(2)利益供与の禁止に抵触しないか、そして、(3)配当規制に抵触しないかという問題点が挙げられます。
会社法では株主はその保有する株式の内容と数に応じて平等に取り扱われなければならないとされます(109条)。一般的には通常の株主優待であれば、株式数などに応じて扱いが平等であるし、差異が生じても軽微であることから問題はないとされます。
利益供与に関しては、優待の内容が社会通念上許容される範囲であれば問題はないとされています。これについて鉄道会社が厳格な基準をおかずに乗車券を交付していた事例で違法とされた裁判例も存在しています(高知地裁昭和62年9月30日)。
会社法では剰余金の配当や自己株式の取得に際しては厳格な財源規制が置かれており、株主優待も現物配当に当たり抵触しないかが問題となると言われています。これについても自社製品やサービスを内容としており、経済的価値としても軽微であれば、一般的には配当に該当しないとされています。
コメント
本件でトヨタ自動車は、同社の事業に対する理解を深めてもらうことと、長期にわたって株式を保有してもらうことを目的に今年3月から同社では初めてとなる株主優待制度を導入しました。
内容は株式数や保有年数に応じた電子マネーとなっていますが、専用サイトで発行された特典コードをスマホ決済アプリで入力するなど手続きが煩雑で多くの株主が期限までに受け取っていなかったとのことです。
同社は約半年間の期間延長を決定しました。
以上のように、株主優待制度は個人株主の誘引や長期保有を促すなど多くのメリットがある反面、コストや手続き面での負担も大きく、制度廃止の際の株価下落のリスクなども存在します。
また、近年では大口の機関投資家など株主優待を期待しない層からの批判も強いと言われています。それぞれのメリットデメリットなどを十分に把握した上で、自社に合った制度の導入を検討していくことが重要と言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階

- 解説動画
 岡 伸夫弁護士
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- ニュース
- 株主総会書面決議9割賛成で可決へ、会社法改正の動き2026.1.19
- 株主総会における「みなし決議」の要件を、全会一致から議決権の90%賛成へと緩和する方向で、会社...

- セミナー
 片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長) 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー) 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード