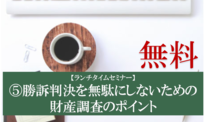今年施行予定、改正消費者裁判手続特例法について
2023/01/30 訴訟対応, 消費者契約法, 民事訴訟法

はじめに
多数の消費者に生じた集団的な被害の回復を図ることを目的とした消費者裁判手続特例法が昨年6月に改正されました。今年6月頃までに施行される見通しです。今回は改正消費者裁判手続特例法の概要を見ていきます。
消費者裁判手続特例法とは
消費者被害が生じても、消費者と事業者との間では情報量や交渉力などに格差があり、また訴訟によって被害回復を図るにも相応の費用と労力を要することから消費者が泣き寝入りすることも多いとされてきました。そこで多数の消費者被害が生じた場合に、認定を受けた適格消費者団体が消費者に代わって事業者に対して訴訟を提起し、消費者の被害を回復する制度が2016年に導入されました。これにより多くの消費者の財産的損害を回復するとともに、多くの消費者に被害を生じさせることによって得た不当な収益を剥奪し、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与するとされております。以下消費者裁判手続の概要について見ていきます。
消費者裁判手続の流れ
消費者裁判手続は二段階型の訴訟制度となっております。まず一段階目は事業者の共通義務確認訴訟となります。共通義務とは事業者が相当多数の消費者に対して、これらの消費者に共通する事実上および法律上の原因に基づき金銭を支払う義務とされます。特定的確消費者団体が訴えを提起し、共通義務に関する審理が行われます。認容判決が出た場合、二段階目の個別の消費者の債権確定手続に移行します。ここでは簡易確定手続開始の申し立てがなされ、消費者に通知・公告、団体への授権、裁判所への債権届出を経て簡易確定決定が出ると個別の消費者に支払われることとなります。ここで決定に異議がある場合は訴訟に移行することとなります。なおこの債権届出を行うことによって、最初の共通義務確認訴訟提起時に遡り時効が中断することとなります。
対象となる請求と手続主体
消費者裁判手続の対象となる請求は、事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって、消費者契約に関する次の請求にかかるものとされます(3条1項)。(1)契約上の債務の履行の請求、(2)不当利得に係る請求、(3)契約上の債務の不履行による損害賠償の請求、(4)瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求、(5)不法行為に基づく民法の規定による損害賠償の請求となっております。これに対し、いわゆる拡大損害、逸失利益、人身損害、慰謝料については対象外とされておりました(同2項)。そしてこれらの責任追求を消費者に代わって行うのが特定適格消費者団体です。これは消費者契約法に基づく適格消費者団体の中から認定要件を満たす団体を内閣総理大臣が認定します。認定要件は適格消費者団体として差止請求関係業務を相当期間行ってきたこと、体制や業務規程、経理的基礎などが適正であること、報酬・費用などの算定や支払いが消費者利益の見地から不当でないことなどが挙げられております(65条)。
令和4年改正
昨年の法改正によって、まず対象範囲が拡大されました。上記のように対象となる損害には慰謝料は対象外とされておりましたが、今回の改正でこれも対象に含まれることとなりました(3条2項)。これは財産的損害と併せて請求する場合であり、故意による場合となります。そして被告の範囲も事業者に加え事業者以外の個人も範囲に入りました(同1項、3項)。これは悪質商法に関与した事業の監督者や被用者を想定しております。消費者への情報提供の方法も拡充されます。事業者に消費者への個別通知を義務付け(28条)、消費者の氏名等の情報カイジも早期に可能となり(9条)、適格消費者団体からの通知も簡潔になり(27条2項)、行政による情報公開も拡充されます(95条)。また一段階目の訴訟でも柔軟な和解が可能となります(11条)。さらに適格消費者団体を支援する法人を認定する制度の導入や、時効の特例の整備、特定適格消費者団体の認定期限も6年に延長されるなど当事者の負担軽減も図られることとなります。
コメント
以上のように2016年に導入された消費者裁判手続特例法では、多数の消費者被害を出した事業者に対し、特定適格消費者団体が消費者に代わって損害の回復を図っていく制度です。しかし同制度の利用は期待されていたほどには進んでおらず改善が必要とされてきました。そこで昨年の法改正によって対象範囲の拡大、和解の柔軟可、消費者への情報提供の拡充などが図られております。これにより従来は不可能であった慰謝料請求や事業者の背後の首謀者も対象とすることが可能となります。また同法改正に伴って消費者契約法も改正されており、契約の取消権の追加や解約料の説明努力義務、不明確な免責条項の無効化などが盛り込まれます。このように近年消費者被害への救済制度の拡充が進んでおります。自社の事業への影響なども踏まえ、法改正の動きに注視していくことが重要と言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士) 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年) 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- ニュース
- 株主総会書面決議9割賛成で可決へ、会社法改正の動き2026.1.19
- 株主総会における「みなし決議」の要件を、全会一致から議決権の90%賛成へと緩和する方向で、会社...

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- 解説動画
 大東 泰雄弁護士
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- セミナー
 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30

- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階