法的観点からみた阿久根市ブログ市長解職問題
2011/01/17 行政対応, 民法・商法, その他

1.ブログ市長解職
竹原信一前市長が住民投票で失職した鹿児島県阿久根市の出直し市長選挙は、
竹原前市長を破ってリコール運動を進めた市民グループの推した新人、
西平氏が8509票を獲得し、前職の竹原前市長に864票の差をつけて初当選を果たした。
この事件に関するリコール手続および竹原前市長の専決処分について、
法的観点から考えてみたい。
2.リコール手続
市長の解職請求(有権者総数が40万を超えない小・中規模の市)の場合
、リコール手続は地方自治法(以下、「地自法」という。)に基づいて、
以下のような形で行われる。
①署名集め
有権者が有権者総数の3分の1以上の者の署名を集める(地自法81条1項)
↓
②代表者による署名提出
署名を集めた者の代表者(以下、「代表者」という。)が市の選挙管理委員会に対し、
集めた署名を提出して、市長の解職請求を行う。
(参考: class="broken_link">署名提出の様子を取材した朝日新聞の記事)(リンク切れ)
↓
③選挙管理委員会による請求の要旨の公表(地自法81条2項、76条2項)
(参考: class="broken_link">請求の要旨について公表された阿久根市ホームページ)(リンク切れ)
↓
④選挙管理委員会による住民投票の実施(地自法81条2項、76条3項)
(参考:住民投票の実施についてあらわした阿久根市ホームページ)(リンク切れ) →代替リンク
↓
⑤選挙管理委員会による代表者・市長・市議会議長に対する住民投票の結果の通知、
および、その結果の公表(地自法82条2項)
(参考:住民投票の結果を公表する阿久根市の広報)(リンク切れ)
↓
⑥住民投票の結果、市長の解職につき有権者の過半数の同意があった場合、
市長は失職する(地自法83条)
↓
⑦市長選挙の実施
以上が、地自法に基づいた市長の解職手続の概略である。
現在の地自法においては、このような慎重な手続がとられているため、
市長の解職手続には、通常6ヶ月から1年程度の期間が必要となる。
なお、市長の解職手続を行うに当たっては、
市長の汚職や健康上の問題などの市長の不適格性を指摘する必要がない(地自法81条参照)。
そのため、今回の阿久根市長の解職において、
仮に市長の専決処分等になんら違法性がなかったとしても、
解職請求は有効となると考えられる。
3.副市長選任の専決処分の適法性
(1)通常の手続
地自法162条によれば、副市長は市長が議会の同意を得て選任することとなっている。
ところが、今回、竹原前市長は議会の同意を得ていない。
(2)例外的に専決処分が許される場合にあたるか
ア.序
そこで、今回の副市長の選任にかかる同意につき、
市長が議会の同意を代わって行う専決処分として適法となるか否か、考えてみたい。
イ.地自法180条に基づく専決処分としての適法性
今回の副市長の選任に関する同意は、議会の指定による委任を受けていない。
そのため、地自法180条に基づく専決処分としては適法とならない。
ウ.地自法179条に基づく専決処分としての適法性
(ア)では、地自法179条に基づく専決処分としてはどうだろうか。
同条の専決処分として有効となるためには、「議会の議決すべき事件について特に緊
急を要するため議会を召集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」
という要件を満たす必要があるが、今回の件で、その要件を満たしているのだろうか。
(イ)この要件は、災害があって直ちに予算が必要である場合など、
市長が議会を召集しようとしても召集できないような場合を想定したものと考えられる。
そこで、この要件を満たす場合とは、市長が議会を召集する行為を行おうとしているが、
災害等によって召集できない場合をいうと解される。
(参考:副市長の選任に関する専決処分についての片山総務大臣(当時)の見解)
(ウ)この解釈に基づいて、今回の副市長の選任を考えてみる。
竹原前市長は、副市長の選任にあたり、議会を召集していない。
また、当時阿久根市に災害等は発生していなかった。
したがって、今回の副市長の選任にかかる専決処分は、市長が議会を召集する行為を行おうとしているが災害等によって召集できない場合にはあたらず、
地自法179条の要件を満たさないといえる。
(エ)よって、今回の副市長の選任に関する同意は地自法179条に基づく専決処分として、適法とならないと考えられる。
(3)結論
以上より、竹原前市長の副市長選任に関する専決処分は適法性を欠き、
違法であると考えられる。
4.総括
このように、法的観点から考えると、
①市政は違法な専決処分による混乱がみられた
②しかし、そのような状況下においてもリコール手続は法に則って適法に行われたということがいえる。
このことから、リコール制度は市民が市政に対し直接影響を与える重要な制度であり、
違法な処分が乱発される状況になってもなお「住民の切り札」として機能するものであることが実証されたと考える。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
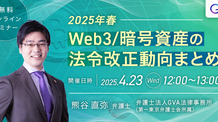
- セミナー
 熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- 解説動画
 加藤 賢弁護士
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- ニュース
- 二次会・三次会でのセクハラに初の労災認定 ー大阪地裁2025.12.16
- 会社の3次会で上司からセクハラを受けて休業を余儀なくされたとして、ITエンジニアの女性が労災認...

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分






















