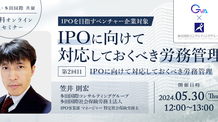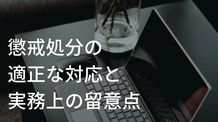企業への影響大!?~年次有給取得の義務化について~
2018/11/06 労務法務, 労働法全般

1.はじめに
2018年6月29日、「労働基準法等の一部を改正する法律案」(通称:働き方改革法案)が成立しました。主な改正内容には、「時間外労働の上限規制」、「同一労働同一賃金の義務化」、「年次有給取得の義務化」といったものがあり、企業にとって、影響は少なくないものと思われます。この改正法は、2019年4月から施行されることになっており、今、改めて確認しておきたい法務担当の方も少なくないのではないでしょうか。
そこで、今回は、その中でも、「年次有給取得の義務化」について、詳しく見ていきます。
2.年次有給取得の義務化とは
年次有給取得の義務化とは、年休が10日以上付与されている労働者(以下、『労働者』といいます。)に対して、最低5日以上の有給休暇を与えなければならないことを言います。『労働者』とは、具体的には、①継続勤務年数が6ヶ月以上の正社員又はフルタイムの契約社員、②継続勤務年数が3年半以上で週4日以上勤務するパート・アルバイト社員、③継続勤務年数が5年半以上で週3日以上勤務するパート・アルバイト社員が該当します。ただし、その期間の出勤率が8割以上でなければ、年次有給取得の義務の対象とはなりません。
このような、 『労働者』 が、5日以上の年次有給休暇の申請をしない場合、使用者は、 『労働者』 の希望を聞いた上で(例:使「いつ休みたいですか。」労「〇月〇日、◇月◇日…でお願いします。」)、有給を付与(例:使「それでは、◇月◇日に休んでください。」)しなければなりません。
以下、具体例を見てみましょう。
・ 『労働者』 が、3日のみ年次有給休暇を取得した場合
この場合、使用者は、最低2日、年次有給休暇を付与しなければなりません。
・ 『労働者』 が、1日のみ年次有給休暇を取得しており、計画年休制度により2日間年休を付与した場合
この場合も、使用者は、最低2日、年次有給休暇を付与しなければなりません。
・ 『労働者』 が、5日の年次有給休暇を取得した場合
この場合、使用者は、年次有給休暇を取得させる義務を負いません。
・『労働者』が、計画年休制度により5日間の年次有給休暇を取得した場合
この場合も、使用者は、年次有給休暇を取得させる義務を負いません。
3.コメント
会社がこの義務に違反した場合、30万円以下の罰金が科せられることになっており、注意が必要です。
会社の法務担当としては、会社の年次有給休暇を5日以上取得しているか否かを調査し、その結果によって以下の対応が考えられます。
1.従業員毎に年次有給休暇を時季指定する対応
会社の年次有給休暇を5日以上取得している労働者が多い場合には、従業員毎に年次有給休暇を時季指定する対応が適していると考えられます。
具体的には、従業員から年次有給休暇の時季指定の請求がない場合、会社から従業員毎に年次有給休暇の時季の希望を聴取し、年次有給休暇を付与する対応です。
この方法のメリットとしては、既に計画年休制度を導入していない会社であっても、直ちに会社の義務を果たすことができることが挙げられます。
一方で、デメリットとしては、時季指定請求をしていない従業員毎に有給の時季の希望を聴取し、管理しなければならないという事務処理の負担があることが挙げられます。また、その管理が上手くいかなければ、罰則が適用されてしまうおそれがあることも挙げられます。
2.計画年休制度を利用する対応
会社の年次有給休暇を5日以上取得している労働者が少ない場合には、計画年休制度を利用するという対応が適していると思われます。
計画年休の付与の方法としては、企業もしくは事業所全体に一斉に付与する方法、班やグループ毎に交代制で付与する方法、年次有給休暇付与表を用いて、従業員毎に付与する方法が考えられます。
計画年休制度を利用するメリットとしては、従業員毎に時季指定する場合とは異なり、個別に年次有給休暇を管理する必要がなくなるため、罰則をおよそ回避できることが挙げられます。
一方で、デメリットとしては、計画年休制度を導入するためには、労使協定を締結することが必要であるため、柔軟に導入することができないこと、一度年次有給休暇の時季指定をすると、後日時季を変更しようとしても、柔軟に変更できないことが挙げられます。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 解説動画
 大東 泰雄弁護士
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌)) 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- セミナー
 森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45

- ニュース
- クスリのアオキが買収防衛策を導入予定、大株主オアシスは反対2026.2.12
- NEW
- 「クスリのアオキ」が臨時株主総会で買収防衛策の導入を予定していることがわかりました。これに対し...
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- 法務の業務効率化