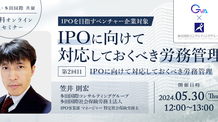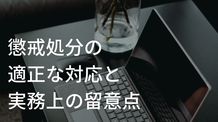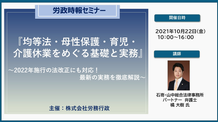いなげやに賠償命令、障害者雇用促進法について
2017/12/01 労務法務, 労働法全般

はじめに
職場でいじめを受けて退職に追い込まれたとして、知的障害のある男性(27)がスーパー「いなげや」とその従業員を相手取り、約580万円の損害賠償を求めていた訴訟で先月30日、東京地裁は計22万円の支払いを命じました。暴言による精神的苦痛が認定されております。今回は障害者雇用促進法上の義務について見ていきます。
事案の概要
報道などによりますと、原告の男性は軽度の知的障害があり、2008年に障害者雇用枠で同社に入社しました。横浜市内の店舗で食品の陳列などの作業に当っていましたが、2009年頃から指導役の従業員から「幼稚園児以下」「馬鹿でもできる」などの暴言や暴行を受けるようになったとしています。男性は同従業員と同社に対し、使用者責任と障害者への就労環境を整える義務違反を理由として約580万円の賠償を求め提訴しておりました。
障害者雇用促進法とは
障害者雇用促進法は障害者の雇用機会の均等と待遇の確保を通じて障害者の職業の安定を目的とし、全ての事業主に対して一定の配慮等を義務付けております。昨年施行された改正法では精神障害者も対象となり、事業主には一定の割合での障害者の雇用義務、差別禁止および合理的配慮義務、紛争解決義務などが定められております。この雇用義務や紛争解決義務は努力義務となっておりますが、一定の場合には企業名公表などのペナルティがあります。
障害者雇用義務
全ての事業主は常時雇用する労働者における一定割合を障害者の雇用に当てなければならないとされております。この割合を法定雇用率と言い、民間事業者の場合は現在2.0%となっております。つまり従業員が50人いた場合、1人は障害者を雇用しなくてはならないということです。この常時雇用する労働者とは、期間の定めのない労働者であるか、雇入れから1年を超えて雇用されることが見込まれる労働者を言い、週の労働時間が20時間以上の者を言います。従業員の数が45.5人以上の場合は毎年ハローワークに障害者雇用状況の報告や障害者雇用促進者の選任などが義務付けられ、雇用状況が水準に満たさない場合には「障害者雇入れ計画」の策定命令が出されます(46条1項)、さらに計画の適正実施勧告がなされ(同6項)、それに従わない場合は企業名の公表が行われます(47条)。なお法定雇用率は来年の平成30年4月1日から2.2%に引き上げられる予定です。
合理的配慮義務
事業主に対しては、募集、採用、賃金、配置、昇進、降格、福利厚生等あらゆる場面において、障害者であることを理由とする差別的取扱が禁止されます(34条~36条)。また障害者が職場で働くにあたっての支障を除去するための措置や、障害者である労働者からの相談に応じ、対応するための体制の整備をする義務があります。この合理的配慮義務は、その措置を講じることが事業主にとって過重な負担となる場合には除外されます(36条の2但書)。過重な負担であるか否かは、それにかかるコストや企業の規模、財務状況、事業活動への影響の大小、事業所の立地条件、公的支援の有無などを考慮して判断することとなります。たとえば車椅子を使用している障害者の場合、机の後ろのスペースを大きく空けて移動しやすくするといった配慮は考えられますが、通路やエレベーター等をバリアフリーに改造するといったことは負担が大きいと言えます。
障害者の能力不足を理由とする解雇
障害者雇用促進法では、障害者が適切に労働に従事できるよう配慮する義務が定められておりますが、障害者がミスを繰り返し、改善が見込まれない場合に、それを理由として雇い止めや解雇はできないのでしょうか。この点について裁判例では、5条の趣旨に基づき事業者は労働者が自立して業務遂行できるよう支援し、障害の実態に即した適切な指導を行う努力義務がある一方、4条では「障害者は自ら進んでその能力の向上を図り、有為な職業人として自立するよう務めなければならない」としていることから、相応の指導を行ったにも関わらず改善がなされない場合は雇い止めもやむを得ないとしています(東京高裁平成22年5月27日)。
コメント
本件で原告男性が「いなげや」の指導役従業員から「幼稚園児以下」「馬鹿でもできる」などの暴言を受けていた点が裁判所により認定されました。知的障害がある場合には仕事内容の理解・把握や仕事の能率面で健常者に比べてある程度劣ることは一般的に想定されており、その程度に応じて、本人の理解力を配慮した上で適切に指導することが求められます。また指導役の従業員にこのような暴言などを吐かないよう適切に指導することも合理的配慮に含まれるものと思われ、それによって過重な負担となるものではないと言えます。本件ではこの点につき不法行為に当たる点は認めましたが、合理的配慮義務違反までは認めませんでした。この点についての裁判所の判断はいまだ例が少ないのが現状であり、今後の控訴審などの展開を見守る必要があります。今後障害者の雇用促進についてはより事業者の義務が拡充されていくものと思われます。以上を踏まえて障害者に対しどのような措置が必要であり、また必要でないかを見極め、適切に対応していくことが重要と言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- 医学生への貸与金制度、県内勤務9年を条件とする高額違約金条項は不当 ー甲府地裁2026.1.22
- 山梨県が実施する大学医学部生向けの修学資金貸与制度をめぐり、違約金条項の差止めを求めた訴訟で、...
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 解説動画
 浅田 一樹弁護士
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
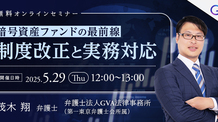
- セミナー
 茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- 解説動画
 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌)) 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...