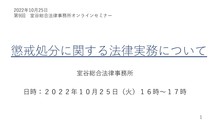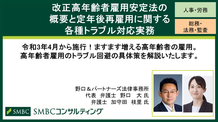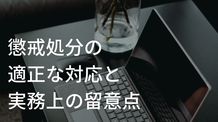パワハラの現状と企業の法的義務
2017/03/22 労務法務, 労働法全般, その他

はじめに
某有名俳優と所属事務所との間で、パワハラをめぐって争いが生じています。パワハラにより企業が被る損害は甚大であるにもかかわらず、対策は進んでいないのが現状です。今回は企業におけるパワハラの現状を再確認し、企業に課される義務がどのようなものか確認していきます。
パワハラ により生じる会社の損害
パワハラは個人的な被害の問題ではなく会社全体にとって大きな損害となり得ます。なぜなら、加害者・被害者という人的資源を失う可能性を含むだけでなく、職場環境を悪化させるからです。職場環境の悪化は、職員の士気を下げ、生産性・能率を下げることになります。また、職場環境の悪さは企業イメージを低下させ、さらなる人的資源の流出にもなります。さらに進んで訴訟になれば、イメージの低下、賠償、弁護士費用等、会社に降りかかる損害は測りしれません。 実際に、あかるい職場応援団(厚生労働省運営サイト)によると、企業へのアンケートで97.1%の企業がパワハラによる影響として職場環境の悪化を挙げています。パワハラによる職場環境の悪化についての問題意識は高いといえるでしょう。
パワハラ 被害と対策の現状
都道府県労働局等への相談件数をみると、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数、民事上の相談件数全体に占める割合は年々増加しています。また、「嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」ことによる精神障害とその労災補償の件数も同様です。それゆえに、企業全体の約80%が、パワハラの予防・解決のための取組が経営上の課題として「非常に重要」ないし「重要」と答えています。それにもかかわらず、パワハラの予防・解決に向けた取組をしていると答えた企業は、全体で45.5%、従業員99人以下の企業では18.2%に留まっています。また、パワハラを受けた人の約半数が「なにもしなかった」と答えています。このように、パワハラ問題の深刻化の一方で、企業の対策は不十分で被害者は何もできないでいるのが現状です。そこで、パワハラ対策についての企業の法的義務について今一度確認していきましょう。
職場環境配慮義務
まず、職場環境配慮義務についてみていきます。内容と法律での明記までの流れを大まかに見ていきましょう。
①職場環境配慮義務とは
職場環境配慮義務とは一般的には労働者が働くための環境を安全・快適に整備する会社の義務のことを言います。判例は「特別な社会的接触関係」にある当事者間では、信義則上、一方が他方の安全を配慮する義務を負うとしました(最高裁昭和50年2月25日)。また、この義務は雇用契約からも生じるものであり、内容は具体的状況により異なります(最高裁昭和59年4月10日)。さらに進んで、ここでいう安全とは一般業務から生じるような危険だけではなくて、他の職員から及ぼされる危険からの安全も含まれると考えられるようになりました(横浜地裁平成14年6月27日)。
②労働契約法5条への明記
判例は信義則等を根拠として義務を導いてきました。それゆえに、義務の根拠を明確にする必要性が叫ばれていました。そんな中で、平成20年3月1日に労働法5条で「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」として、配慮義務が明文化されました。ここで言う「生命・身体の安全等」には心身の健康も含まれるとされています(平成24年8月10付け基発0810第2号)。なお、雇用均等法21条はセクハラに関して会社の職場環境配慮義務について規定しており、ここからパワハラに関する職場環境配慮義務を導く考え方もあります。企業がこのような義務を怠れば債務不履行として賠償責任が生じます(民法415条)。
使用者責任
また、民法715条1項本文では「ある事業のために他人を使用するものは、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」とされています(使用者責任)。使用者責任は本来、会社がパワハラ被害者に対して負う責任ではありません。パワハラ加害者の不法行為責任(民法709条)を会社が肩代わりするものです。裁判例としては、大阪地裁昭和55年3月26日、千葉地裁平成11年9月21日ではパワハラについての企業の使用者責任を肯定されています。 しかし、被用者の選任・監督について使用者が相当の注意を払ったことを証明すれば免責されます(同但書)。したがって、民法715条が会社に求めている使用者責任は決して無条件の肩代わりを求めるものでは有りません。会社内でのパワハラが不法行為に至らないように監督する義務が課されているといえるでしょう.
コメント
以上のように、企業には職場環境を整備し、従業員を適切に監督することが法律上求められています。この法的義務を果たすため、各企業は対策を講じていくことになります。パワハラ予防のためには、労使協定の締結、社内アンケートの実施、研修の実施、組織方針についての周知や啓発等が行われています。パワハラ事案の解決や再発防止に向けて窓口を設置することも大変有効です。
関連サイト
あかるい職場応援団(厚生労働省)
基発0810第2 号平成24年8月10日(労働契約法の施行について)
職場のパワーハラスメントに関する実態調査(平成24年7月調査)(厚生労働省)
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階

- ニュース
- 太平洋工業でTOBが成立、MBOのスキームについて2026.1.29
- NEW
- 自動車部品メーカーの太平洋工業(大垣市)は27日、経営陣によるMBOに向けて進めていた株式公開...

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- 解説動画
 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌)) 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
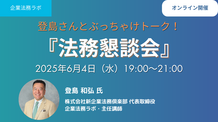
- セミナー
 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード