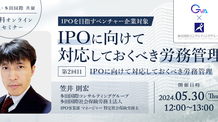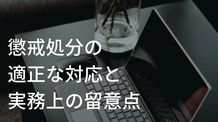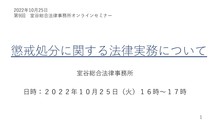電通女性社員の死からひも解く日本企業の過労死
2016/10/13 労務法務, 労働法全般, その他

1事案の概要
東京労働局は、電通に対して長時間労働対策をするよう指導しました。これは去年12月に電通の女性社員が過労を理由に自殺したことを受けて行われた措置です。また、自殺した女性は、残業時間が1ヶ月で100時間以上の長時間労働による過労が原因として労災と認定されました。
2過労死は年々増加傾向
日本の労働時間は、OECD加盟国の中で最も長いです。OECD加盟国の平均労働時間は259時間に対し、休日も含めた日本人の平均労働時間は、およそ375時間になっています。
そして、厚生労働省が発表したデータによると、脳心臓疾患等による過労死の労災請求件数は795件と前年度よも32件増加し、精神障害等による過労自殺の労災請求件数は1515件と前年度よりも59件増加しています。このように、過労死は、年々増加傾向にあります。
3過労死を取り巻く法律
(1) 過労死等防止対策推進法
過労死等防止対策推進法は平成26年11月1日に施行されました。
過労死等防止対策推進法は「近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与すること」を目的としています。(同法1条)
そして、同法は今まで定義されていなかった「過労死」について初めて以下のように定義しました。
「過労死」とは、「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害」を指します。(同法2条)
もっとも、同法は事業主に直接罰則を与えるものではありません。国や地方公共団体に対して以下のような過労死対策をするよう努めるべきとの法律です。
過労死等防止対策推進法
(2) 過労死等の防止のための対策に関する大綱(平成27年7月24日閣議決定)
過労死等防止対策推進法7条に基づき大綱が閣議決定されました。
本大綱では国や国以外の者に対しての対策が書かれています。
事業主へ求められる対策は、国が行う対策に協力するとともに、労働者を雇用する者として責任をもって対策に取り組むよう努めるとあります。具体的には2つあります。
一つ目は、①経営幹部等の取り組みです。具体的には、最高責任者・経営幹部が先頭に立って取組等を推進するようにする。また、働き盛りの年齢層に加え、若い年齢層にも過労死等が発生していることを踏まえて、取組の推進をする。さらに、過労死等が発生した場合には、原因の究明、再発防止対策の徹底する。
二つ目は②産業保健スタッフ等の活用です。具体的には、産業スタッフ等の専門的知見の活用を図ります。また、常駐するスタッフが適切な役割を果たすよう環境整備を図るとともに、産業医がいない規模の事業場では、産業保健総合支援センターを活用した体制の整備をします。
過労死等の防止のための対策に関する大綱まとめ
(3) 労災関係
労働災害として企業に労災補償義務が生じ、労災保険給付の対象となります。また、企業に安全配慮義務違反(労働契約法5条)などが認められれば、従業員の遺族から企業に対し債務不履行を理由とする損害賠償請求をされます。
4過労死と判断されるライン
現在、労働行政での過労死ラインは80時間(月に20日出勤とすると、1日4時間以上の残業・12時間労働)となっています。ただし、あくまで目安であって絶対的なものではありません。
労働時間については詳しくは以下の企業法務NAVIまとめを参照してください。
法務NAVIまとめ
5 企業がすべき対策
企業にとって過労死は単に労働力の損失だけではありません。他の従業員へ不安が広がります。したがって、企業はしっかりとした対策が必要です。
具体的には、過労死を防ぐために事業主がすべき取組みは労働基準や労働安全衛生に関する法令の遵守です。
長時間労働の削減に向けて事業主としての対策は、時間外休日労働協定の内容を労働者に周知し、出退勤時間の管理などをして週労働時間が60時間以上の労働者をなくすことです。
また、労働安全衛生法により事業主は、常時50人以上の労働者を使用する事業場では衛生管理者を選任しなければなりません。(第12条)また、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者もしくは衛生推進者の選任が必要となります。(12条の2)そして、衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業所等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康被害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。(規則第11条)
労働安全衛生法
6 参考サイト
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- セミナー
 殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー) 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- 解説動画
 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士) 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年) 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- ニュース
- 「患者からのクレームの多さ」を理由とした懲戒解雇は無効 ー東京地裁2026.1.28
- 山梨県の市立病院で理学療法士として働いていた男性(44)が「患者からのクレームが多いことを理由...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード