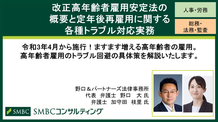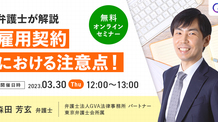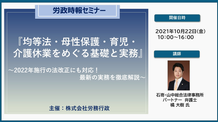総務省「テレワーク(在宅勤務)」全職員対象拡大
2014/08/26 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
今月7日、総務省は「テレワーク(在宅勤務)」をより使いやすいものとして、多様な働き方を実現するため、制度・システムの両面で充実・柔軟化を図ることを発表した。具体的には、「テレワーク」の利用対象が幹部を除く本省職員約1800人に限っていたものを全職員約5000人に拡大、育児中の職員が子どもの急な発熱などの際に利用できるように、利用当日の申請も可、自宅PC等から職場LANへ接続できる専用USBメモリーを貸与しセキュリティを確保する。
コメント
「テレワーク」は、情報通信技術を活用した場所と時間にとらわれない柔軟な働き方として、ワーク・ライフ・バランスを図りつつ業務効率・生産性の向上を実現し、少子高齢化、地域活性化等の課題解決にも資するものとして期待されている。
政府は、特に就業継続が困難となる子育て期間の女性や育児参加する男性、介護を行っている労働者などを対象に、週1回以上、終日在宅で就業する雇用型在宅型テレワークを推奨モデルとして産業界と連携支援し、利用者数を全労働者数の10%以上を目標とする。また、こうした取組も含め女性の就業支援等によって、第一子出産前後の女性の継続就業率を 55%(2009年においては 38.0%)、25歳から 44歳までの女性の就業率を 73%(2011 年においては 66.8%)まで高める。
現状として、総務省は2006年からテレワークを導入しているが、13年度の利用者は64人(のべ203人)にとどまっており、まだ定着には遠い。今回の改定により長時間労働が当たり前となっている国家公務員像を改め、見本となることを目指す。
「テレワーク」にはワーク・ライフ・バランスを図るだけでなく、大規模災害やパンデミック等が発生した際のBCP(業務継続計画)、オフィススペースや紙などオフィスコストの削減と通勤・移動時間や交通費の削減、節電対策等のメリットもある。逆に、デメリットしては、コミュニケーション効率が落ちることや上司の業務監視が及ばないことから手を抜いてしまう可能性があることが考えられる。しかし、これに対しては、情報通信技術の活用によって顔を合わせなくても情報の共有や連絡が可能であり、WEB会議、テレビ会議、スカイプなどを活用することで職場に近い環境が実現できる。また、テレワーク実施者から、メールや電話を通じた開始・休憩・終了の連絡、業務日報、成果物の提出等を徹底することにより、勤務管理を行うことが可能である。導入にあたっては、セキュリティ面での対策(上記、総務省のように専用USBの貸与など)を要するが、企業にとっての利用メリットは大きい。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
 岡 伸夫弁護士
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 解説動画
 加藤 賢弁護士
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- セミナー
 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- ニュース
- スリムビューティハウスに3ヶ月間の業務停止命令(特定商取引法違反疑い)2026.2.9
- NEW
- エステ大手「スリムビューティハウス」に対し、消費者庁が3ヶ月間の業務停止命令を出していたことが...

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階