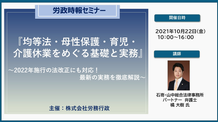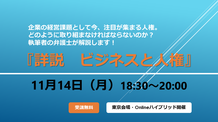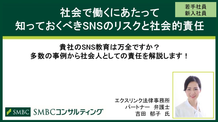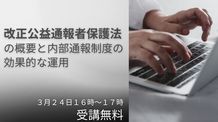自社の偽装が発覚!どうすればいい?
2013/10/28 コンプライアンス, 消費者取引関連法務, 民法・商法, その他

先日、阪急ホテルズがメニューに表示された内容とは実際には異なる食材を使用していたことを発表し、同社の信頼が大きく揺らいでいる。
28日時点では、食品とメニューの不一致が意図的な偽装であったか誤表示であったかを巡って出崎社長の釈明が行われたものの、その内容は説得力を欠くものであり、消費者の視線は厳しさを増している。出崎社長は明日にも再調査結果を公表したうえで誤表示との表現を改める予定という。
似たような問題は実際にはどの会社にも起こりうる問題である。
今回47種類のメニューが実際の食材と不一致であったが、そのなかに「鮮魚」という文言が入っていたにもかかわらず、実際には冷凍ムニエルをだしていたというものがあった。
しかし、現代の冷凍技術によると冷凍された魚であってもその鮮度は鮮魚に比べて落ちるとは一概にはいえないようだ。
そうすると当事者としてはこれくらいは大丈夫という甘い意識が働くのも、ある意味では無理からぬことかもしれない。
もちろん、偽装などということは起きて欲しくないが、起きてしまったらどうするのか?
その場合、会社法という観点からはミスタードーナツの肉まん違法添加物混入事件についての判例が経営者、ひいては法務の方に参考になるかもしれない。
この事案は、ミスタードーナツが販売している肉まんの中に違法な添加物が含まれており、取締役らがそれを知った後も売り続けたというものである。
一般に経営判断については法律上、経営者の裁量は広く認められるものであるが、この点についての判例は断固としたものであった。
判例は、取締役が事実が露見するおそれを認識しながら何らの行動も起こさなかった点について、事実が露見する蓋然性が高く、また露見したことによる被害は甚大なものになることが予想されたにもかかわらず漫然と事態を成り行き任せにすることは許されないとして、取締役らの責任を認めている。
この判例が、不祥事が露見すれば一律に経営者はそのことを公表する義務があるのか、あるいは事案の露見の可能性が少なければ公表しないことも許されるのかについて判断を下したかはさだかではないが、一般的にはやはり速やかに事実を公表した上で再発防止策の策定およびそのことのPRに務めたほうがいいだろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- ニュース
- 外国産ロブスターを伊勢海老表記で販売したサコウ食品に措置命令 ー三重県2026.2.18
- NEW
- 三重県が6日、「伊勢志摩みやげセンター王将」を運営する「サコウ食品」に対し景品表示法と食品表示...

- セミナー
 片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長) 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー) 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- 弁護士

- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- 解説動画
 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士) 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年) 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- 解説動画
 加藤 賢弁護士
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間