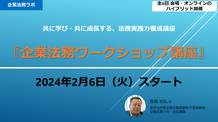だれでも目にする秘密保持契約の存在意義と本当に必要な措置を考える
2021/10/22 契約法務, 情報セキュリティ, 不正競争防止法

このコラムでは、民間企業でのビジネス経験のある法務担当者が、企業法務の世界に関心のある方向けに、初めてでも分かりやすい内容に噛み砕いてノウハウを公開していきます。
はじめに
民間企業の法務担当者がカバーする領域は多岐にわたります。
契約審査、M&A、訴訟予防、株主総会、クレーム対応、業法対応、さらに規制業種においては所轄官庁対応などに関わることもあり、とても一言では言い表すことができない業務です。
会社の方針や規模によって法務業務を担当する部署もまちまちで、業務内容に応じて扱う法律も全く異なります。ゆえに外から見ると実態が掴みづらく、法務初心者にとっては仕事のイメージが湧きにくいこともあります。また、法務業務の仕事は営業職と異なり数値目標がなく、トラブルを未然に防ぐことが目標となります。
そのため、成果がみえづらく、何をすれば企業の利益を守れるのかを常に考えていないと、頭でっかちなだけで実践的でないアドバイスや必要以上の事務負担をしてしまいがちです。
そこで、今回は、企業法務のうち誰でも最初に業務として取り組むことになるであろう「秘密保持契約」をテーマに、ビジネスの現場で法務担当者が本当に役立つためにはどうしたらいいかという視点でお伝えします。
どこでも目にする秘密保持契約
「秘密保持契約」とは、企業間が事業を推進するにあたり社外に流出すると困るような情報を事業提携先などの他社や自社の従業員に必要な範囲を超えて利用させないことを目的に、提携に先立って締結する契約です。法務の現場では必ずと言っていいほど目にします。
なぜこのような契約を締結するのでしょうか?
企業が他社に知られたくない内容とは、一般的に、製品の開発に関わる重要な情報や、新サービスの内容に関する情報、顧客に関する情報など、いわゆる企業秘密になります。
このような情報はなるべく必要最小限の範囲でしか共有しないものですが、企業が利益を生み出すためには、顧客や他社との情報交換を通じて事業を進めていく必要性が生じます。
その際にトラブルとなるケースとして、例えば、ビジネスパートナーとの協業検討の際に情報を提供したら、協力しながらビジネスを推進していくはずが、その情報を好き勝手に利用されてしまい、結局は他社に先を越されてしまった、その情報獲得のために自社で投じたコストは丸損になった…ということが起こり得ます。
事前に秘密保持契約を締結していないと、どのような情報が秘密であるのか相手方との合意がなく、文句を言おうにも根拠がない状態になってしまいます。
また自社の従業員がその情報をプライベートで流出させ利益を得たり会社の信用を損ねたりといったことも起こり得るため、従業員との雇用契約等のなかで従業員に対して守秘義務を課すこともあります。
このように自社にとって大切な情報を不本意な形で利用された場合に、損害賠償請求を行ったり被害拡大を防ぐために差止請求を行ったりするための手段、あるいは相手への抑止力としてのツールの1つとして存在するのが秘密保持契約です。
秘密保持契約の締結は必要だが、不正競争防止法対策の方が実践的
先ほど「ツールの1つ」と表現しましたが、企業の秘密を守る手段は他にもあり、不正競争防止法により保護される「営業秘密」として企業の秘密を守ることも可能です。
不正競争防止法違反とすることができれば、民事上の差止請求、損害賠償請求のほか、告訴を経て刑事罰も課すことができます。
秘密保持契約との違いは、契約を締結しなくても法律で一定の救済手段が定められていることです。ただし、企業の情報が営業秘密として認められるには「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3要件を満たしていることを証明する必要があり、これが現実的に認められるためには、日頃から要件を満たすべく社内の体制を整備しておく必要があります。
特に「秘密管理性」については、経産省が具体的にどのような措置を講じれば認められるのか公開していますので、ぜひご参考にしてください。
その他、情報漏洩の防止方法や初動対応などについてケース毎にガイダンスがありますので、掲載します。いずれも経済産業省ホームページ配下にあるものです。
・「営業秘密管理指針」経済産業省HP ・「営業秘密を守り活用する」経済産業省HP |
実際のところ、企業が重要な情報を他社や従業員との間で共有する場合に、情報漏洩防止を目的として秘密保持契約を締結することはもはや商慣習のようになっていますが、情報が流出した際の救済措置という観点では、いざというときのために不正競争防止法の活用ができるような体制づくりを目指した方がより実践的のように思います。
情報漏洩に関して秘密保持契約違反で救済が認められたケースはほぼ無く、経済的な救済措置が認められた事例については不正競争防止法違反がほとんどです。
まとめ
まとめると、秘密保持契約は、相手方に契約上の義務として秘密にしたい内容の利用や開示範囲に制限を課すことができる反面、実務上のメリットに乏しい、むしろ「秘密保持契約を締結したからあとは安心」というような法務対応では意味がない、ということでした。
その点で、企業にとって重要な情報については、実際に経済的な救済措置を得られるよう、不正競争防止法の活用ができるような対策を講じること重要であることをお伝えさせていただきました。
これからも、ビジネス目線で、企業にとって本当にメリットのある法務部員として活躍できるような豆知識や考え方を公開していければと考えています。
==========
本コラムは著者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラム内容を業務判断のために使用し発生する一切の損害等については責任を追いかねます。事業課題をご検討の際は、自己責任の下、業務内容に則して適宜弁護士のアドバイスを仰ぐなどしてご対応下さい。
【筆者プロフィール】
慶應義塾大学卒。 大手メーカー法務部にて国際法務(日英契約業務を中心に、ビジネス構築、社内教育、組織再編、訴訟予防等)、外資系金融機関にて法人部門の企画・コンプライアンス・webマーケティング推進業務を経験。現在、大手ウェブ広告企業の法務担当者として、データビジネス最前線に携わる。 企業の内側で法務に携わることの付加価値とは何か?を常に問い続け、「評論家ぶらない」→「ビジネスの当事者になる」→「本当に役に立つ」法務担当者の姿を体現することを目指す。 シンプルに考えることが得意。 |
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階
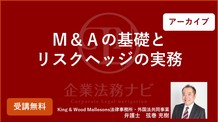
- 解説動画
 弦巻 充樹弁護士
弦巻 充樹弁護士
- 【無料】M&Aの基礎とリスクヘッジの実務
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
 岡 伸夫弁護士
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- ニュース
- 太平洋工業でTOBが成立、MBOのスキームについて2026.1.29
- NEW
- 自動車部品メーカーの太平洋工業(大垣市)は27日、経営陣によるMBOに向けて進めていた株式公開...
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階

- セミナー
 松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属) 阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード