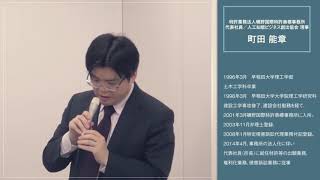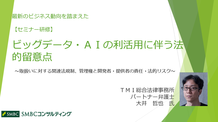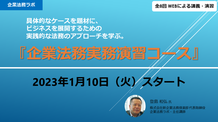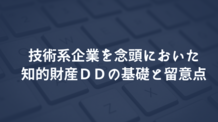大学と企業の未利用特許活用へ/共有特許について
2022/06/03 知財・ライセンス, 特許法

はじめに
政府の知的財産戦略本部がまとめた「知的財産推進計画2022」で大学と企業が共有する未利用特許を新興企業が利用しやすくするためのルールを新たに作る方針が明らかにされました。先端技術の事業化を促す狙いがあるとのことです。今回は共同発明の特許について見ていきます。
事案の概要
読売新聞によりますと、日本の大学は国内で年間6000~7000件の特許を出願しているとされます。そのうち半数以上は企業との共同研究によるもので出願費用も企業が負担しているケースが多く、大学と企業の共有特許となっているとのことです。これら大学と企業が共同で保有する特許には今後成長が見込まれるバイオ技術や宇宙、ロボット関連技術が多く含まれており、これらの特許の活用が期待されております。そこで「知的財産推進計画2022」では特許を共同で保有する企業が一定期間正当な理由なく特許を使わない場合は大学が独自に第三者にライセンスできるようルールを整備するとしております。年内にはガイドラインをまとめるとのことです。
共同発明と特許
複数の者が共同で発明を完成させた場合、その全員で特許出願する必要があります(特許法38条)。特許庁により特許が認められ、登録されますと共有特許権として全員が共有することとなります。その場合、各共有者は他の共有者全員の同意を得なければ、その持ち分の譲渡、質入れ、また他人にライセンスしたり、特許発明の実施をすることができないとされております(73条1項~3項)。これは特許を共有する者が変わることによって、その技術や資本力などに変動が生じ、特許自体の価値、ひいては他の共有者の持ち分の価値に影響を及ぼすからと言われております。また複数の者により共有されている特許について、第三者が特許無効の審判請求を行う場合も、当該特許の共有者全員を相手として審判請求の申し立てを行う必要があります(132条2項)。逆に特許権が侵害されている場合に、侵害行為の差止め請求をする場合や、損害賠償請求する場合は各共有者は単独で行うことができるとされております。
共同発明者とは
特許を受ける権利は「発明者」に帰属するとされており、発明者でない者で、特許を受ける権利を承継もしていない者が特許をうけることはできず、間違って特許を受けた場合はその特許は無効とされております(29条1項、49条、123条1項6号)。そして複数の者が共同で発明した場合は、共同者全員が発明者となります。ここに言う「発明者」とは創作行為に現実に加担した者だけを指し、単なる補助者や助言者、資金提供者などは発明者には該当しないとされております。例えば具体的な着想を示さず一般的な管理だけをした上司、研究者の指示に従い単にデータをまとめたり実験をしただけの者、研究者に資金や設備を提供した者などは共同発明者には該当しないと言われております。発明の成立過程で新しい着想を提供した者が共同発明者とされております。
職務発明制度とは
上記のように特許を受けるべき発明者とは現実に創作に加担した者であり、資金や設備提供者等は発明者には該当しません。しかし特許法の平成16年改正により、契約や勤務規則その他の定めにより、従業員から会社等に特許を受ける権利を「相当の利益」の支払いを受けることを条件として承継させることができることとなりました(35条)。これを職務発明制度と言います。この相当の利益は契約や勤務規則等によって定めることとなりますが、従業員と会社ではその保有する情報の量や質、交渉力などの点において大きな差があることから、対価が決定され、支払われるまでの全過程を総合的に判断して不合理なものであってはならないとされております(同5項)。
コメント
以上のように特許は発明者に与えられることとなります。複数の者の共同研究によって発明がなされた場合は、その全員が特許の申請者となり共有特許となります。この場合、他の共有者全員の同意がなければ持ち分の譲渡や第三者へのライセンスができないとされます。そのため大学と企業の共同研究による特許はその多くが利用されずに休眠していると言われております。そこで政府の知的財産推進計画2022では企業側が一定期間、正当な理由なく特許を行使しない場合は大学側だけでライセンスすることができるようになるとされます。また国立大学の場合でも各種規制の撤廃により、ライセンス料を現金の代わりに株式等で支払うことを可能とし、資金力の乏しい新興企業の特許活用を促すとしております。これを期に、休眠特許の積極的な活用を検討してみることが重要と言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- セミナー
 片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長) 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー) 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- 解説動画
 岡 伸夫弁護士
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- ニュース
- あおぞら銀行、内部通報した行員の長期隔離配置は違法 ー東京高裁2026.1.26
- 「あおぞら銀行」の行員が内部通報後に受けた懲戒処分を巡り損害賠償などを求めた訴訟で22日、東京...

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード