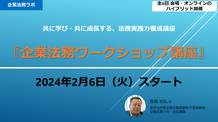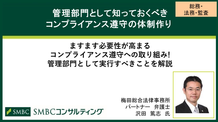時短後に契約解除のセブンイレブン元オーナー、二審でも敗訴
2023/05/12 契約法務, コンプライアンス, 民法・商法, 独占禁止法, 小売

はじめに
時短営業に切り替えた後、セブンイレブンよりフランチャイズ契約を解除された元オーナーが、解除の正当性を巡って争っていた事案で、大阪高裁は、4月27日、元オーナー側の控訴を棄却する判決を出しました。
人手不足などが理由に、セブンイレブンの合意なしに24時間営業から時短営業へ切り替えた元オーナー。この訴訟の経緯について、整理します。
訴訟までの経緯
報道などによりますと、元オーナーの男性は、2012年、株式会社セブンイレブン・ジャパンとフランチャイズ契約を締結しました。その後、一緒に店舗を運営していた妻が病気で亡くなるなど、人手不足に陥ったことから、2019年に終夜営業をストップすると宣言します。
これを受けて、セブンイレブン側は、「24時間営業に戻さなければ契約を解除する」旨の通知を行ったといいます。その後、一度はこの通知を撤回したものの、後日、顧客と元オーナー間のトラブルの様子を撮影した動画などをきっかけに、「接客態度がよくないことで店のブランドイメージが毀損された」として、フランチャイズ契約を解除する旨、通知しました。
これを受けて、元オーナーの男性は店舗の営業を停止しましたが、店舗自体の明け渡しには応じていませんでした。その後、セブンイレブン側は、元オーナーに対し、店舗の明け渡しと損害賠償を求める訴えを提起しています。
これに対し、元オーナー側は、「契約違反の行為はなく、時短営業を始めたことへの意趣返しで行われた契約解除も不当だ」として、逆に、契約解除の無効を求める訴えを提起しました。
一審の大阪地裁は、セブンイレブン側の主張を認め、解除は有効として店舗の明け渡しと損害賠償を命じました。この判決を不服として、元オーナーは大阪高等裁判所に控訴。高裁でどのような判決が下されるか、注目されていました。
今回、大阪高裁は、一審に続き、セブンイレブン側の訴えを認めた形になります。「契約の解除は、本部側から接客態度の改善を求められていたのに、横柄な言動をしたり大声でどなったりするなどの顧客対応を繰り返したためであり、『物言うオーナー』を排除する目的ではない」として、店舗の明け渡しとともに約1450万円の損害賠償の支払いを命じました。
元オーナー側は上告する方針だということです。
コンビニフランチャイズにおける24時間営業の問題点
今回の判決では、セブンイレブン側が行ったフランチャイズ契約の解除は、24時間営業を取りやめたことが原因ではないと認定していますが、24時間営業の強制については、コンビニ業界で度々問題となっています。
この問題に関し、公正取引委員会が「コンビニエンスストア本部と加盟店との取引等に関する実態調査」を行い、その結果を2020年9月に発表しています。
※調査対象:コンビニエンスストア 8大チェーンに加盟する全国57,524店(回答率21.0%)
調査の結果、77.1%の店舗が深夜帯は赤字で、93.5%が人手不足を感じているといいます。また、同調査の対象となった8チェーンではいずれも本部と加盟店との合意により時間短縮が認められる旨定められていますが、それにも関わらず、調査の結果、時短営業に関するコンビニエンスストア本部との交渉に関し、本部が交渉に応じていない(交渉を拒否している)と回答した加盟店が8.7%にのぼりました。
公正取引委員会では、コンビニの24時間営業に関し、
合意があれば時短営業への移行が認められてるにもかかわらず、本部がその優越的地位を利用して協議を拒絶し、加盟店に不当に不利益を与える場合には、独占禁止法第2条第9項第5号(ロ)に定める「取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。」(優越的地位の濫用)に該当し得る |
なお、上述のように、時短営業への移行を拒む動きが一部みられるものの、2019年以降、24時間営業に対する姿勢に変化を見せるコンビニエンスストアチェーンは増えており、24時間営業の加盟店は2000店以上減少しているといいます。
コメント
今回、セブンイレブン側が、元オーナーの接客態度に問題があった旨の証拠を提出したことで、時短営業自体が解除理由ではなかったと認定された側面があります。
上述の公正取引委員会の見解を踏まえると、オーナー側から時短営業に向けた協議を求められた場合には、原則応じる必要があります。そのため、時短営業に関する協議の申出が行われている中で、フランチャイズ契約の解除を行った場合、優越的地位の濫用と主張されるリスクが出てきます。契約解除を断行する場合は、契約解除の正当性について、十分な証拠を取りそろえたうえで進める必要がありそうです。
逆に、オーナー側としては、「時短営業の協議を求めたこと」、「一定期間、協議に応じられなかったこと」の証拠を押さえておくと、その後、訴訟に進展した場合に有利に進めることが出来そうです。内容証明等の活用を検討するのもよいと思います。
しかし、いずれにせよ、訴訟まで進展した場合、本部側・オーナー側双方に多大な負担が生じることになります。必要な証拠を残す準備は行いつつ、相手方の立場を思いやりながら粘り強い協議を進めたいところです。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- セミナー
 片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長) 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー) 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- ニュース
- 太平洋工業でTOBが成立、MBOのスキームについて2026.1.29
- NEW
- 自動車部品メーカーの太平洋工業(大垣市)は27日、経営陣によるMBOに向けて進めていた株式公開...

- 解説動画
 大東 泰雄弁護士
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...