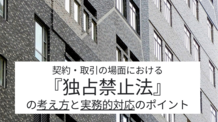独禁法審査手続き見直しの行方
2015/05/21 独禁法対応, 独占禁止法, その他

2013年に、審判制度の廃止等を内容とする独禁法改正が行われた。これを受け、公正取引委員会が行う、調査手続の在り方について、内閣府の「独占禁止法審査手続についての懇談会」で議論が行われ、2014年12月に報告書が取りまとめられた。
2013年の改正独禁法
従来、公取委の執行力強化という観点から、課徴金制度の拡充、課徴金減免制度の導入等を内容とした法改正が行われてきた。一方、公取委の執行力強化に応じた、違反被疑事業者の十分な防御権の確保が課題となっていた。
こうした問題意識から、2013年に審判制度廃止を含む法改正が行われた。それ以前は、公取委が行う排除措置命令や課徴金納付命令に不服がある場合は、公取委に対し、審判請求により、不服を申し立てることができた。
そして、この審判に不服がある場合に、はじめて裁判所(東京高裁)に提訴できるという仕組みになっており、公取委の審判が、事実上第一審としての機能を果たしていた。
この審判制度は、不服審査手続において、公取委が行政処分を下し、公取委の審判で自らが下した行政処分の適否の判断を下すということから、公平性・中立性に欠けるとの批判があった。
そこで、審判制度を廃止し、行政処分に対する不服審査を裁判所に委ねる(管轄を東京地裁に専属させる)こととなった。
一方、独禁法違反被疑事件の審査手続に関しては、改正法本則には盛り込まれず、附則第16条に「事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から検討を行い、この法律の公布後一年を目途に結論を得て、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする」とされ、内閣府に設けられた「独占禁止法審査手続についての懇談会」で議論が行われていた。
懇談会報告書の内容
①立入り検査に関する論点
Ⅰ立入検査において、事業者は弁護士を立ち会わせることができるものの、弁護士の立会いを事業者の権利として認めるものではなく、事業者は弁護士が到着しないことを理由に立入検査を拒むことはできないとすることが適当である。
Ⅱ立入検査当日における提出物件の謄写については、これを事業者の権利として認めることは適当ではなく、運用上、日々の営業活動に用いる必要があると認められる物件について、立入検査の円滑な実施に支障がない範囲での謄写が認められることが適当である。
Ⅲ立入検査に関し、公正取引委員会は、マニュアル又はガイドラインに明記して公表し、広く情報が共有されるようにするとともに、事業者に対して明確にする必要がある事項については、例えば、立入検査着手時などの適切な場面において、書面による方法も活用しつつ、事業者に伝えることが適当である。
②弁護士・依頼者間の秘匿特権に関する論点
秘匿特権については、その根拠及び適用範囲が明確でなく、その実現に当たって実態解明機能を阻害するおそれがあるとの懸念を払拭できないことから、現段階で秘匿特権を導入することは適当ではない。
もっとも、秘匿特権を全面的に否定するものではなく、十分検討に値する制度であることから、今後の検討課題としている。
③供述聴取に関する論点
Ⅰ現状の仕組みの下で供述聴取時の弁護士の立会い及び供述聴取過程の録音・録画を認めるべきとの結論には至らなかったが、実態解明の実効性を損なわない措置を検討する中で、その必要性を含め導入の可否を検討していくことが適当である。
Ⅱ調書作成時における供述人への調書の写しの交付、供述聴取時における供述人によるメモの録取及び自己負罪拒否特権については、これを認めるべきとの結論には至らなかった。
Ⅲ公正取引委員会は、次の点につき指針等に明記して公表し、広く情報が共有されるようにするとともに、供述人に対して明確にする必要がある事項については、例えば、供述聴取を実施する前などの適切な場面において、書面による方法も活用しつつ、供述人に伝えることが適当である。
・供述聴取が任意のものであるか間接強制権限による審尋であるかを供述人に対して明確にする。
・聴取時間の目安を示す。
・供述聴取に支障が生じない範囲で、食事時間等の休憩は供述人が弁護士に相談できる時間となるよう配慮しつつ適切に確保する。休憩時間には供述人が弁護士等の外部の者と連絡を取ることやメモを取ることが妨げられないことを供述人に対して明確にする。
・調書の読み聞かせの段階で誤りがないかどうかを問い、供述人が増減変更の申立てをしたときは、審査担当官がその供述を調書に記載することを供述人に対して明確にする。
・供述聴取時において供述人が審査担当官の対応に不満がある場合に苦情を受け付ける仕組みを公正取引委員会内部に整備する。
今後の方向性
経団連は、審査手続の適正化のために、供述聴取時の弁護士の立会い、弁護士・依頼者間秘匿特権の導入などを求めてきたが、報告書においては、実態解明機能への影響が懸念されるとして、これらの点について、認めるべきとの結論には至っていない。
もっとも、報告書によれば、企業が調査に協力することにより、課徴金を減額する裁量型課徴金制度や、非協力・妨害に制裁などを課す仕組みが導入された場合には、「事業者による協力が促進されることにより、現状の仕組みの下で懸念されるような実態解明機能が損なわれる事態は生じにくくなると考えられる」としており、経済界が求める、防御権の保護が実現される余地はある。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- セミナー
 松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属) 阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- ニュース
- 買収防衛策?フジ・メディアHDが基準日を1月18日に設定2025.12.24
- NEW
- フジ・メディア・ホールディングスは22日、臨時株主総会の招集に向けた基準日を2026年1月18...
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階