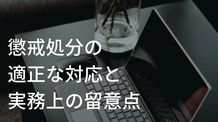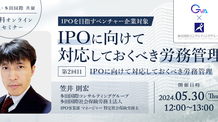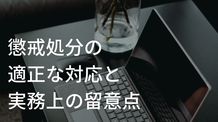雇用差別禁止法制について
2018/10/18 労務法務, 労働法全般
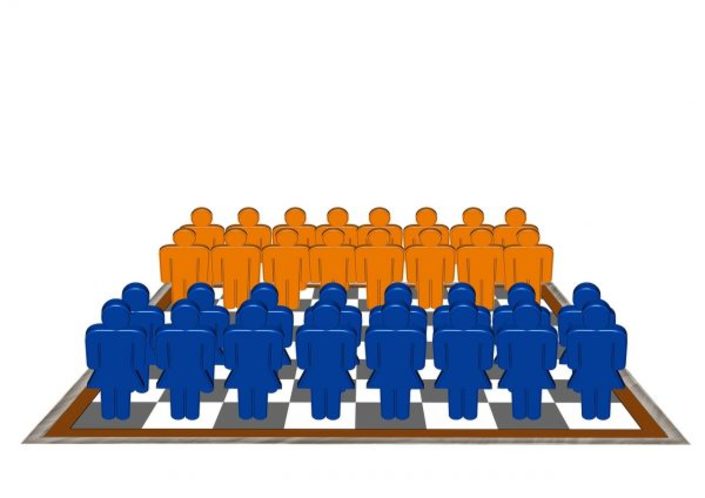
1 はじめに
差別禁止に関するルールは、今日、労働法独自の一領域として確立しつつあります。そこで今回は、平等な雇用を実現して法的リスクを軽減できるよう、雇用差別禁止法制を概観していきたいと思います。
2 雇用差別禁止法制について
労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することが重要な課題となっています。雇用機会禁止法制は、憲法14条に規定される法の下の平等を出発点にしています。1947年に制定された労基法でも、国籍・信条・社会的身分による差別的取扱いをしてはならないと規定され(3条。均等待遇原則)、男女賃金差別が禁止されています(4条)。
労基法3条の差別禁止事由は、国籍・信条・社会的身分の3つとされています。信条とは宗教的・政治的信念を含むと解されており、社会的身分とは人種を含むと解されていますが、現在政策課題とされている性別・障害・雇用形態等による差別的取扱いは、労基法上は禁止されていません。このように、労基法が差別として禁じるものには限界があり、契約自由の原則が均等待遇原則に優先されがちな状況は今なお続いているといえます。
3 性別に基づく差別の禁止
男女雇用機会均等法は、企業に対して採用や昇進・職種の変更などで男女で異なる取り扱いを禁じる法律です。雇用の分野における男女均等な機会及び待遇の確保等のために第5条から第9条、事業主の講ずべき措置が第11条から第13条、労働者派遣法第47条の2、規則13条に規定されています。
労働者・雇用者を取り巻く状況は変化していきます。法改正も段階的に行われてきていますが、改正には手間がかかるため、厚生労働省は定期的に指針等を公表しています。
〈指針一覧〉
・労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針
・事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上、講ずべき措置についての指針
・事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針
4 障害に基づく差別の禁止
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律は、障害を理由とする差別を解消し、障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会を実現しようとするものです。
全ての事業主に募集・採用など雇用のあらゆる局面での障害者に対する差別が禁止されています。厚労省HPでは周知用のパンフレット、自社が不当な差別を行っていないかを自分で確認できる点検資料、告示として障害者差別禁止指針と合理的配慮指針等が公開されています。
平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されています。雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずることが求められています。
5 労働上の地位に基づく差別の禁止
パートタイム労働法(正式名称「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)は、適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを講じることによって、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための法律です。
平成27年改正によって、適用の対象が拡大されました。改正前まで、(1)職務内容が正社員と同一、(2)人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3)無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることが適用要件とされていました。改正後は、(1)、(2)に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者にも適用され、正社員との差別的取扱いが禁止されるようになりました。その他にも、短時間労働者の待遇の原則、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務、パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務等が新設されました。
6 その他の差別について
雇用上の差別は様々な要因によって発生します。社会に相当数存在する性的少数者・刑務所出所者等も就職先を必要としていますが、特別な法的保護がなく、差別を受けやすい立場にあるといえます。雇用に対しては労力に見合った賃金を支払うのが原則であり、このような人材に対して差別的取り扱いをすると、訴訟などの法的リスクが発生するおそれがあります。ある労働者に対して、他の労働者との間にある一般的な労働条件とは異なる条件を提示する場合、その労働者が労基法3条にいう機会均等原則に含まれない者であったとしても、限界が広がりつつあるという潮流を念頭に置いたうえで、合理的説明ができるかどうかも考えたうえで実施するとよいでしょう。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- 解説動画
 加藤 賢弁護士
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
 大東 泰雄弁護士
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...

- ニュース
- 買収防衛策?フジ・メディアHDが基準日を1月18日に設定2025.12.24
- フジ・メディア・ホールディングスは22日、臨時株主総会の招集に向けた基準日を2026年1月18...
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- セミナー
 森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45