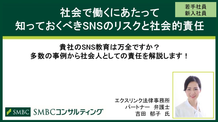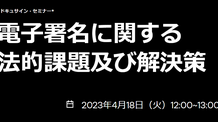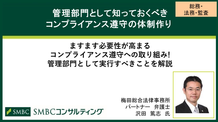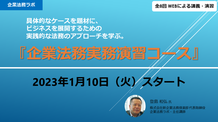不利益を受けても97%が申告せず、インボイスと独禁法
2025/06/02 契約法務, 税務法務, コンプライアンス, 独占禁止法, 租税法, 下請法
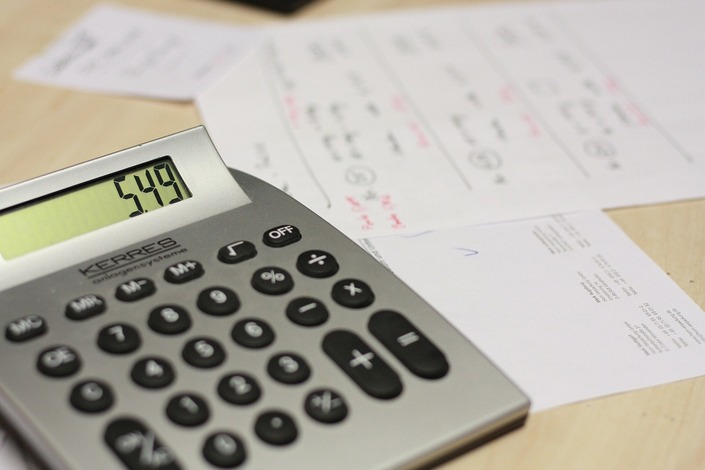
はじめに
インボイス制度を巡り、取引先から不利な契約を迫られる被害を受けたとする事業者の約97%が公取委に申告していなかったことがわかりました。取引先との関係悪化を懸念したとのことです。
今回はインボイス制度を巡る独禁法などの問題を見ていきます。
事案の概要
報道によりますと、インボイス制度の廃止などを求める団体「インボイス制度を考えるフリーランスの会」が3~4月にオンラインで実施したアンケートで、取引先から一方的な取引額の値下げや取引の打ち切りに遭ったとの回答が4370件にのぼったとのことです。
また、このうち97.2%が公取委への申し立てをしなかったと回答したといいます。
その理由として、取引先との関係性の懸念が61.9%で最多、制度によるものか明確な証拠がなかったとするものが24.3%、相談窓口を知らなかったとするものが19.8%とされています。
公取委は不利な契約を一方的に強いる行為は独禁法に抵触する可能性があるとして警戒を強化しています。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入された制度で、消費税の仕入税額控除を受けるためには「適格請求書(インボイス)」を必要とするというものです。
適格請求書は消費税法により、取引内容を明確化するため登録番号や取引年月日、取引内容、適用税率などの記載が求められ、適格請求書発行事業者として登録された事業者のみが発行できます。
本来、消費税法では年間売上高が1000万円を超えない個人事業者は消費税の申告・納税義務が免除されていました(免税事業者)。
しかしこの制度の導入により、取引先から適格請求書を求められた場合、納税を行う適格請求書発行事業者として登録せざるを得ない状況となっており、個人事業主から強い反発がなされていました。
なお、取引先が消費者や免税事業者、または簡易課税制度適用事業者である場合は適格請求書は不要です。簡易課税制度適用事業者とは、前々年度の課税売上高が5000万円以下である事業者をいいます。
独禁法の優越的地位の濫用
上記のように免税事業者と取引する場合、自己が免税事業者や簡易課税制度適用事業者である場合はこれまでどおり適格請求書は不要です。
それ以外の場合でも、経過措置として制度導入後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入税額控除が可能とされます。
しかし、やはり免税事業者に対して適格請求書を求める、または控除できない消費税分を取引代金から減額するといったことも予想されます。
免税事業者に対しこれらの対応を一方的に行った場合は、独禁法の優越的地位の濫用などに該当する可能性があると公取委は注意喚起しています。
独占禁止法2条9項5号では、「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に」相手方に不利益を強いる行為を禁止しています。
優越的地位の濫用の要件
優越的地位の濫用における「優越的地位」とは、取引において相手方が不当または不利益な要請であっても従わざるを得ない関係を言います。
公取委のガイドラインでは、
(1)劣位の側が優位の側に対しどの程度取引を依存しているか
(2)優位の側の市場での地位
(3)取引先変更の可能性
(4)その他相手方と取引の必要性
などを総合的に考慮するとされています。そして、禁止される濫用行為について2条9項5号では、
購入・利用強制行為(同号イ)、
経済上の利益提供の要請行為(同号ロ)、
相手方に不利益となる取引条件の設置等(同号ハ)
が列挙されています。
自社の製品や利用券などを劣位の取引先に購入させたり、無償で従業員を派遣させたり、協賛金などを負担させたりする行為が典型例と言えます。また、納品予定であった商品の受領を拒否したり、在庫調整として返品したり、取引代金を一方的に減額するといったことも該当します。
これらは別途、下請法でも同様の規定が置かれています。
コメント
以上のように、2023年10月1日から新たな仕入税額控除の仕組みとしてインボイス制度が導入されました。
その目的は消費税の計算に際してより正確に税率を把握するためとされています。
しかし、これによりこれまで免除されていた免税事業者の一部についてはインボイスの発行が求められ、結果として納税義務が発生する事態が予想されていました。
今回のアンケート結果でも、有効回答1万538件のうち4370件で取引先から一方的な減額や取引の打ち切りに遭ったとしています。
しかし、上でも触れたように自己よりも立場の弱い取引相手に対し一方的な契約内容の変更などは、独禁法や下請法、またフリーランス保護法などに抵触する可能性があります。
取引先、特に個人事業主など零細事業者に対し、自社の対応に問題は無いか、今一度確認しておくことが重要と言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...

- セミナー
 森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- ニュース
- 従業員に出向先探しを1年以上させた旭化成エレクトロニクスに賠償命令 ー東京地裁2026.1.14
- 配置転換後、自ら出向先を探すよう迫られたとして「旭化成エレクトロニクス」の社員が同社に330万...

- 解説動画
 岡 伸夫弁護士
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 解説動画
 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士) 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年) 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分