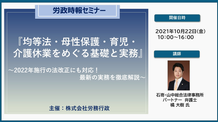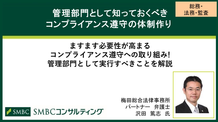小林製薬の紅麹問題で、消費者庁が検討チームを発足/機能性表示食品について
2024/04/04 コンプライアンス, 医療・医薬品, 食料品メーカー

はじめに
小林製薬の「紅麹」成分入りサプリメントを摂取した人に健康被害が発生した問題で消費者庁が1日、機能性表示食品のあり方を検討する対策チームを発足させていたことがわかりました。5月末までに改善に向けた方向性を取りまとめるとのことです。今回は機能性表示食品の制度について見ていきます。
事案の概要
報道などによりますと、小林製薬(大阪市)の「紅麹」の成分を含む健康食品「ナイシヘルプ+コレステロール」を摂取した人に腎機能障害などが発生した問題で調査の結果、去年製造された紅麹原料と製品から「プベルル酸」とみられる製造工程で想定しない成分が確認されたとされます。この問題を受け消費者庁は同社に対し、機能性表示食品として届け出ているサプリメントの安全性を再検証して5日までに回答するよう求めたとのことです。また届け出を受けている約1700業者、約6800食品についても緊急点検をしており、対策チームを発足させて制度の課題を検証し、改善に向けた方向性を取りまとめる予定とされております。
機能性表示食品とは
従前機能性を表示することができる食品は、消費者庁が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と一部の規格基準に適合した栄養機能食品に限られておりました。そこで機能性をわかりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者が正しい情報をえて選択できるよう平成27年4月に「機能性表示食品」の制度が発足しました。機能性表示食品の制度趣旨は、①安全性の確保、②表示を行うにあたって必要な科学的根拠の設定、③適正な表示による消費者への情報提供となっており、消費者の誤認を招かない自主的かつ合理的な商品選択に資する表示制度を目指しております。機能性表示食品制度の特徴は、疾病に罹患していない人を対象にした食品であり、生鮮食品を含めたすべての食品が対象となっており、安全性や機能性の根拠などが販売前に届け出られ、そしてそれに対し国は審査を行わないという点にあります。
機能性表示食品の安全性の確保
機能性表示食品の安全性の確保については、国の定めた一定のルールに基づいて事業者自身が機能性に関する評価を行い、生産、製造、品質管理体制、健康被害の情報収集体制を整え、商品の販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出ることとなっております。安全性の評価については、今まで広く食べられていたかどうかの食経験、安全性に関する既存情報の調査、動物や人を用いての安全性試験の実施によるとされます。機能性の評価については、最終製品を用いた臨床試験、最終製品または機能性関与成分に関する文献調査などによるとされます。そして生産、製造、品質の管理体制については、製造施設・従業員の衛生管理体制、生産・採取・漁獲などの衛生管理体制、規格外製品の出荷防止体制、機能性関与成分の分析方法について体制を整えることとなっております。届け出られた内容は消費者庁のウェブサイトで公開されます。販売後も消費者庁が中心となって監視を行うとされております。
特定保健用食品とは
それでは特定保健用食品(トクホ)とはどのようなものでしょうか。トクホとは食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うものとされます。トクホとして食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければなりません(健康増進法43条1項)。そして表示の許可に当たっては食品ごとに有効性や安全性について国の審査を受ける必要があり、その点が機能性表示食品との大きな違いと言えます。現在のトクホは、「特定保健用食品」「特定保健用食品(疾病リスク低減表示)」「特定保健用食品(規格基準型)」「特定保健用食品(再許可等)」「条件付き特定保健用食品」に分けられております。疾病リスク低減表示は疾病リスクの低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合となっており、規格基準型は許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている関与成分について規格基準を定め、個別審査なく基準適合性を審査して許可する場合です。条件付きは有効性の科学的根拠が要求レベルに達していないものの一定の有効性がある場合、限定的な根拠である旨の表示を条件とする場合です。
コメント
本件では小林製薬の調査で原料から青カビ由来の「プベルル酸」が検出され製造工程に問題があった可能性も指摘されております。消費者庁は同社に届け出ている機能性表示食品の安全性の再検討を求め、専門家の意見も踏まえて制度の課題の検討に乗り出しております。以上のように機能性表示食品はトクホと異なり、その効果や安全性等の評価を販売する事業者自身が行います。厳格な国の審査を受ける必要が無いことから多くの事業者が参入しております。しかし本件のように消費者に不測の健康被害が生じるリスクもあり、今後はより厳格な安全性確保のための監視体制等が整備されることが予想されます。機能性表示食品を販売している場合は今後の当局の規制強化への動きを注視しつつ、自社製品の安全性確保の体制についても見直しておくことが重要と言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- あおぞら銀行、内部通報した行員の長期隔離配置は違法 ー東京高裁2026.1.26
- 「あおぞら銀行」の行員が内部通報後に受けた懲戒処分を巡り損害賠償などを求めた訴訟で22日、東京...

- セミナー
 殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー) 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階

- 解説動画
 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌)) 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 解説動画
 大東 泰雄弁護士
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間