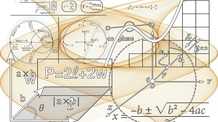認知症を支える
2011/08/22 法務相談一般, 民法・商法, その他

まずは介護認定
認知症が悪化し、介護が必要となれば市町村から要介護認定を受ける必要がある。現在、認定の後の支援の程度は段階が設けられており、要支援1~5までがある。認定を受けた支援の段階によって、利用できる介護保険の額が変わる。
認知症の場合、悪化させないために不安やストレスを与えないことが必要とされる。家庭的な雰囲気で、個室も用意されている特別養護老人ホームも存在するが、予約がいっぱいであることも多い。
その前段階として、家での介護も重要になってくるだろう。
地域活動の流れ
施設に入らないで、自宅での介護を受ける場合、これまでは家族の力で支えてきた場合が多いと考えられる。その結果、介護ストレスを抱えたまま続けるケースが多く、支える家族に過大な負担が生じていたのが現実だった。
ここで、改めて「ご近所」などの地域の力を借りることを提案したい。例えば、静岡県のある市では、認知症の母を持つ人がご近所の人と相談し、数件が「近くを通った」などの報告の形で見守りをしてくれることになった。
これからは、退職をした段階の世代などご近所のネットワークは広がっていく可能性がある。介護を支えるネットワークとなることを期待したい。
成年後見の制度
いざ、認知症になった時のために自分の財産を守る制度を知っておくこと必要である。法律上の成年後見の制度である「法定後見」の制度がある。これは裁判所の判断でなされるもので、行為能力のほとんどが制限される。ただ、被後見人と判断する基準が厳しいので少し敷居の高い制度ではないだろうか。
現在、いまだ認知症になっていないが将来に備えるのであれば任意後見の制度がある。これは裁判所に申し立てた上で後見契約を結ぶもので、代理権を与えるので急な判断能力の低下に備えることができる。例えば、急な入院があった場合、後見人が代わりに支払いをすることができる。
代理権を持つことができる者には、弁護士、司法書士などの法律家も含まれている。これからは、法律家も介護の現場を知っていくことが必要であろう。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌)) 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- セミナー
 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- ニュース
- 要件の厳格化を経団連が提言、株主提案について2025.12.11
- 経団連は12月8日、コーポレートガバナンスに関し、株主提案権の要件を厳格化すべき旨を提言しまし...
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号