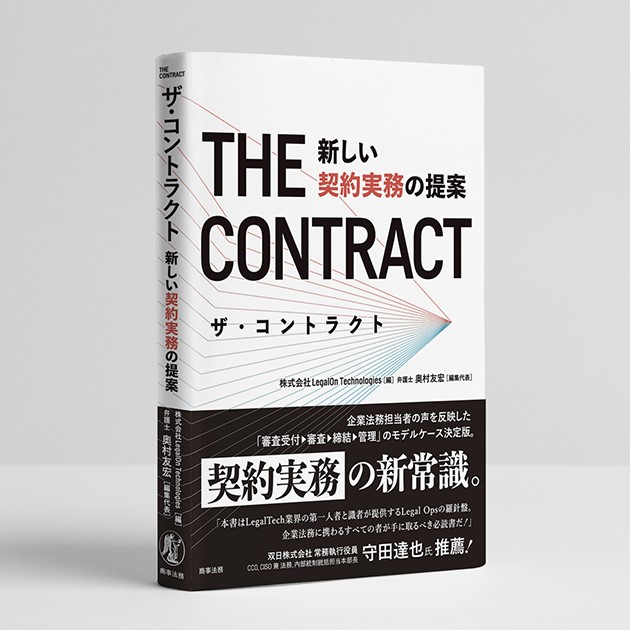法務初心者のための契約審査業務ごとの注意点(2/2)
2023/08/10

| <目次>
|
第1.はじめに
前回の記事では、契約の重要性や契約に関する業務フロー全体についての解説を行いました。今回は、契約審査業務のより具体的な注意点や効率化のコツ等を解説していきたいと思います。
第2.ビジネスシーンにおける契約の重要性
1.契約審査受付とは
契約審査受付とは、事業部門の担当者が、法務部に対し契約書の作成や審査を依頼するプロセスをいいます。契約審査受付は、単なる受付業務と思われがちなプロセスです。しかし、この段階において事業部門から必要十分な情報を入手できる仕組みとなっているかどうかは、契約業務の質と効率性において非常に重要な意味を持ちます(株式会社LegalOn Technologies「ザ・コントラクト~新しい契約実務の提案~」商事法務、2023年、31頁)。
2.ヒアリング項目の設定
契約審査受付において重要なのは、ヒアリング項目の設定です。事業部門からの契約審査受付時に、ヒアリング項目を考慮したフォーマットに従って必要な情報を全て共有してもらうことができれば、追加でヒアリングをする必要が無くなり、法務部門の業務効率は上がります。
しかし、契約審査受付のフォーマットとして、取引に関するあらゆる情報の入力を求めることにすると、必ずしも必要でない情報の入力まで強いてしまう非効率的なシチュエーションを生じさせ、事業部の負担を大きくすることになりかねません。
そのため、契約審査受付のヒアリング項目は、事細かにあらゆる情報項目を入手するという視点でなく、主要な情報に限定して情報を共有してもらうという発想から検討する必要があります。
第3.契約審査
1.契約審査とは
契約を締結する前の段階で、契約条項を精査し、リスクを事前に排除するためのプロセスが、契約審査です。契約審査を行うことにより、自社にとって有利な内容で契約を締結し、又はリスクの大きさや内容を考慮して契約を締結しないという判断をすることもできます。
契約審査は、契約リスクに直接アプローチできる点で、契約実務のプロセスの中でも中核的な意義を有します(前掲書、45頁)。
2.審査に必要な情報の確認(ヒアリング)
法務部門にて、契約審査受付で共有された情報を確認して分析をした結果、追加で共有が必要な情報があれば依頼部門にヒアリングを行う必要があります。
ヒアリングにあたっては、簡易な事項であればメッセージのやり取りで済ませ、必要に応じて口頭での話し合いをする等、依頼部門との間で円滑な情報共有ができるように心がけて情報収集をします。
3.書面の審査や作成
契約審査に必要な情報の収集の後は、ひな形や相手方提示書面を審査するプロセスに入ります。なお、ひな形や相手方提示書面が無い場合は、新規に契約書面を作成することになります。
(1) 取引実態の確認
まずは取引実態を確認し、広い視点から審査対象や方針の整理をします。
たとえば、契約の具体的な内容についての審査が求められるのであれば、売買の目的物の個数、納品方法、代金額や支払方法等の具体的な取引の詳細に関する条項につき確認をする必要があります。
審査対象の契約が自社ビジネス全体の中でどのような位置づけにあるかという点も、取引リスクの考慮材料となるため、審査に当たって留意すべき事項です。また、取引の重要性、求められる対応スピード、取引の相手方とのパワーバランスといった事項を把握することで、契約審査にかけるべき労力や、書面の審査や作成方針を適切に設定することができます。
(2) リスクの検討
次のステップとしては、契約から想定されるリスクの検討をします。ポイントとしては、取引で生じる可能性のある紛争を想像すること、契約の法的性質とデフォルトルールを検討すること、適用される各種法令やガイドラインを確認すること等が挙げられます。
一例を挙げますと、例えば、食品を販売することを内容とした売買契約においては、到着時点で食品が腐ってしまっていたようなトラブルが生じるリスクが想定されます。企業間の食品の売買契約については、民法、会社法や製造物責任法等がデフォルトルールとして適用されますので、これらの法令を前提に、上記のトラブルに起因する代金返金や健康被害に対する賠償等に関して会社が義務を負う範囲を検討することになります。
(3) 条項の検討
上記(1)(2)で検討した取引実態やリスクを念頭に置きつつ、契約書中に具体的にどのような条項を設けるかを検討します。
条項の検討にあたっては、意図している取引実態に即した条項が設けられているか、法律が定める基準より不利になっていないか、また、規制法規に抵触する条項が定められていないか等といった観点で、多角的な視点で精査を行う必要があります。この作業においては、過去に自社が締結した同種契約を参考にすることができます。自社内で過去に例のない契約を締結する場合は、同類型の契約書のひな形を基にして作成することもできます。
4.依頼部門への回答、取引の相手方との交渉
契約審査が終わった後は、依頼部門へ共有し、依頼部門は契約の相手方との交渉を行うことになります。
依頼部門へ回答する際、多くの場合は単に契約書案を渡すだけでは不十分で、審査や作成の過程で生じた懸念事項等が明確に伝わるよう、対象となる条項を特定してコメントを行います。また、依頼部門に対しては、依頼部門の意向どおりの条件になっているか、依頼部門においてどの範囲で修正や選択が可能か、取引の実態に即した内容となっているか等といった事項を確認しておくことも重要となります。
依頼部門は必ずしも契約実務に明るくはないため、担当者の理解度に応じ、できる限り平易な言葉で、ポイントを絞って説明をするといった配慮をすることで、より円滑にコミュニケーションをすることができるようになります。
5.効率的な契約審査 ー テクノロジーの活用 ー
企業によって取り扱う契約数は異なりますが、法務部は多くの契約審査をこなさなければならないことがあります。1日を争うスケジュールで事業部門が契約交渉を行っている中、法務部が時間をかけて審査をすることはできず、そのため効率的な契約審査が求められるようになります。しかしながら、効率化を求めるあまり、契約内容を精査することができず契約審査の品質が低下してしまうといった問題に直面することも少なくはありません。
効率化と品質というトレードオフの問題を解決する方法の一つとして、テクノロジーの導入を検討することができます。昨今は、リーガルテックと呼ばれる分野の発展も目覚ましく、多くの企業が契約審査のAI自動レビュー等の契約審査をサポートするサービスの導入を進めています。自社にマッチしたサービスを導入することで、契約審査の品質を保ったまま、より業務を効率化することができます。弊社の奥村弁護士が編集代表を務めた書籍「ザ・コントラクト」では、テクノロジーの活用方法を含め、契約実務における効率化のヒントになる事項を詳細に解説しています。契約審査業務の効率化に悩んでいる方へ、お勧めの一冊です。
書籍紹介
新着情報
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
 江嵜 宗利弁護士
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- ニュース
- 医学生への貸与金制度、県内勤務9年を条件とする高額違約金条項は不当 ー甲府地裁2026.1.22
- 山梨県が実施する大学医学部生向けの修学資金貸与制度をめぐり、違約金条項の差止めを求めた訴訟で、...

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- 解説動画
 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士) 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年) 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- セミナー
 殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー) 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59