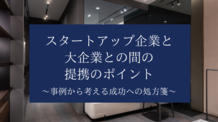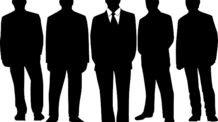【コラム】法務は社内の敵?
2022/01/25 法務部組織

法律事務所と一番仲がいい部門は法務?
前回に引き続き、法務部門のあるべき姿について掘り下げてみたい。
名前は同じ法務部門であっても、それぞれの会社で果たす役割は会社によって随分と異なるということが現実であると思っている。意外に思うかもしれないが、東京や大阪等の日本の大都市に拠点を持つ大手法律事務所(特に海外の事務所の日本拠点)が日本でイベントを行うと、クライアント企業からの出席者は、“法務部門以外の部門の人間”、すなわち非法務部門の人間であることが多い。具体的には、事業部門の担当者や他職種の管理部門の担当者等が例に挙げられる。
ここで気になるのは「なぜ、社内に法務部門を有している規模の企業であるにも関わらず、非法務部門の人間が、それほど法律事務所と親しい関係にあるのか?」という点である。
当初、私はその点を特に疑問にも思わず、「まあ、法務以外の部門から法律事務所に案件相談を持ちかけることもありえる話かな」という程度にしか考えていなかった。
しかしながら、全ての企業とは勿論言わないが、大手法律事務所のイベントに出席している非法務部門の人間の多くが普段行っていること、ひいては、そういったイベントに出席するに至る経緯を知って非常に驚いた。それは、私から言わせてもらえば、法務部門は彼ら、彼女らにとって、いわば敵とすら言える状況にあることを示していたのであった。
法律事務所を積極活用する非法務部門
これは実に意外に思えることだが、多くの場合、部外者がイメージしているほど、法務部門は法律事務所とは頻繁に付き合ってはいない。むろん付き合うこと・機会は必ずあるであろうが、法務部門以上に非法務部門の方が、法律事務所と密に接点を持っている会社は少なくない。
例えば、契約書審査などを通じて法務部門が事業展開のための決済部門の一つとなっている会社は多いと思うが、そうした会社では、法務部門の決済を通すために、事業部門が法務的な内容を説明しなければならない場面がある。そして、そのための準備や理論武装のために法律事務所に教えを請うているケースが見られる。
つまり、非法務部門が、自ら法律事務所を利用して法務部門を説得する作業を行っていることになる。本来この作業は法務部門が担うべき仕事の一つではないのか?また、これでは、社内の法務部門を説得するために事業部門が骨を折って外部の弁護士より意見聴取を行っていることになり、法務が屋上奥に構えて裁いていることになる。
これでは、法務は、企業運営上、事業の非効率化を助長するだけの不要な存在に見えても仕方ないであろう。
法務部門と事業部門の対立トピックのほとんどが「事業上のリスク判断」
いうまでもなく違法行為はいくらそれが一時的な利益に結びつくからといっても許されるべきことではなく、法務部門として絶対に阻止すべき事項である。しかしながら、経験上、法務部門と事業部門とのやりとりの大半は、違法性の有無の判断ではなく、事業上のリスク判断である。
なぜなら、事業部案件の違法性の有無の判断はシンプルに判断できるケースが多く(グレーな解釈が求められる限界事例に類するケースは少ない)、さらに、法令遵守の徹底が叫ばれている昨今の企業体制にあっては、事業部門も、明確に違法な行為を行ってはいけないという認識を有しているからだ。そのため、わかりやすく違法な事項に関して、法務部門と事業部門とで対立構造が生まれるケースは稀と言える。
かたやリスク判断というのは明確とは言えない定性的なものであることが多く、各人が主観的に判断する決まった回答のないものであるため、意見対立が生じやすく、結論を出すまでに時間がかかるケースが多い。そして、このリスク判断に対し、“法務部門”対“事業部門+法律事務所”という対立構造が頻繁に生まれている。それもこれも、結局は法務部門の意固地さゆえの問題のように感じる。
そういえば、機会こそ多くはないが、たまに契約書や法解釈で他社と揉めた時に相手方に対して「法務同士での協議」を提案することがある。だが、殆どのケースで相手方の法務より、協議の場を持つこと自体を拒絶される。そうした業務は、自分たちの本来の仕事の範疇外と位置付けているのか、はたまた、口頭の対話での協議・交渉に自信がないからなのか、本当のところの理由はわからないが、私はその度に、「企業の法務というものは、なんと意固地な存在なのだろう」と暗澹たる気持ちになったものである。
最近はあまり言われないが、欧米でも日本でもビジネスジャッジメントルール=Business Judgment Ruleという法理がある。
これは、「会社とはその事業推進のための経営判断として十分に事前に法定会議体である取締役会等で検討・準備をし、怠りなく万全を期して事業展開を行ったとしてもなお、環境変化や不測の事態の発生等により損失を発生させることは有り得るのであり、仮にその結果として失敗に終わったとしても、その場合にまで、当該経営判断の責任を問われるものではない」とするものである。全くその通りであり、それも認めないのであればそもそも人間という不完全な存在が行っている経営判断に完璧さを求めるという間違ったものになってしまうのである。
事業リスクを判断する役割も担う法務部門においても、このビジネスジャッジメントルールへの理解が必要なのではないか。
この点において、前号でも述べた「事業部門を経験した人間が法務業務を担う」ことが大きな意味を持ってくるのである。これは事業部門経験を持つ法務担当者がリスク判断に甘くなることを意味するものではなく、リスクを負う場合にはどういった内容のリスクなのか、またリスクとして許容される範囲のものなのか、仮にリスクが顕在化する場合はどう対処すべきなのかといったことを事業部門の立場で判断できるということである。
次回は続きとして法務部門と事業部門との間に存在する微妙な溝について考察してみたい。
==========
本コラムは著者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラム内容を業務判断のために使用し発生する一切の損害等については責任を追いかねます。事業課題をご検討の際は、自己責任の下、業務内容に則して適宜弁護士のアドバイスを仰ぐなどしてご対応ください。
【筆者プロフィール】
建設系の会社の法務部門に通算20数年在籍し、国内・海外・各種業法・コンプライアンス関連などほぼ全ての分野に携わった経験を持つ。事業部門経験もあり、法務としてもその重要性を事あるごとに説いている。米国ロースクールへの留学経験もあり、社内外の人脈も広い。 |
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
 加藤 賢弁護士
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- セミナー
 片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長) 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー) 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
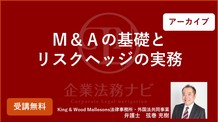
- 解説動画
 弦巻 充樹弁護士
弦巻 充樹弁護士
- 【無料】M&Aの基礎とリスクヘッジの実務
- 終了
- 視聴時間1時間

- ニュース
- 米投資ファンドが江崎グリコに「自己株式の取得」を提案意向か2026.1.21
- 米投資ファンド「ダルトン・インベストメンツ」が2026年3月開催予定の株主総会に向け、江崎グリ...

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード