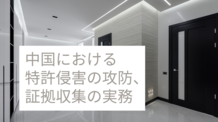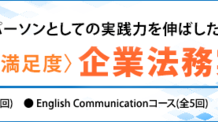SIACへの申立件数が4割増、国際商事仲裁とは
2016/06/24 海外法務, 外国法, その他

はじめに
日本経済新聞電子版は23日、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)への申立件数が過去5年間で4割増えた旨報じました。国際取引が増える中、外国企業同士での紛争も増加しております。今回はそういった国際取引紛争の解決手段の一つである国際商事仲裁について見ていきたいと思います。
国際商事仲裁とは
国際商取引において紛争が生じた場合に訴訟以外の紛争解決方法として、第三者(仲裁人)に判断を委ねる手続きを国際商事仲裁といいます。海外の企業との紛争を訴訟で解決しようとした場合、まずどこの国の裁判所に訴えるべきなのかという国際裁判管轄の問題、どこの国の法に基いて判断すべきなのかという準拠法の問題等さまざまなハードルがあります。その点、あらかじめ当事者間で仲裁機関を定めておけば紛争が生じた場合にスムーズに紛争解決に乗り出すことができます。近年国際取引での契約に仲裁機関を定めておく企業も増加しております。そんな国際商事仲裁のメリット・デメリットについて以下見ていきます。
国際商事仲裁のメリット
(1)裁定機関
上記のように訴訟による場合には、まずどこの国の裁判所に訴えるべきかが問題となります。海外の巨大企業と取引する場合には相手方に有利な専属管轄条項を一方的に飲まされることも多々あり、日本の裁判所に提訴出来る場合は限られているのが現状です。相手企業の国の裁判所に訴えても言語や法制度の違いといった障害があり、対応には相当の労力を要するでしょう。また法制度の整っていない発展途上国では公平・公正な裁判が期待できないことも多々あります。仮に日本の裁判所に訴えたとしても、相手側からみれば同様に不公正感は感じることになるといえます。その点両国の制度や言語に詳しい第三国の仲裁機関を合意により定めておけばこのような問題は解決します。どちらか一方の裁判所よりも互いに納得しやすく紛争解決により近づくと言えるでしょう。
(2)執行の可否
訴訟による場合、仮に勝訴しても実際に執行が可能かという問題が生じます。たとえば相手企業の代金不払いの場合、日本の裁判所に訴え勝訴しても、相手企業が日本国内に財産を持っていなかった場合は空振りということになります。日本の勝訴判決を持って相手企業国で執行ができるかは外国判決の承認の問題になります。日本においては民事訴訟法118条により、①当該国に裁判権があること②訴訟への呼出し、送達が適切に行われたこと③判決内容が日本の公序良俗に反しないこと④相互保証があることの要件を満たす場合に外国の判決を承認し日本で執行できます。海外においては承認するかは国によって異なり、日本の判決を承認しない国は相当数に登ります。ちなみに中国とタイは日本の判決を承認しません。その点国際商事仲裁では相手国がニューヨーク条約に加盟していれば仲裁判断により相手国で執行することができます。ニューヨーク条約には現在中国、タイも含め150カ国以上が加盟しておりほとんどの場合に執行が可能と言えます。
(3)非公開性
多くの国において裁判は一般に公開されるのが原則となっております。それ故に企業間の取引の内容や企業秘密、紛争の存在自体が公になってしまう恐れがあります。その点仲裁手続きはほとんどの場合が非公開となっており、手続き、審理、裁決が一般に公開されず機密を保護できると言えます。企業秘密の漏洩防止だけでなく、紛争を抱えていることに対する評判の悪化や株価の下落も防止することができます。
国際商事仲裁のデメリット
以上のように国際商事仲裁には多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。まず一つは国際商事仲裁は仲裁手続きであり、前提として相手方の合意を要するという点です。一方的に訴えることができる訴訟と違い、どこの国のどの機関で審理をするかはあらかじめ合意しておかなくてはなりません。相手方が仲裁手続きは利用しないと拒否すればそれまでです。そして二つ目はコストの問題です。裁判所による裁判は国家が運営していることから国費によって営まれており、費用もその分抑えられます。一方国際商事仲裁はすべて当事者が費用を負担します。一般的には両国の言語と法に詳しい弁護士が請け負うことになりますが、コストは訴訟の場合よりも割高になると言われております。
コメント
近年、国際商事仲裁を選ぶ企業は増加しており、三井物産やセイコーホールディングスもSIACを仲裁機関として採用していると言われております。訴訟手続きに比べ迅速で柔軟な紛争解決が望めることから注目を集めているようです。一方で上記のようなデメリットもあり、一概に国際商事仲裁が優れているとは言えず、場合によっては訴訟手続きのほうがコストや結果が優れていることもあり得ます。また、国によっては訴訟と同様、公平・公正な裁定が期待できない仲裁事例も存在しました。香港での仲裁に中国政府の意向が影響したとして多くの国から不信を買った事例も存在します。このように国際商取引では相手国もそれに伴う紛争も様々です。紛争が生じた場合にはできるだけ多くの手段を念頭に置き、柔軟に適切な紛争解決手段を選択することが重要であると言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- ニュース
- 飲み会でのセクハラに初の労災認定 ー大阪地裁2025.12.16
- NEW
- 会社の3次会で上司からセクハラを受けて休業を余儀なくされたとして、ITエンジニアの女性が労災認...

- 解説動画
 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌)) 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- 解説動画
 大東 泰雄弁護士
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
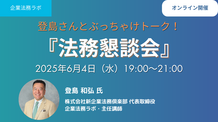
- セミナー
 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード