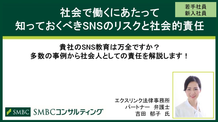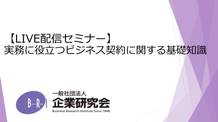企業のネット炎上対策まとめ
2017/10/17 コンプライアンス, 民法・商法

はじめに
近年、TwitterやFacebookなどのSNSでの不用意な投稿が原因となって、これらのSNSでの投稿を契機として企業が予期せぬ非難に晒されたりする、いわゆる「炎上」が注目されており、ニュースなどで見かけたこともあると思います。
今回はそういった炎上をどうやって予防するか、また、炎上してしまった場合の対応についてまとめたいと思います。
炎上のパターン
一言に炎上といっても、大きく分けて3つのパターンがあります。従業員個人のSNSが原因で炎上するバターンと、公式SNSや広告、CMといった企業の発信が原因で炎上するパターン、また、クレーム等の顧客トラブルが原因で炎上するパターンです。
1つ目のパターンとしては、従業員が業務中に不適切な行為をした場合や、業務外であってもプロフィール欄に企業名が記載されており、その結果企業に対する炎上につながる場合があります。
また、2つ目のパターンでは、発信の方針が世間の感覚とずれていて反感を買う場合や、公式SNSを担当者が私用化してしまった結果、不適切な発言をし、炎上する場合などがあります。
3つ目のパターンとしては、商品に虫が混入しており、それを顧客がSNS上でクレームとして発信し、炎上をした場合がその一例です。
以下に日本で企業が炎上した事例がまとめられているウェブページを紹介しておきます。
日本の企業・自治体ソーシャルメディア炎上事例まとめ
企業の存続危機に発展するかも!?Twitter炎上事例からわかるリスクの実態とその対策
炎上の予防策
炎上が起きないためにどういった予防策を講じればいいのでしょうか。以下、主に社内向けの予防策として、①ガイドラインや社内規程の作成、②教育研修、③監視・チェック、④個別の契約書等の4つの方策について見ていきます。
①ガイドラインや社内規程の作成
まず、SNSを利用する際の企業方針を定めた、社内向けのガイドラインや社内規程を作成しておくというのは大事なことでしょう。
ガイドラインや社内規程作成の際に注意すべき点について詳しいウェブページを紹介しておきます。
企業のソーシャルメディアポリシー・ガイドラインの作成方法
企業のSNS運用において気を付けるポイントとは
そもそも、会社は従業員のSNS利用を禁止することができるのでしょうか。就業時間中は、業務利用の場合を除き、SNSの利用を禁止しているケースは多いようですが、従業員には職務専念義務があるため、問題には当たりません。しかし、就業時間外については、基本的には従業員の自由ですので、機密情報の保持や会社の信頼を失墜させること等については就業規則等で規程しておけば禁止の対象となり得ますが、それ以外については表現の自由との関係で禁止することが難しいと思われます。
以下参考になるウェブページを紹介しておきます。
会社は従業員の「SNS」利用を禁止できるのか?
②教育研修
次に、従業員へのSNS教育研修を行うことも非常に有効です。上記の企業方針をより正確・迅速に従業員に伝えることができます。この際注意すべきなのは、業界、企業ごとに生じやすい炎上パターンが存在するので、個別にアレンジしていく必要があるということです。
以下、研修について詳しいウェブページを載せておきます。
ネット炎上からブランドを守る。企業のソーシャルメディアポリシー4選
③監視・チェック
そして、投稿の監視をして、炎上の火種がないかチェックしておくことも考えられます。勤務先を明記している従業員のSNSをモニタリングするといった方法です。しかし、これは多大な労力がかかる上に、従業員の個人アカウントであればプライバシー侵害の問題も生じうるので、慎重に検討すべきでしょう。
④個別の契約書等
また、個別契約書、誓約書を作成するということが考えられます。個々の従業員の意識に訴えかけるという点で非常に効果的な対応策といえます。ただし、従業員のSNS利用一般を制限することは企業による過剰な干渉となり、おそらく契約書の効力は認められません。そのため、約束という意味合いが強くなりますが、前述したように効果的であることには間違いありません。②で述べた研修とセットで誓約書等を提出すると効果的です。
誓約書作成例が載っているウェブページを紹介します。
実効性の乏しい対策では意味がない!『SNS問題』に関する実務対策と規定・研修の見直し
【その他参考にしたウェブページ】
ネット炎上を防ぐ!企業で全従業員向けにやるべき3つのSNS対策
企業が炎上を予防するために必要なこと10選
炎上後の対策
適切な対応
では、実際に炎上してしまったら、どうやって対応すべきなのでしょうか。
まず、炎上の火種を特定し、対応を決めることが必要となります。対応としては、問題となる情報の削除、SNSアカウントの停止、静観、謝罪、あるいは弁護士や警察へ相談すること等が考えられますが、その中から適切な対応を選ぶことが何よりも大切です。
ただし、SNSアカウントの停止については、公式アカウントであれば自主的に停止できますが、従業員の私的アカウントの場合、停止という措置をとるのは表現の自由の観点からも難しいでしょう。
見極め方についてまとめられたウェブページや過去に起きた事例とその対応がまとめられたウェブページを紹介しておきます。
炎上させない、しても慌てない、ソーシャルメディア防災マニュアル
企業の存続危機に発展するかも!?Twitter炎上事例からわかるリスクの実態とその対策
削除できる場合
問題となる情報の削除は、どのような場合にできるのでしょうか。
具体的には、企業に対する誹謗中傷が行われている場合に、名誉権(人格権)に基づく妨害排除、または予防請求権として差止請求を根拠として、当該誹謗中傷が掲載されているサイト等に対して情報の削除請求を行うことができます。
ここで注意しなければならないのは、弁護士ではない削除代行業者が依頼を受けて削除請求を行うことは、弁護士法違反になってしまうということです。
したがって、削除請求を行う時は弁護士に依頼することが前提となります。
この点について詳しくまとめられているウェブページを紹介します。
削除代行業者による削除請求は弁護士法違反!裁判で返金請求できる
最後に
以上、炎上の予防と対応について見てきましたが、炎上が多発したことでここ最近は炎上対策について社内の法整備やガイドラインが整ってきています。
しかし、新しいパターンの炎上が発生することも考えられますし、企業側としても注意を怠らず、法整備やガイドラインを常にアップデートしていくことが望まれます。
特に、PR部や広報部などSNSを利用する部署、クレーム処理を行う部署、社内全体を熟知している総務部、法務部等が部署等を横断して議論していくことが必要となります。
【紹介したウェブページ以外の参考資料】
「炎上の類型別対処法」早川明伸(Business Law Journal 2017/10 No.115 Lexis Nexis)
「インターネット上の誹謗中傷への法的対応」北岡弘章(同上)
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階

- セミナー
 片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長) 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー) 板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- 解説動画
 浅田 一樹弁護士
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 解説動画
 大東 泰雄弁護士
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士

- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- ニュース
- 株主総会書面決議9割賛成で可決へ、会社法改正の動き2026.1.19
- 株主総会における「みなし決議」の要件を、全会一致から議決権の90%賛成へと緩和する方向で、会社...